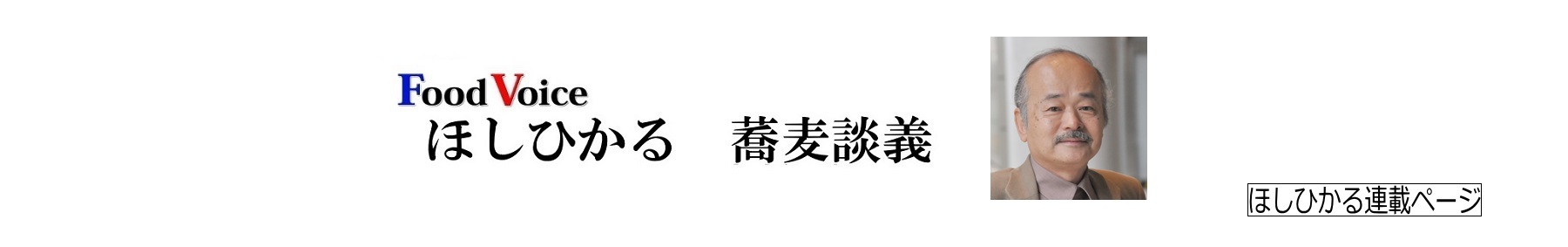第304話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅲ」
2025/12/06
~ Mr.Wonderful ♪ ~
銀座5丁目の〔クラブ恵子〕が入っている白いビルの前でタクシーが停まった。車から下りてきたのは、野中健とキリスト大学病院の山田教授と東京国際総合病院の河村部長だった。
先ほどまで三人は、赤坂の〔山小舎 洋灯亭〕でタータルステーキと赤ワインを楽しみ、そして今は山田教授行付けの〔クラブ恵子〕に繰り出したところであった。
野中はタクシーの前の座席から後を向いて念を押した。「河村先生、今後ともよろしくお願いしますよ。」
「ああ・・・・・・、」
今夜は、野中が山田教授に頼んで、山田教授と東大の同期の河村部長を誘ってもらったのだ。それなのに河村の返事は要領を得ない。
野中は大学病院や大病院を担当するようになってから、東大閥の鉄骨のような堅固さを知った。主要な国立病院、公立病院の要職は東大出身の医者で押さえられている。しかもその縄張を堅持するために、結束も堅い。その堅さを活用させてもらおうと思っての今夜の接待だった。
しかし観ていると、同期コンビといっても、この二人は、あの大村病院の院長と副院長の私大医学部同期と同じようにはいかないようだ。山田教授は日比谷高 → 東大医学部 → 東大医局の、バリバリのエリートコース。河村部長は優秀な高校ではあろうが地方の県立校 → 東大医学部 → 東大医局、同じエリートでも、日比谷高分、山田教授が頭一つリードしている感じだ。たぶん河村部長はそれを良しとはしていないだろう。だから同期の山田から野中という男を紹介されたことも、「ああ」という程度の生返事だったのだ。
三人が乗ったエレベーターは7階でドアが開いた。
「せんせーい。」山田教授お気に入りの徳子が背の高い山田の首に抱きついて、手を引っ張って席へ案内した。
前もって野中がクラブに電話を入れておいたのである。
河村も何度か来ているようだ。すぐにナオミというホステスが河村を見つけて「せんせーい、おひさしぶりー」と飛んできた。
徳子は何人かのホステスに指図して山田と河村の周りに女たちを侍らせた。
〔恵子〕は銀座でも指折りの高級クラブだ。いずれも流麗な和服や高級なドレスに身を包んだトップクラスの美女ばかり。
部屋は落ち着いた木目調の壁と厚い絨毯。ソファは沈むように深い。野中は初めて山田教授に連れて来られたときは気後れしたものだったが、今は慣れた。
「カンパーイ!」
野中は、少し離れた所のソファに身を沈め、水割の入ったグラスを隣に座ったホステスのグラスと合わせた。店の中では一番おとなしい。
山田教授も河村部長も着飾った女たちに囲まれ、上機嫌だった。
「後は、ホステスに任せればいい。」野中は立ち上がってトイレに行って、そのまま離れた所のカウンター席の椅子に座った。
バーテンがお絞りを差出し、野中が座っていたテーブルを見て、同じ水割を作って置いてくれた。
野中がこのクラブに来たのは4回目だが、徳子のことはあまり知らない。自分と同じぐらいの30歳前だろうか。何とかいう彫りの深い女優に似た美人だ。というよりも、徳子は〔クラブ恵子〕のナンバーワンのせいか、ホステスの中でも輝くような存在感があった。
以前、病院部の先輩に菅原という伝説の営業マンがいた。菅原は昼間は寝て、夜になると出勤するという猛者だったらしい。背広は何着も持っていて、一度締めたネクタイは使わない。床屋には一週間に一度のペースで行っていた。ホステスなみだ。接待の前日は当日の接待とまったく同じコースの店を回って、事前チェックをしていたという。多少の尾鰭は付いた話かもしれなかったが、大学病院の教授たちと夜の銀座を肩で風を切って闊歩していたのはまちがいない。
菅原をライバル視していた他の先輩が「あいつは、医者の〝財布〟だよ」と皮肉を言っていた。
野中も、「昼は寝てて、夜出勤なんて、ああはなりたくない」とも思っていた。
営業は言葉ではない、行動だ。これが会社の風土だった。しかし、隙のない菅原のやり方を見れば、行動というよりも細心のプロデュースだという気がする。それはそれで納得する。〝財布〟もその中の一つだろう。ただし、それをライバルの先輩が「あいつは財布だ」と言い切ったところに、菅原先輩の問題点があるのかもしれないと野中は考えていた。しかし、その菅原は他の会社にスカウトされ、今はいない。また、その後の噂も耳にしていない。
病院部にきてから野中は、一人前に銀座のクラブの十数軒には顔を出していた。でも贔屓の店、常連の店はないし、作ろうとも思わなかった。
美味しい食事処を見つけてくるのは営業マンの仕事だが、クラブは医者の行付けの店に付合っていた方がいい。馴染みのクラブなんか作って案内すれば、バカなホステスは医者より自分をちやほやしてしまう。それでは折角の接待も台なしとなる。
それにしても、医者を接待する度に思うのは、夜の銀座は権力と金を持つ者の棲む世界だ、ということだった。
先ごろ、麻布にある行付けのスナックのヘラヘラしたボーイが言っていた。「お客にはね、『シャチョウ!』とか、『センセイ!』って、言ってりゃいいんですよっ」
「社長と先生はどう違うんだよ?」
「カネ持ってる奴が『シャチョウ』、エライ人が『センセイ』ですよ。」
「ハハハ、分かりやすいナ。」
エライというのはもちろん偉人という意味ではない。権力を握っている者とか、そういう職に就いている者という意味だ。医者、弁護士、教授、役人・・・・・・とかだ。だから彼らにはスポンサーがついている。
「どっちでもない奴は?」
「センパイですよ、野中センパイっ」
「プッ」
そのボーイは一週間で店をやめたが、また何処かでヘラヘラと過ごしていることだろう。
違う客を見送ったママの恵子が、カウンターにいる野中の隣にやって来て座った。和服から、いい香りがする。客はテレビで見たことのある顔だった。たぶん政務次官クラスの政治家だろう。
「野中さん、お久しぶりね、」
そう言いながら、ママの手が野中の膝の上にいく。しかしそこまでだ。膝の上の手は冷たかった。スポンサーへの挨拶にすぎない。ママも野中もそれを心得ている。ママは30歳少しぐらいだろうか。徳子やナオミのハデさはないが、色っぽさと小粋さは抜群である。
野中はママに怖さを感じた。それは、前回来たときの帰りの車中で、山田教授が言ったことを思い出したからである。
「あのママには手を出さない方がいいぞ。」接待の後、料理の方は美味しかったとか評するようなことをお互いに言ったりするが、クラブの女たちについては触れない方が何かと無難なのである。大袈裟にいえば暗黙のマナーみたいなものだが、それを山田医師は破るようにして言った。「徳子が言っていたけど、昔、ママの男が自殺したことがあるそうだ。あのママは銀座でも指折のすごい女だって。われわれには手が出ないよ。」
野中は、恵子ママの横顔を見た。鼻筋が通っている。それに背筋もピンの伸びて凛としている。近寄り難いぐらいの美人だ。野中は「自分には関係のない世界だ」と思って、首を振った。
そのときピアノ弾きの女とサックスを抱えた男が入って来た。女性は長い髪をしていた。男は体格がいい。
この店では、時々生演奏をさせる。
男がすぐにサックスを吹き始めた。
野中の耳には聞き覚えがあった。たぶん映画『アルフィー』のテーマだ。
「ソニー・ロリンズか。」野中が小さく呟くと、「そう、いいわねえ」とママが相槌を打った。
野中はママの言葉に少々驚きながらも、サックスの広い音にほっとしていた。
終わってから野中は、心から拍手をおくった。
横で、ママも拍手をする。
そのとき河村がピアノの所へ近づいていった。「歌いたい」と言っているようだが、この店は、それをさせない。だからマイクはない。
長い髪の女の子がママの方を見た。「どうすればいいか?」と目で訊いている。
ママは笑みを送って、肯いた。
サックスが前奏を始めた。「ブランデーグラス」である。話題の〔クラブ姫〕のママ 兼 作詞家の山口洋子が作った歌だ。
面白いことに、銀座の女の子たちは山口洋子の話はほとんどしない。ライバル視しているからだろうか。その証拠に銀座と離れた新宿のホステスたちは「頭のいい人は違うね」と言ったりしている。
河村は堂々と歌う。やや太り気味の河村は声量があった。マイクがなくても十分である。
「まったく頭のいい連中は何でも巧くこなすナ」と野中は舌を巻いた。
ホステスはもちろん他の客も、盛大な拍手を贈った。
歌い終わった河村は席に戻った。
「先生、すごーい。お上手、」徳子たちが称え、席はますます賑わった。
野中は徳子とあまり話したことがない。でも、初めて会ったときは驚いた。昔、付合っていた由利子という女にそっくりだったからである。しかし、徳子と握手したりして、その感触が由利子とは全く違うのを感じてから、他人の空似だったと納得していた。それでも、野中は徳子をちらりと見て、由利子のことをまた想い出していた。
そんな野中を見て、隣のママがほんの一瞬だが頬に笑みを浮かべた。
暫くしてから、山田と河村が「そろそろ切り上げるか」と野中に声をかけた。
野中がハイヤーを頼もうとすると、山田が言った。「野中君、車は一台でいい。河村とちょっと話があるから。」
「分かりました。」
たぶん、東大系列の病院人事の話だろう。
車が来たというので、皆はエレベーターに乗った。
エレベーターは各階で停まる。このビルは全てがクラブばかりだ。だから停まる度に各階は客を見送るホステスで華やかだ。それでもエレベーターに乗った男たちは各駅停車を楽しんでいる。ホステスに腕を組まれたり、手を握られたりしているから時間がかかっても平気なんだろう。
その中で河村が感心したように呟く。「このビル一つにいったい何人の女の子がいるんだ。」
山田が答えた。「9階まであるから、100名、200名はいるだろう。」
「このビルだけでか! 昭和の大奥だな」と河村が首を竦める。
「先生、浮気しちゃダメよ。お局様がお仕置きしちゃいますよ。」ナオミが河村の頬を抓る真似をした。
河村も「イテテテ、分かった、わかった」とワザとらしく言う。
みんなが笑った。
帰り際、河村が野中に言った。「野中君、世話になったな。」
歌ったためか、女の子に煽てられたためか、気分でもよくなったのだろうか。それとも「山田は山田、私は私。直接、私の所へ来なければ、面倒は見ないぞ」とでも言ってるのだろうか。
「ありがとうございます。お気を付けて。」野中は頭を下げながら、そう思った。
車を見送ったママが「野中さんはまだいいじゃないの」と言うと、徳子とナオミが「そうよ。先生が言ってたけど、野中さんまだ花の独身でしょ。遅くなったからって怒られることもないから、いいでしょ」と腕を引張るが、そうはいかない。この店は山田教授の店だ。「いや。また来るよ」と言って、野中はその場から離れた。
野中は問題を抱えていた。
キリスト大学病院の営業成績が伸びないことである。
理由は分かっている。この大学病院は、投薬日数と投薬量が少ないのだ。
野中は社内営業会議でも説明した。
キリスト大学病院は、たとえば3錠×3日分投与が多いから=9錠しか出ない。
一方、自分の優良得意先である、東京消防中央病院はといえば、6錠剤×14日分投与が普通だから=84錠が出る。同じ労力を費やしたとして、東京キリスト大学病院の、9倍の数字を獲得できる。
本当はこんな説明は言訳しているようでやりたくない。だが、それを話すことは、部下や後輩たちに病院によって戦術を考えろ、と言いたかった面もある。
しかし病院部長にはそれが通用しなかった。
「3錠投与を6錠投与に、3日投与を1週間投与、2週間投与にしてもらうのが営業だろう」と子供が言うようなことを平気な顔をして言う。
野中は唇を噛みながら、逆に遠慮などせずに言ってよかったと思った。
病院の医者は病院のルールの中で処方をする。一人王様の開業医じゃない。外部の者が、それも営業員が口説いて変れるなら、苦労はない。「そういう問題点を共有しなければ」と言えば、部長は「マイナスばかりに目を向けるな」と追い打ちをかける。
対して野中もさらに反論しようとするが、営業は議論じゃないと思って、止めた。営業は、数字が出なければ、屁理屈とみなされる点はあるにはあるものだ。
初秋のころ、野中は、西銀座クリニックを訪ねた。そこは東京消防中央病院の循環器科の遠藤医師のアルバイト先だった。
野中の会社は、東京消防中央病院の外科には強かった。この夏も医局全員、バスを貸し切っての湘南へ海水浴に行った。もちろん費用のほとんどは当社負担である。しかし、効率はよかった。1年に一度のサービスで安定した実績が得られる。ただ、これは野中の前任者が組立てたものだった。
だから、野中はプラスして循環器を開拓しようしていた。遠藤富士子医師は循環器科の医局長だった。しかも部長の山本医師に信頼されているとの話を聞いていたから、彼女からアプローチしてみようと思ったのであった。
クリニックに遠藤医師を訪ねるのは三度目であった。野中は、もうそろそろいいだろうと思って。昼食に誘った。
「いいわ。地下に〔生粉打ち亭〕っていう蕎麦屋があるから、そこで待ってて、そのかわり2時よ、大丈夫?」
近辺にある会社の昼休時間に患者さんが見えるから、どうしてもその時間になるのだろう。
「いいですよ。」
野中は同じ地階にある本屋で時間を潰してから、1時半に〔生粉打ち亭〕に入って、理由を言って待たせてもらった。
女の店員が「蕎麦湯です」と言って、猪口に入った飲物を持ってきた。
野中は週刊誌を捲りながら、茶碗を取って、飲んだ。
「不味い」と思った。野中は蕎麦湯を飲むのが初めてだった。お粥の汁だけのような変な感触である。
手にした週刊誌には栞が挟んであった。開くと〔生粉打ち亭〕の店主の写真が載っていた。「ラケットを麺棒に替えて ~ 元テニスプレイヤー菊地志郎さん」という見出しだった。元テニスの選手だった菊地さんは怪我で引退した後、蕎麦打ち修業・・・・・・、会津魂でやってきた・・・・・・」みたいな記事だった。陽に焼けた顔、白い歯、確かにここの店主だった。
「脱サラして、手打ち蕎麦店、コーヒー専門店、続々開業」なんていう記事を目にしたのは、経済新聞だったか、経済誌だったか。
そんなことを思っていたとき、白衣を脱いだ遠藤医師が入ってきた。2時少し前だった。美人とまではいえないが、健康そうで、スタイルもよかった。
「このビルは食べる所はここしかないのよ。お蕎麦で大丈夫?」
「僕は麺類が好きですから、大丈夫です。」
「そう、よかった。」
「先生こそ、女性で和食っぽいものなんて、珍しいですね。」
「私、会津出身だから、お蕎麦は毎日でもいいの。ここ美味しいのよ。ね、菊地さん!」
「そりゃもう、美人先生のために愛情込めて打ちましたから。ハハハ、」
店主が白い歯を見せながら言う。
「あの店主も会津なのよ。それで?」
「それで、って。先ずは頼みましょうよ。」
「用があるから呼び出したのでしょ」と言って、近寄ってきた店員に「天ざる」と注文する。
店員が野中の方も見る。
野中も「同じく」と答えてから、「呼び出した、わけではありませんが・・・・・・、」
「はっきり言いなさいよ。できないことはできないって言うから。」
「部長先生にお会いしたいのですが、どうしたらいいかというご相談です。」
「あっそう、分かったわ。でも、部長はいまアメリカなのよ。」
「えっ、そうなんですか。学会ですか?」
「そう。だから、少し待ってて。」
「はい。」
「お蕎麦、どう?」
「はい。美味しいです。」
「菊地さん、美味しいんだって。」
「ありがとうございます。」
「また来て上げてね。」
正直に言って、野中は蕎麦を食べた記憶があまりなかったから、美味しいのか、そうでないのか、よく判らなかった。ただ、蕎麦の野趣を帯びた味はわるくないと思った。
野中が蕎麦屋を出てから、離れた所の駐車場まで戻ろうとしたときだった。〔クラブ恵子〕のママにばったり会った。先に見つけたのは野中だったが、ほぼ同時ぐらいにママも「あら」というような目をして野中を見つけた。
恵子ママはタイト・スカートにハイヒールだった。
「いやだわ、こんな格好のときに会ったりして、」と照れながらも、「野中さん、お茶でも飲まない♪」と誘った。
二人は裏通りの〔バッハ〕に入った。
目の前に座った恵子は、夜の席とちがって、ずいぶん若そうだし、庶民的な可愛い顔をしていた。夜の和服姿も、小粋さも作ったもので、こっちが本来の姿だったのか、と野中は感心した。
ママはハンドバックからロングの〔パーラメント〕を取り出した。
野中はライターで火を点けてやりながら、「今日は何ですか?」と尋ねる。
「お買い物。明日は集金で回るから、お客様に何か手土産でもないかな、と思ったの、」ママは煙を吐き出しながら、答えた。
クラブのホステスもわれわれと同じようなものだ。重要お得意先があればあるほどいい。ママやナンバーワン・ホステスなどは、重要得意先をたくさん抱えているだろう。その得意先とは、〔クラブ恵子〕ともなれば、それこそ「シャチョウ」か、「センセイ」ばかりだ。特に、金のあるシャチョウ族に夜の蝶は甘い密を求めるように群がるが、そのためには女としての特色を活かしながら変身する。セクシーな女になったり、色っぽい女になったり、可愛い女になったり、優しい女になったり、小悪魔のような女になったり、情の深い女になったり、面倒見のいい女になったり、気風がよかったり・・・・・・。だから夜の女は女優みたいなものだ。しかし、うっかりすると、女の方だってジョーカーを掴ませられることがある。女たちに吸い尽くされても、病みつきになって通ってくる中小企業のオッサンたちにだ。そういうオッサンたちの金庫が空になっているのも気づかないでいると、ホステスは肩替りをしなければならない、ナンバーワンともなれば、その金額は並大抵ではない。高級マンションの2~3軒ぐらい楽に買えるだろう。ただ借金とはいえ、多額の金の世界に浸っているということ事態がまた「女の勲章」にもなるというから夜の世界は摩訶不思議な所だ。ただし、それは筋が悪質でない場合だ。下手をすれば海の底に沈むことにもなりかねない。江戸時代の遊女と同じだ。美女だから海中を泳ぐ人魚になったのかと冗談を言っている場合ではない。
その点、センセイ族は危険がない。なにせ財布はスポンサーだ。たとえば、大病院のエライ先生と製薬会社、こういう関係が、取りっ逸れることがなくて一番安全だ。それにセンセイ方は賢いから、毒を察知すれば自ら遠ざかってくれる。
今日の恵子が庶民的に見えるのも、野中がセンセイでもシャチョウでもないサラリーマンの身だから、そうしたある種の緊張感をもつ必要がなかったせいでもあるのだろう。
野中は店でのことを想い出し、尋ねてみた。「ママはジャズ、好きなの?」
「好きよ。でも、一人で聴くのが好き。」
「僕と同じだね。」
「ふふ。お互いに残念だったわね。」
「そう、残念だった。はは。」
ママは吸いかけの煙草を灰皿に置いて、訊いてきた。
「野中さんは、慎重なの? 真面目なの? リアリストなの?」
野中が山田教授としか店に来ないことを言っているのだろう。
ママの煙草には紅い口紅が付いていた。
野中はそれを見ながら「リアリスト?」と鸚鵡返に呟いた。
「そう、リアリスト。」
そんなことを言われたのは初めてだと思いながら、「真面目は真面目ですよ。」
「そうよね。初めてお店に見えたとき、ちょっと驚いた。」
「どうしてですか。」
「きちんと、私にご挨拶されたでしょ。そんな方は初めてよ。」
野中は何て返事すればいいだろうと考えていたとき、ママはいきなり突いてきた。
「野中さんは、徳ちゃんのことが好きなの? それとも・・・・・・、もっと若いころ徳ちゃんと似た子で失敗したの?」
野中はムッとしたが、抑えながら黙ってカップを持って、珈琲を飲んだ。
〔キャラバン〕の親父は、「美味しいと噂を耳にすれば、その店の珈琲を飲んでみることだ。自分の舌で確かめることだ。それが勉強になる」とよく言う。
だから、この〔バッハ〕の珈琲も何度が飲みにきたことがある。
その度に「うまい」と思う。
「珈琲、美味しいね。」
ママは敏感だった。「ごめんなさいね」と一旦引いた。
野中の頭には、山田教授の言葉が過っていた。「昔、ママの男が自殺した。」
レコードの「ブラック・コーヒー」が小さく聞こえてくる。歌っているのはペギー・リーだ。
ママは謝りながらも自分の観察が正しかったと確信したように、野中を優しい目で見つめていた。
野中はその視線も身体で受けて落ち着かなくなり、「行こうか」と言った。
「怒ったの?」
「そんなことないよ。」
「そう。私、傷つく前の野中さんを知りたかったわ。」
そう言うと、ママもバッグを手にして立ち上がった。
野中は伝票を取ろうとした。
すると「いいわよ。私が誘ったのだから」と指で伝票をすっと摘まみとって、高そうなバッグの口を開けた。
外に出たとき、ママはまた同じようなことを言った。「もっと早く会いたかったわね。」
その言葉に胸の高鳴りと少しだけの怖さを感じながら、野中は半歩先を歩く恵子の白い襟足を見つめた。
恵子は「ふふ」と笑って振り向いた。「こういう台詞、一度言ってみたかったのよっ。」
不思議な女だ。野中の中にドンドン入って来る。何のために? 銀座で屈指の恵子ママなら、大臣クラスや財界人の客がいっぱいいるだろう。オレみたいな安サラリーマンからは何も獲れない。そう思いながら、強い口調で切り返す。「いつも言ってるんじゃないの。」
「そんなことはありません。」恵子も強く否定した。
野中は少し口を噤んでから言った。「でもね。歳月は戻らないっていうから、逆に『3年後に会いたいわ』と言ってみれば、」
「へえ。そんな台詞があるの、初めて聞いたわ、」
「言葉だけ、」
「ンもう・・・!」恵子は野中の後に回ってバッグで尻を叩いた。
「ははは。」
「あんがいキ・ミ・の傷は浅かったようね。また会ってね♪」
野中の心臓の部分を指で突きながら微笑む恵子の目はいつもの艶っぽい目付に戻っていた。
野中は病院部の部長に呼び出された。
「キリスト大学病院だけどな、常務が『担当を変えてみたら』とおっしゃってる。俺もそう思うけど、どうだろう。」
野中は腹の中で可笑しかった。前に提案したときは「そこを何とかするのが営業だろう」と言っていたけど、役員がいえば「俺もそう思う」になる。
それはともかくとして、「大学ですから、ちゃんとした先輩あたりに担当してもらいたいですね。」
「鈴木はどうだろう。」
部長は聞いていない。鈴木は佐藤と同期の後輩だ。たぶん牧田常務の意見だろう。
野中は、常務も大学病院の価値が分かってないなと思ったが、もしかしたら、一か八か的な賭けに出たのかもしれないとも思った。それは鈴木がユニークな男だったからである。
鈴木はヤンチャなピエロ、あるいはイタズラ小僧みたいな役割を演じながら、医者に可愛がられていた。
最近聞いた話では、ある病院の医者専用の駐車場に行って、医者の車のサイドミラーに製品名の入ったシールを貼ったというのである。
医者たちは「運転中、サイドミラーを見たら何かおかしい。停まって見てみると、シールが貼ってあるじゃないか、驚いたよ」と大笑いしたというのである。
医者というのは、非常識なことをする者を呆れながらも、かえって許すところがある。自分とはまったくちがった人種と見るせいもあるだろうが、鈴木自体にもどこか可愛げがあったから、皆「わかったよ。その製品名は覚えたよ」と苦笑しながら言うのである。
だからといって、こんな離技は誰にでもできるわけではない。鈴木しかできない専売特許であろう。
野中は、常務の考えにも一理あるが、たとえうまくいったとしても大学病院を相手にする策ではないと思った。
しかし野中は鈴木に「イヤだったら、いつでもオレに戻していいよ」と言うしかなかった。
鈴木は「はい。課長、そのときは助けてください」と憎めない顔をして言った。
野中はこの春、課長になっていた。ただ営業所とちがって、病院部は課長といっても一営業員だった
野中は鈴木と引継同行をした。山田教授も紹介した。これで、恵子ママや徳子に会えなくなるのが、少々残念なような気がしないでもなかった。
しかし、それよりもこの大学病院を手放すことが良いのか、悪いのか、野中自身にとっても賭だと思った。
一週間後、野中が循環器科の医局に顔を出したとき、遠藤医師が野中をつかまえた。
「部長がアメリカでの学会報告をやりたいって言ってるの。」
「どういう所でやりますか?」
「何処かスライドが映せるような部屋を取って、後は食事会というのはどう?」
「だったら、個室のある中華料理店ですね。」
「じゃ、それでお願い。で、そのときの説明資料としてスライドを作ってほしいの。」
「わかりました。」
「イエスだろうと思って、野中さんのことは部長に話しておいたから。」
「ありがとうございます。」
「だから部長の所へ行って、資料をもらってきて。」
その日、六本木の上海料理店の個室に部屋をとって、医局員と野中を入れた10名が椅子に座った。医師は6名、部長・医長・医局長・医局員3名だ。それに心電図やレントゲンの技師、秘書なども加わっている。
野中は、この医局のやり方に驚いた。一般に医局会に技師が加わることはあまりない。仮にあったとしても、秘書という事務方までもが入ることなどありえない。それが、この医局では同席しているのである。
とにかく、そんなメンバーで報告会が始まった。最初は部長に随行した黒木医師だった。その内容は出発する前に発表していたから、簡単に済まされたが、ボストンの大学で開催された学会会場ではどういう質問があったか、他に似たような研究発表や参考になる症例はあったかなどが質問され、論議された。
そして次が部長の番だった。野中はこれにもまた驚かされた。
3年前、6年前、9年前、12年前の学会の演題を一覧表にして、その変化から疾病、治療法の予測をしようというのだ。企業のマーケッティングと同じ手法だ。その後は半時間ほど議論が進み、最後に部長が「野中君、意見はないかね」と質問を向けた。
野中は自分なりに思い付いた薬剤の方向を述べてみたが、部長は何もコメントしなかった。どうやら的外れだったようだ。だが、野中にとって今日の医局会は驚きの連続であった。
しかし、翌日はもっと驚かされた。部長に挨拶に行ったときだった。
「昨日の報告会のことをレポートにして、会社に提出してみたらどうか」と言われたのである。
野中は文章など書いたことがない。困ったが、仕事だと思って、一晩かかって集計用紙に経緯と昨夜の報告会の内容を書いて部長の所へ持っていった。
部長は紙を受け取ってチラリと紙に視線をやるや、「君、これはメモかね」と言った。
野中はがっくりと肩を落とした。
部長は右手を本棚に伸ばし、一冊の本を取って、テーブルの上に置いた。中根千枝の『タテ社会の人間関係』だった。
「これを持っていって、しっかり目次を研究したまえ。一部上場会社の課長が、これでは困るんじゃないの。」部長はそう言い残し、病棟へ行った。
入れ代わって、秘書の上村さんが茶碗を下げに部屋へ入ってきた。「部長は、野中さんにレポートの書き方を教えようとしているのよ。知ってるでしょう、この医局は〔山本学校〕って言われているのを、」
上村さんは背が高くてスラリとしている。
野中は顔を見ながら「あ、そういうことだったの」と低い声で返事をした。
このとき遠藤医師も通りかかった。
「この医局に出入りする人は、みなさん山本先生のスタッフになるの。でも、勉強になるわよ。それが嫌だったら早めに退散することね」と言って、上村さんと一緒になって笑った。
野中は〔キャラバン〕で珈琲を飲みながら、『タテ社会の人間関係』の目次を何度も見ていた。
親父が「野中さん。何、勉強しているの?」と声を掛ける。
「いや、別に」と言いながら、野中は社長の友人である瀬戸内隆が社内で講演したときのことを思い出していた。
瀬戸内隆という人物は戦時中の大本営の参謀で、東大の学生時代には秀才の名をほしいままにしていたという伝説じみた男だった。その瀬戸内先生の話は約100分、当然、演題もあった。
最初に瀬戸内は言った。「これから10項目についてお話します。先ず、○○についてお話しましょう。」それが終わると「次は△△について」。「次は××について」、「次は□□について」という具合に、10項目を話していったのである。
瀬戸内隆の表情には温和さと冷たさの両方があった。そのうえ周囲を圧するような風格もあった。
講演後、病院部長は心酔したような顔をして言った。「瀬戸内先生はやっぱりすごい方だよな。社長がおっしゃっていたけど、先生が話されるとき録音しておいて、テープ起こしすれば、そのまま本になるくらい筋が通っていて、まとまっているんだってさ。やっぱり秀才だよな。」
野中は〔キャラバン〕の珈琲を飲干してから、近くの大きな本屋の寄ってみた。本棚から真面目そうな書籍を引張出し、目次を調べた。
良書ほど、その目次は題名に向かっているように思えた。
翌日、野中はレポートらしきものを書いて、山本部長に見せた。
山本医師はさっと目を通してから「目次立ては、箱を並べるところがコツだよ」と言って、机の上の原稿用紙に長方形を5個描いて、その上にまた大きな長方形を描いた。そしてその大きな長方形を鉛筆で指しながら、これが題名、そしてこれが目次。これを解決するのに、どういう項目が必要か? これを語るのに、どういう項目が必要か? それを考えるのが、目次立てだ」と言いながら、5つの箱、各々を線で題名と結んだ。
野中は頷いていた。
部長が静かに言った。「だいぶ良くなったけど、結論が甘い。もう一度やってみたまえ。」
「はい。ありがとうございます。」
病院を出た野中は、何かこの充実したような感覚を大事にしたいと思う気持がわいてきていた。それは、これまでのお得意先を攻略したときとは一味違った感覚であった。野中は急に〔らんぶる〕の珈琲を飲みたくなった。〔キャラバン〕の飽きない味とは違う味の珈琲を今は飲みたかったのである。野中は車を運転した銀座へ行った。
ドアを開けると、店内は珈琲と煙草の匂いに包まれていたが、席は空いていた。野中は座った、そこは恵子と座った椅子だった。
たまたまなのか、また「ブラック・コーヒー」の曲がかかっていた。今日はジュリー・ロンドンである。
野中は〔マイルドセブン〕を吹かしながら、ジュリー・ロンドンの歌い方と恵子ママの話す雰囲気はどことなく似ているなと思ったりしていた。
そのとき〔バッハ〕のドアの開く音がした。
野中は煙草を銜えたまま、何気なく振り向いた。すると煙の向こうに恵子が立っていた。
(Ⅳへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる:作〕