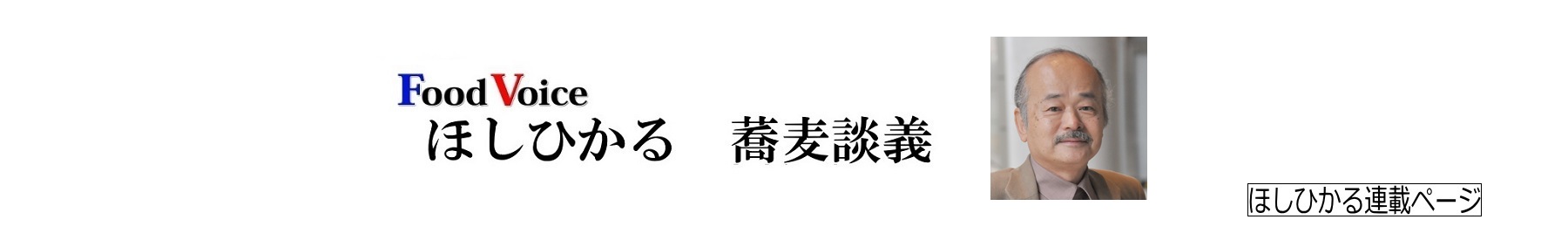第305話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅳ」
2025/12/06
~ Lovin’you ♪ ~
築地の高級マンションの一室だった。
恵子はステレオのスイッチを回し、何枚かのレコードの中から何となくペギー・リーを選び、盤をターンテーブルに乗せて回転する溝にピックアップをそっと置いた。それからソファに座って〔パーラメント〕に火を点け、煙と一緒に小さな溜息を吐いた。
それから窓に寄添って、外の景色をぼんやり見るともなく見ながら、ペギーリーと一緒に〔Mr.Wonderful〕を口ずさんだ。
Why this feeling, why this glow
Why the thrill when you say hello
It’s strange tender magic you do
Mr.Wonderful あなたのことよ♪
一曲終わったとき、ふと恵子は〔らんぶる〕に珈琲でも飲みに行こうかと思った。でも今日の美容院の予約は午後3時である。ついでに行くにはまだだいぶ時間があった。
恵子は寝室に行って、化粧台の前に座ってみた。大きな鏡には背後にある大きなダブルベッドが映っていた。2年前、愛人だった滝川が自殺してから、恵子はこのベッドに誰も入れていない。恋人もボーイフレンドもつくっていなかった。ところが最近、妙に人が恋しいと思うようになっている自分に恵子は気が付いていた。
恵子は鏡を見ながら、髪にブラシを入れた。「〔らんぶる〕に野中さんは来ているだろうか?」ふとそう思いながら、口紅を塗った。しかし塗ってはみたものの、今の気分としては濃すぎて気に入らない。恵子は紅い口紅を落として、薄いピンクの色に塗り替えながら、初めて野中とお茶を飲んだとき、普通そうに見える野中が何かをもっているような気がしたことをぼんやりと思い出していた。
ピンクの唇が形になったとき恵子は、「やっぱり、〔らんぶる〕に行ってみよう。」と思った。恵子は黒い下着を白に取替えた。ブラジャーを外したとき、乳房の張りをじっと見詰めた。
恵子は立って、隣のステレオのある部屋に戻り、受話器を取って管理人にタクシーを呼ぶよう頼んだ。それから衣装室に行って、鏡を見ながら幾つかのスカートを腰に当て、最後に目も覚めるようなブルー色の前ボタン・スカートを穿いた。
それから寝室に置いてある宝石箱を開けた。恵子は着物で仕事をするから、ほとんどネックレスは付けないが、宝石箱の中にはプレゼントでもらった指輪やネックレスがたくさん入っていた。その中からシルバーの腕時計と合う、一番細いネックレスを首に飾って、また鏡を見た。そして上げていた長い髪を下ろして、左肩の前に持ってきた。この間も、ペギー・リーは歌い続けていた。何曲か歌い終わったころ、管理人室から車が来たことを告げる電話があったので、ステレオを消し、透明のように薄いストッキングを白い脚に通した。
恵子はハンドバッグを持って、ブルーのハイヒールを穿いた。
「毎度ありがとうございます。」エレベーターで下りると、運転手が女王でも迎えるように深々と頭を下げ、ドアを開けてくれた。時々迎えに来る運転手の顔だった。運転手は走って運転席に座り、「どちらまで参りましょう」と言った。
「近くて悪いけど、銀座の〔らんぶる〕の手前で停めてください。」
「はい。」車はスタートした。
「今日は天気が良くて・・・」と運転手が話しかけてくる。
「急いでくれます。」恵子は美しい眉をひそめながら、バッグからサングラスを取り出した。約束があるわけでもないのに、急いで〔らんぶる〕に行きたかった。恵子の気持がそうさせるのである。
運転手は、まずかったかなというよう顔で「はい」と低くしっかり返事をした。
車に乗ったとたん、久しぶりに恵子は死んだ滝川のことを思い出していた。本気で愛していたというのに、皮肉にも彼の死後はひどく苦しめられた。
滝川は映画監督だった。幾つかの作品が幾つかの映画賞候補にノミネートされたが、20年の映画監督人生で、とうとう一つも入賞にはいたらなかった。それまで「映画の虫」を自認していた彼は自分の能力の限界に悩み、ついに北海道行きの客船から海に飛び込み自殺した。
彼には妻子がいた。遺書はその妻子宛と映画の仲間宛と、恵子宛の三通があった。そのため恵子も警察に呼ばれた。遺書には「恵子、死んでも愛している」というようなことが書いてあった。
むろん取り調べではなかったが、刑事たちからはまるで心中の生き残りのような目で見られた。いま思い出しても、あんな屈辱的なことはこれまでの人生ではなかったことであった。ただ、配慮だったのか、たまたまの日程だったのか、警察へ行ったのが、滝川の家族と別の日だったことが、せめての救いだと思っていた。が、後日とんでもないことになった。
事件は、最初新聞に比較的小さめの記事が出た。ところが、恵子宛の遺書のコピーがどういうわけかフリーのジャーナリストの手に渡り、それが滝川の妻のもとへともたらされた。妻は激怒して「夫は夜の女に殺された」と週刊誌にぶっつけた。それから嵐が吹き荒れた。
映画監督と銀座の美人ママ・・・、マスコミの恰好の餌食だった。テレビでは、「美しすぎる恵子ママの本当の貌!」などと報道され、週刊誌、スポーツ新聞には見たくもないような下品な見出しが躍り、世間からは「悪女」「魔女」のレッテルを貼られた。
恵子は、二人のことは、普通の男女の関係だと思っていたが、このときほど自分が水商売の女だということを思い知らされたことはなかった。
マスコミはマンションの前、クラブの前に押し掛けた。毎日が針の蓆だった。恵子は唇を噛締め、一人で泣いて耐えていた。
運転手が声をかけた。「お客様、どの辺りでお停めしましょうか?」
「えっ? あ、そうね。ここで下りるわ。」恵子は目が覚めたように驚いて、車を下り、松坂屋デパートの洗面所に入った。化粧を直そうと思ったのであるが、それ以上にできるだけ明るい顔に戻そうと思った。
外に出た恵子は、歩きながら自分自身に何かを祈り、サングラスを外して〔らんぶる〕のドアを開けた。
何人かが一斉に恵子を見た。恵子はこうした視線に慣れていた。
恵子の眼は一番最初に野中の姿を捕まえた。「いた!やはり、」恵子は嬉しかった。この奇跡の偶然が、かつて恵子の株の師匠・三木茂吉が「女相場師になれる」と呆れながら称えた、恵子の直感だった。
「そこ、構いませんか?」
「はい。」野中は恵子を迎えるようにして立ちあがった。
恵子は野中を見て、艶然と微笑んだ。
野中は眩しそうに恵子を見入った。「今日も買い物ですか?」
「ううん、今日は他の用事なの。驚いた?」
「はい。びっくりはしたけど、ぼくは人と偶然に会うことがよくあるんですよ。」
「え~!」
「珈琲、頼みますか?」
「そうね、お願い。今日も『ブラック・コーヒー』がかかってるわね。ジュリー・ロンドン?」
「そうですね。ママと雰囲気が似てますよ。」
「え~、嬉しいわ。」
「前から思ってましたけど、ママは英語の発音が上手いですね。」
「そうかしら。若いころ、英会話を習ったことがあるからかしら。それからジャズ・ヴォーカルを聞くようになったの。ネ、野中さん。ちょっとお願いがあるの、」
「えっ?」
「昼間は『ママ』って呼ぶのは止めてくれません、」
「それは失礼しました。でも・・・、」
「恵子でいいわよ。」
「本名なんですか?」
「そうよ。美薗恵子よ。」
「きれいな名前ですね。あの・・・、さっき『昼間は』っておっしゃったけど、実はキリスト大の担当が変わったんですよ。ですから、山田先生とお店に伺う機会が少なくなるかもしれません。」
恵子はおみくじを開けてみたら、「凶」の字が飛び込んできたときのような感覚に縛られた。
「・・・・・・。」
「すみません。」
「そう。」恵子は少し困った。そういうことじゃないのよ。恵子は言いたかった。
珈琲がきたので恵子は一口だけ飲んで、「ねえ。お昼は済んだの?」
「いえ。」
「何か、食べに行かない? 直ぐ近くに美味しいお鮨屋さんがあるの。」
「は、でも。」
「行きましょうよ。」恵子は伝票を取って、立ち上がった。足を運びながら、ハンドバッグの口を開け、財布をとって伝票とお金をレジに置き、お釣りを取らず外に出た。これまでの恵子は、男を食事に自分から誘ったことは一度もない。初めてのことだった。しかし、男と女の駆引は知っていた。
誠意ある野中さんは、ぜったいこのままサヨナラはしないはず。歩く背中で野中の気配を感知していた。一緒に来てくれている。だけど今は彼と話さない方がいい。口を開けば、行けない理由を言われないともかぎらない。彼を店の中に入れるまでは・・・。
まるでハンターだった。彼女をここまで急がせたのは、「お店に伺う機会が少なくなる」という野中の言葉によって、縁が切れることを恐れたからだった。というよりか、「野中と離れてはいけない」という心の声が聞こえたのである。
恵子は通りを渡って、細い路地に入った。駕籠看板は出ているから休みではない。ここの大将は気分で店を休むことが、たまにある。よかった。恵子は〔鮨 小竹〕の暖簾の前で野中に微笑み、「ここよ」と戸を開けた。
間髪、「らっしゃいッ!」主人の声が飛んでくる。
その声に合わせ、恵子は手の指先で野中の背をそっと押した。
狭い店だ。二つしかないテーブルには先客がいた。カウンター席の方は半分ほど空いている。
店の女将が「恵子ちゃん、奥でいい?」と言いながら、案内してくれる。
恵子は一瞬のうちに、自分の店のお客さんが来ていないかを確認した。いない。ほっとした。でも、右のカウンターに座っている人は、恵子の店のお客ではないが、この鮨屋の常連だ。食通の作家として知られている大口仁志。恵子も軽く言葉を交わしたことがある。恵子は目を合わせないまま会釈して、「今日は声を掛けるような野暮なことはしないで」と思いながら、座った。
「ご注文は?」女将が訊く。
野中は若いからビールがいいかとも思ったが、食通の大口の目が「ビール飲んで、腹いっぱいになって鮨か!」とうるさいことを言いだしかねない。
「お銚子一つ」と注文しながら、「いい?」と野中に目で尋ねた。
「あいよ。人肌一本。」
「江戸前はぬる燗なんて言わねえ、人肌って言うんだ」とは、ここの大将が教えてくれたことである。
恵子は野中にぐんと身体を寄せて「ごめんなさいね。無理に誘ったみたいで」と低い声でいいながら、杯に酒を注いだ。
このとき恵子は、そういう自分を「ああ」と嘆きたくなった。わざと低い声を出しながら男に寄り添い、酒を注ぐのは親密さを演出するためのホステスの常套手段だった。「でも、それは偽りの恋人。今日は本物の恋人のつもりよ」と思いたかった。
野中は「いいえ。お鮨と聞くと断れなくて。でも、お酒は仕事中だから」と言って、恵子の杯に酒を注いでくれた。
恵子と野中は杯を合わせた。
恵子は「何か摘まみましょうよ」と続けて、野中の小皿に紫を少し点してやった。「江戸っ子は、鮨、蕎麦に汁をたっぷり付けねえ」これも大将から教わった。
野中も醤油差しを恵子から取って少し点してくれた。野中も営業マンだ、江戸前鮨の食べ方を知っているようだった。
このとき大口仁志が立った。「大将、ご馳走さま。今日も最高だった。」
「へい、毎度、ありがとうございます。」
それが合図になったかのようにして、他の客も帰り支度をする。
恵子からすれば、「やっと帰ってくれた」という感じである。恵子は伸び伸びとなった。
恵子はまた野中の杯に酒を注いだ。野中が口に運び、杯を置いた。
野中もまた恵子の杯に酒を注いだ。恵子は口に運び、その杯を野中の杯にピッタリとくっつけて置いた。恵子の白磁の杯には恵子の口紅が付いている。
「ふふ。この二人、仲いいでしょ。」恵子は杯を指しながら、悪戯っぽい目で野中にそう言った。
恵子は今の気持を何か悪戯でもして、言い表したかったのである。
野中は照れながら、「それにしてもマ、」と言おうとした。
恵子は甘えるようにして指で彼の唇を押さえた。「ママじゃないでしょ」と言いたいのである。
野中は言い直す。「それにしても恵子さんは、脚が速い。まいりましたよ。」
「そうお。ネ、何がいい?」と知らんふりをしながら、恵子の身体はもう野中の身体に接したままである。
野中は白身を握ってもらった。鯛、饎の昆布〆、平目の昆布〆・・・。
「お客さんは九州のお人ですか?」
「当たりです。鯛や白身が好きそうだから?」
「へい。九州のお人は鯛が好きですね。」
「え? そうなの。知らなかったわ。」
「いいんですよ。鮨さえ、食ってもらえれば、」
続いて、鮍、蛤、鳥貝、貝柱。
恵子がまた野中の顔すれすれに口を寄せて言う。「穴子のキジ焼、食べる?」
野中は肯く。
大将は二人の真正面ではなく、少し離れた板前に立って握ってくれていた。そして恵子を珍しいものでも見るような目で、女将に「おい、今日の恵子ちゃんは変だぜ、」と目で訴えていた。
女将も、今日の恵子がいつもと違うことを察知していた。というよりか「恵子ちゃんは本気だよ」と大将に目で答える。
穴子が来た。
恵子は「熱いうちに食べてね。」と言いながら、七味を振掛けてやる。
「美味しいでしょ。」恵子は野中の顔をすれすれに唇を寄せて言う。
大将が女将に向かって笑いながら、手拭で出てない汗を拭く真似をする。
「もう、お腹一杯だよ。恵子さん食べました?」
「食べたわよ。」
上がりを飲みながら、野中は考えていた。「こんなことになってしまっていいのかな。他のお客さんを連れて、〔クラブ恵子〕に行って上げなければならないかな。それにしてもママは一回も店に来てとは言わない。不思議な人だな。」
野中は山田教授が言ったオトコの自殺について、週刊誌に載っていたことをとうに想い出していた。あのころは銀座のクラブに通うことになろうとは思っていなかったから、事件について関心はなかった。だから、詳しくは知らない。でも、野中自身も20歳のころ、このまま死んでもかまわないというような失敗をしていたから、自殺について山田ほどに忌まわしくは思っていなかった。ただ、恵子の色気に怖さを感じるところはあった。
恵子は場所を変えようと思って、「もういい?」と訊いた。
野中は頷いて、椅子から立って、胸の財布を取ろうとする。
恵子はその手を押さえながら言う。「野中さん。いいわよ、ここは。」
「でも、いつも申し訳ないですよ。」
「いいのよ。私の方が少しだけお姉さんなんだから、」と、今日の強引さの言訳をするように「お姉さん」と言ってみた。
「いいねエ。あたしも言ってみたいね。お姉さんなんだから、払うよって、」
「ケッ。おメエみたいなハバアが言やあ、オトコが逃げちまうよ。オメエはこのオレでちょうどいいんだよっ。ネ、恵子ちゃん。」
「ふふふ」
野中も苦笑いしながら、先に外に出た。
それを見て、鮨屋の女将が言った。「恵子ちゃん。元気になってよかったね。良さそうな人じゃないか。」
「そんなあ、まだ何でないですよ。」
「あたしゃ、嬉しいよ。男はね、普通で、真面目が一番。」
「お母さん、ありがとう。」
女将はカウンターに行って杯を持ってきて洗ってから、「これも持って行きな」とそっと渡した。
「エッ!」
「アタシだって昔は乙女だったからね。よく気持は分かるよ。」
「ありがとうございます。大事にします。」
恵子はすっかりしおらしくなって、頭を深く下げた。
「いいよ。明子とちがって、あたしゃ何にもできなかったけどね、応援してるよ。」
明子 ― その名が出ると恵子の眼からは涙が溢れ出た。
「あらら・・・、どうしよう。恵子ちゃん、」
女将は、きっと今日の恵子は神経が昂ぶっていたんだろうと思いながら、優しく背中を摩った。が、そのとたん、堪え切れず恵子がカウンターに泣き崩れた。「ううううう・・・、」
「あらら・・・、どうしよう。恵子ちゃんごめんねえ。」
「バカ、おメエは余計なことを言ってよ。オレは、あのお客さんを呼んでくるから、オメエは恵子ちゃんのホレ化粧を、」
「あいよ。」
店主は野中を呼んだ。「お客さん。」
「はい。」
「すみません。うちのバカが、恵子ちゃんの、亡くなったばかりの母親代わりの人の話を持ち出したもんで、泣き出しちゃったんですよ。」
「・・・!」
「できれば、そのう。恵子ちゃんは、お客さんを信頼しているようですから、車で連れて帰ってくれませんかね。すみませんねえ。」
「もちろん、いいですよ。車を駐車場に入れていますから、すぐ取って来ます。」野中は駐車場へ走って、路地の外の通りへ持って来た。
女将と大将が、恵子を連れて来た。恵子はサングラスで両目を隠している。
野中は心底驚いた。あの凛とした美人の恵子ママが悄然として助手席に座るのである。
大将が二人を見送りながら言った。「雨降って地固まればいいな。」
「あんたにしちゃ、機転が利いていたね。彼に送らせるなんて、さ。」
「しかし、あの人は普通のサラリーマンだろ。恵子ちゃんも変わったな、野球選手とか、歌舞伎俳優じゃなくて、さ。もう、映画監督なんてクソ喰らえだな」
「あんた。もう、それは言うじゃないよ。」
「そうか。でもよ、泣き出すなんて、こんなこと初めてだな。驚いたよ。」
「よっぽど溜まっていたんだよ。あの事件、明子ママの死、続いて母親も心労で亡くなっちゃったんだから。恵子ちゃんは今、必死で立上がろうとしているんだよ。こういうときはあの彼みたいに普通の男の支えがいるんだよ。」
野中は恵子のマンションへ送るつもりで場所を尋ねたが、恵子は「帰りたくない」と言う。仕方なく、野中は当てもなく晴海まで車を転がして、埠頭で停めていた。
すでに、野中の恵子に対する疑念は、さっきの涙で一掃されていた。それよりむしろ恵子のことを無償に可愛い女だと思うようになっていた。
しかし恵子は口を閉じたままだった。
車のフロント・ガラスの右側を見ると、自動販売器があった。恵子の気分でも変わればと思って野中はドアを開け、ポケットから小銭を出した。見ると一本分の金しかない。まあ、いいかと思って近ごろ売出したばかりの〔ポカリスエット〕のボタンを一回押した。ガタンといってそれは落ちてきた。
恵子は、鏡で自分の顔を見た。二人だけのときはサングラスは外したい。だけどみっともない顔は見せたくない。鏡を見て、大丈夫そうだと思った恵子は、サングラスを外した。
「飲む?」野中は栓を開け、恵子に渡した。
「ありがと。」恵子は、聞こえるか、聞こえないかのような低い声で言って、口を付けた。そして恵子は縁に付いた口紅を指で拭き取って、それを野中に渡し、野中をじっと見つめた。「貴方も飲んで」と言ってるのだろうか。
野中は受け取って、二口飲んで、また恵子に渡した。恵子は嬉しくなって、またそれを飲んだ。恵子の心は安らかになった。ふと恵子は、子供のころに何もしゃべらないで父と母が座っていた姿を懐かしく想い浮かべていた。高校の美術の教師だった父は恵子が大学に入ってすぐに病死した。母は秋田で一人暮らしを続けていたが、2年前に亡くなった。「お母さん、ゴメンネ」と心の中で謝ったとき、野中が煙草を取り出した。恵子は急いで、ライターを探して火を点けてやった。それから恵子は意味もなくカーラジオのボタンを押してみた。音は低くして、手持ち無沙汰に次々とボタンを押した。野中は黙って、恵子の悪戯を許していた。
恵子はまたポカリを取って一口飲み、野中に渡した。目には安らかな微笑みがあった。
野中も微笑みながら一口飲んで、恵子に戻すと、恵子はごくんごくんと全部飲み込んだ。恵子は、少女のような気持になっていた。これが「デート」というものだろうと思った。恵子には初めての経験だった。
恵子はまたカーラジオのボタンを押した。低い声で何か聞こえる。恵子は少しボリュームを高くしてみた。
「神様は、人間のどんな死でも許してくれます。どんな死に方をしても許してくれます。」NHKの宗教の時間のようだった。
それを聞いた恵子がまた微かな嗚咽を始めた。
野中は慌てた。そして車の座席に座ったまま身体をよじって、恵子の頭を包むようにして抱いてやった。
どのくらいの時が経っただろう、抱かれていた恵子は顔を起して、野中をじっと見つめた。髪が乱れている。野中は恵子の髪を撫でてやりながら、顔を近づけてきた。恵子は瞼を閉じて待った。そして野中の唇を受け入れた。
野中は〔生粉打ち亭〕に来ていた。
何となく銀座界隈から離れづらい気持があったが、そもそもが山本部長のことで嬉しくなって、〔らんぶる〕珈琲を飲み、その後にそのきっかけの一つであった〔生粉打ち亭〕の蕎麦でも食べに行こうと思っていたのであった。
「何にしますか?」店員がお品書きを持ってきた。
江戸蕎麦、会津蕎麦、津軽蕎麦などの字が並んでいるがよく分からない。それに今の野中には思考能力が全くなかった。野中は、とりあえず一番最初に書いてあった江戸蕎麦を頼んだ。
今日の恵子とのことは、野中にとっては予想もしてなかった。あまりにも急な展開に気持の整理がついていなかった。手も届かない女性だと思っていた恵子とこんなことになるなんて、今でも夢ではなかったかと思うほどである。
蕎麦がきた。野中は割箸をそっと割って、麺を啜った。野中は少年のころから、ソーメンやうどんやラーメンを食べるのが速かった。だから、食べ慣れていないとはいえ蕎麦もアッという間に啜り終わった。
店主の菊地が蕎麦湯を持って挨拶にきた。「毎度。野中さんでしたね、遠藤先生とお見えになった。」
「ええ。」
「お蕎麦の食べ方、なかなかカッコいいね。」
「え、いや。」
菊地は、野中の蕎麦猪口に蕎麦湯を注いでくれた。
野中は礼を言って、それを飲んだ。旨いと思った。そして「あ~、蕎麦湯ってこうやって飲むのか」と初めて知った。
「また、遠藤先生とお越しください。」店主は新しい客が来たので、そう言って厨房に引っ込んだ。
野中は、店を出た。外から見上げると、クリニックの看板が見えた。野中は近々のうちに遠藤先生を訪ねて、また一緒に蕎麦を食べよう。その前に山本部長にレポートを再提出しよう。そんなフォローを予定した。
しかし・・・・・・、そんな野中も、恵子のことになると、これからのことが全く読めないでいた。
野中の身体には、いま別れたばかりの恵子の、柔らかい身体の感触と、甘い匂いが残っていた。野中はもう抑えられないと思った。恵子が忘れられない女になっていく自分自身を・・・・・・。
(Ⅴへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕