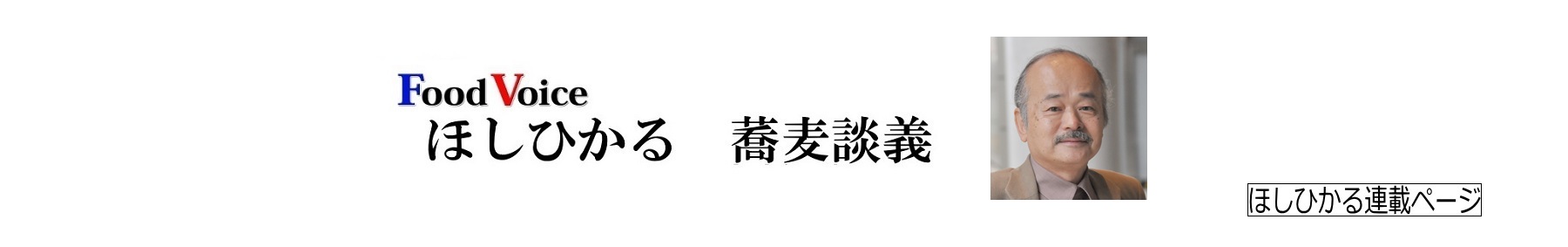第351話 小説「コーヒー・ブルース- 最終章」
2025/12/06
~ There You'll Be (Sarai Oui) ♪ ~
健は掲示されてあるものを読んだ。英語は喋れないが文章はだいたい分かる。
1. 患者は、思いやりのある[人格を]尊重したケアを受ける権利がある。
2. 患者は、自分の診断・治療・予後について完全な新しい情報を、自分に十
分理解できる言葉で伝えられる権利がある。
3. 患者は、何かの処置や治療を始めるまえに、インフォームド・コンセントを与えるのに必要な情報を医者から受け取る権利がある。
4. 患者は、自分のケアに関係するすべての通信や記録が守秘されることを期
待する権利がある
5. 患者は、病院がそれをすることが不可能でないかぎり、患者のサービス要求に正しく応えることを期待する権利がある。
「患者の権利! これだ!」健は声に出して叫びそうになった。いわば、医療情報は医療機関のものではない。患者のものと書かれているのである。
ここが日本なら、公衆電話へ走って、古賀に電話するところであった。
「どうしたの?」健と腕を組んでいた恵子が健の顔を覗き込んだ。
「探していた答が、ここにあったんだよ。」嬉しくなった健は、恵子の身体を抱き締めた。
「ふふふ。あなたって、目に入るのは何でも参考にしちゃうのね。でも、よかったわ♪」恵子も一緒になって嬉しくなり、健の頬に軽くキッスをした。
診察室には恵子が先に入った。
暫くしてから、健が呼ばれた。デスクで、担当の女医が待っていた。日本人ではなかったが、中国人か、韓国人の血が入っているような顔付の、いかにも利発そうな女医だった。名札を見ると、〔M. Lee〕とある。
恵子が「日本から主人が来てくれました」と英語で伝えた。
ドクター・リーは立ち上がって、笑顔で健と握手を交わし、片言の日本語で「ミスター・ミソノ、ケイコさんは順調です。安心してください」と言って、その後は英語で何事か喋って、「何か、質問はありますか?」と最後にまた日本語で言った。
健は戸惑ったが、「出産日は予定通りですか?」と訊いた。
「イエス、予定のままです。産後は少し注意します。アメリカ人は出産後、その日に帰ります。でも、日本人の女性は骨盤が小さいですから、安全をとります。」途中、また何か英語で言って、「私もそうですから、産後は4日間、休みました、ケイコさんも同じくらい休めば、オーケーです。心配ありません。」とニッコリ笑った。
健は (はあ、そうなのか。東洋人と西洋人はそんなに、) と感心しながら、聞いていた。
診察室を出ると、恵子が「ごめんなさいね」とペコリと頭を下げた。
「何が?」
「ミスター・ミソノって言われたでしょう。」恵子は、健に〔きゃらばん〕へ連れて行かれたとき「奥さま」と呼ばれて、くすぐったい感じがしたことを思い出していた。
「別に構わないさ。恵子は妊婦だし、人様から見ればどう見ても夫婦だよ。ま、座ろうよ。」
「うん。」
二人は手続の番がくるまで、椅子に掛けて待った。
健は続ける。「だから、式を挙げなきゃ。」
「あの、」
「ん?」
「ご両親にはおっしゃったの?」
「まだだよ。びっくりして、こっちへ飛んで来るので精一杯。」
「そうよね。ごめんなさい。」
「親の方は大丈夫だよ。」と健は胸にかかえていることと、反対のことを言った。実のところ (子供ができた・・・、年上・・・。そんなことを下手に母に言おうものなら、「お前は騙されている」なんて言い出しかねない。母親から見れば、可愛い息子をたぶらかした女に見えるかもしれない。しかし実際は逆だ。何せ、一人で産む決心をした、優しいけど、強い女。それにおれにとっては可愛いい女、もったいないくらいに。でも、世間の常識の塊みたいなガチガチの母親に、分かってもらえるだろうか?) と考えあぐねていたのである。
「ご両親に気に入っていただけるかしら?」
「親父と弟は美人の恵子を見れば、直ぐウンと言うだろう。母は孫の顔を見れば納得するだろうよ。心配ないよ。」健はわざとケロリとした顔で言う。
「そうお。」
「今は、元気な児を生むことだけに集中。」
「はい。」
健は、恵子のお腹を軽く擦りながら、「昨夜、丸くなった素肌のお腹を触ってみて、感動したよ。このおれに赤ん坊か、ってね。」
「まあ! それまではどう思ったの?」
「う~ん、桃子姐さんから聞いたときは、どう思っていいか分からなかった。でも、恵子の肌の感触と体温で、より実感がもてたのさ。やっぱり来てよかった。」
「ありがとう。あなたが来てくれて、百人力よ。」
「おれは何もできないよ、」
「そんなことないわ、ほんとよ。ところで、あなた。煙草は止めたの?」
「ンンン・・・。気付いた!」
「うん。こちらに来てから、一度も吸ってないから、」
「禁煙中、というところかな。」
「この児のため?」
「そりゃそうさ。」
「えらいわ。フフフ。」
「何?」
「このお腹だから、昨日は踊れなかったでしょう。」
「親子三人で踊ったんだよ。」
「まあ♪ この児が大きくなったら言ってあげるわ。あなたとパパとママの三人で踊ったのよっ、て。ふふふ」恵子は健の身体に寄り添って、健の唇を心配そうに見詰める。「まだ切れてるわ。痛い?」
「食べるときにチョットだけ、」
「ごめんなさい。」
「記念だ。恵子の可愛いさの。な、ベイビー!」健は恵子のお腹に向かって、笑いながら言った。
翌日は、エリザベス夫婦が自宅に、恵子と健を招いてくれた。子供たちはキャンプ中で留守らしい。エリザベスは夫のクリスと共に、恵子のアパートメントに車で迎えに来てくれた。
健が驚いたのは、自宅に到着するやクリスがマメマメしくキッチンやリビングを往復して働くことであった。彼は、健のために分厚いステーキを焼き、恵子のためにスープ、野菜サラダ、サケのマリネなどを作ってくれた。
リビングのエリザベスといえば、女王のように椅子に座って、恵子や健の相手をしている。
しかも健の目には、二人が日常的なごく自然な姿に映ったから、そこがまた何とも不思議だった。感心しながら、健はエリザベスのワイングラスに白ワインを注いだ。
エリザベスはニッコリと微笑みながら会釈して、「ケイコ。わたしはね、東京にお店を出したいと思っているの、」
「いいわね。」恵子は喜んだ。
エリザベスは一度健の顔を見てから、恵子に「ケイコさえよかったら、その東京のお店を貴女に任せたいの。」
「エッ!」
「・・・・・・。」健も驚いた。
「サンキュー、エリザベス。でも、今の恵子はこの児を産むことだけしか考えていないのよ。」
「ほほほ。そう、今すぐという話じゃないの、計画なの。」エリザベスは笑った。
クリスがコーヒーを運んできて、言った。「東京に店を出す。エリザベス、素晴らしいプランだよ。ケン、ファッションは、平和で、重要なビジネスだ。東京にとっても、ニューヨークにとっても。」
「え?」
「ニューヨークは、世界の都市へ通じている。これから東京も、もっとニューヨークと仲良くなった方がいい。ファションで世界の都市がネットワークを結めば、それが平和の道にもつながる。」
健は、恵子が書いて寄こした手紙に、何とかというファッション専門のジャーナリストが、「ファション産業は平和産業だ」と言っていたということが書いてあったことを思い出した。ファションが平和産業なんていうことは、考えもしなかったことである。これが小田社長の言う「これからは美と健康がビジネスになる」ということなのかと思った。
帰りは、またクリスがアパートメントまで送ってくれた。
部屋に戻ると、恵子はベッドに横になった。
「疲れたのかい。」
「ううん、そうじゃないわ。あなたもここに来て横になって、お願い♪」
健は乞われるまま並んで寝転がった。
とたんに恵子は顔を健に近付け「もうあなたと離れたくない。」と甘い吐息を漂わせながら言って、顔を健の胸に埋めた。
恵子は、健が今ここにいることに幸せを感じていた。
先ほどエリザベスが「あなたに東京の店を任せる」と言ったとき、明子ママのことを思い出していた。20代の若いころ、明子ママに同じようなことを言われた。それから恵子は明子の特訓を受け、ママになった。ある意味、私は明子ママの作品だったかもしれない。でも、面白かった。その上に三木茂吉も紹介してもらって、一財産を作ることができた。これも面白かった。そのころの恵子は漠然とだったが、このまま一人で生きていくものと思っていた。それから、あの事件が起きた。
しかし、その事件も風船が萎むようにいつのまにか落ち着いた。そこへ健が現れた。恵子は健を自分から求めた。銀座一の美人ママといわれていた恵子が、そんな行動をとったのは初めてであった。二人は愛し合うようになった。それから恵子は健とNYで待ち合わせた。恵子は分かっていながらも裸で健を愛した。そして妊娠した。不安をかかえながらも恵子は一人で産む決心をし、NYにやって来た。ところが、このNYで恵子は新たな自信をもつようになった。『他人の行く裏道に花あり』。そう教えてくれたのは亡き三木茂吉だった。一人ぼっちのニューヨークは泣きたいほど寂しかった。でも、その寂しさと苦しさが自信という花をもたらしてくれた。お蔭でプロポーズも自分からするつもりにまでなった。しかし結果的には桃子姐さんのお蔭で、健がそれをやってくれた。
恵子は、銀座のママのころの自分は仮の姿で、健を愛している今が本当の自分だと思うようになった。今の恵子は、父にしたがって生きてきた母の気持がよく理解できた。
「大丈夫かい、うつ伏せになって。」心配した健は、恵子を寝かせて逆に覗きこんだ。
恵子は下から健を見つめながら、指で健の切れた唇を押さえ、「もう東京に帰らないで、このままいて!」と、まるで半年分の寂しさを取り戻すように甘えた声で言った。
健は「そうしたいな」と言って、微笑んだ。「この前の曲でもかけるかい?」健は起き上がって、レコードを回した。
二人は、目を閉じて黙って聞いていた。ヴァイオリンとペットのデュオが美しい。
恵子は、エリザベスとは尊敬する大事な友人として、これからも付き合っていこうと考えていたが、エリザベスのあの誘いは断るつもりでいた。
そして恵子は健の顔を見ながら、これからの人生は健と共に歩んで行くんだと心の中であらためて思った。
このとき健が言った。「な、恵子」
「はい。」
「式は、NYでやろうか?」
恵子は健の頬に唇を寄せ、「妻は夫に黙って従います」とはにかむようにして言って、「でも、ご両親は?」と心配した。
「二人、いや二人半でやろう。生まれてくる前に済ませてないと、この児がママ、パパと呼べないだろう。」
「まあ♪」
「だから、一旦日本に戻り、親や周りに披露宴は日本でやるけど、式はニューヨークで挙げる、と言ってくる。」
恵子は身体をゆっくり起こして、ベッドに両手を着いて頭を下げ、「不束な嫁でございますけど、どうか宜しくお願いします。」と言うや、にっこり笑って、健に抱きついた。
健は恵子の身体を抱いて、耳元で囁いた。「My One and Only Love ♪」
日本に戻った野中は忙しかった。先ずは、小田社長に報告した。山本先生にも会った。社長と山本医師は「アメリカに行って、よかったじゃないか」と同じことを言った。
野中は古賀を伴って木村病院へ行った。
途中、古賀は「アメリカから帰って来たら、すごい元気ですね。彼女の力は大きいなあ。」と笑っていた。
木村院長には、医療情報は患者のものという考えにしたがって、医師の動線の一つに説明行為を加えること、つまり患者への説明を医療の一つとする考え方を具体的に推進するにはどうしたらよいかを相談した。
院長は言った。「う~ん、そうだな。やっぱり、アメリカのように患者の権利章典みたいなことを病院の中央に掲げ、『当病院では、患者さんに納得のいく説明する』ということを医師やスタッフ全員が徹底させるのが一番だろう。」
帰社した野中は古賀と相談して【患者の権利宣言】をまとめることにした。
そして、後輩の佐藤や、経理の小林さんも、プロジェクトに加わってもらうための手続を取ろうと考えた。
そんなとき、小川先生から電話があった。
「立川に大学の後輩がいる。〔レオニス・ケア・システム〕を勧めてみたら興味をもったので、行ってくれ」ということだった。
野中は詳しい話を聞くために、先ず小川医師に会った。
小川医師の話はこういうことだった。「彼は大学の後輩だけど、同級生の息子でもあるんだ。前田というんだけど、大学生のとき、彼の父親が亡くなってね、この度やっとドクターになったので、無事父親の跡を継いで開業できたというわけなんだ。母親が電話してきてね、何とか一人前にしてくれと言うんだ。だから、これからの若い者は新しいやり方をやった方がいいと思ったので、君に行ってもらいたいんだ。」
会社に戻った野中は、社長に立川の前田医院のことを報告した。社長は野中の顔をじっと見詰めながら、聞いていた。そして「小川先生は、若い者は新しいやり方をやった方がいい。そう言ったのか!」と言った。
それから野中は岩崎を訪ねた。アメリカに研修に行っていたから、患者の権利章典のこと知っているにちがいないと思ったからであった。
岩崎さんは「患者の権利章典ね、確かにその線はいい。ハハハ」と高笑いして、あらためて賛同してくれた。
野中は、まとめようとしている【患者の権利宣言】のことを話してみた。
「【宣言】か、いいね。【章典】って硬いからね。野中さんは言葉のセンスがいいよ。感心するな。」
それから、立川の前田医院のことも話した。
「そりゃいいね。木下先生みたいに、常にトレンドを観ている人の考えも大事だけど、そういうホヤホヤのドクターのセンスも、このシステムの将来を占うためには必要だと思うよ。」
野中も、直感的にそう思ったから、岩崎に話してみたのである。そしておそらく「若い者は新しいやり方をやった方がいい。そう言ったのか!」と言ったときの小田社長の表情からも、同じ思いもったはずだと思った。
「野中さん、新しいやり方というのはね。〔レオネス・ケア・システム〕を使うに当たっての、考え方も入るよ。」
「え?」
「先ずは、院内のスタッフが情報を共有化しなければ始まらないという認識。それから、患者情報は患者情報のものだから、絶対情報を悪用しないという倫理感。これを医療機関に分かってもらうこと。」
「なるほど。」
「それから野中さん、医療機関の意識改革のためのいい方法があるよ。」岩崎は「ある経営セミナーで、学んだことだけど」と断りながら、あることを教えてくれた。
帰社した野中は前田医院に電話をしてシステムの概要を説明し、その翌日の木曜日に、古賀と一緒に車でシステムを運んだ。木曜日の診療は午前中のみで、午後休診だという。
前田院長と前院長夫人、それに看護婦3名が待っていた。
古賀は、パーソナルコンピューターをセットした。
医院のみんなは興味深かそうに古賀の動きを見守っている。
一段落着いたところで、野中が看護婦たちに質問した。「皆さま方のお給料は誰から頂いてますか?」
「え~! 院長先生から、」
「まあ、お金そのものはそうですけど、本当の意味ではお給料は患者さんから頂いているのですよ。」これが岩崎から「いい方法がある」と言って、教えてもらったことであった。
看護婦たちは自分たちが的外れの回答をしたことを照れていたが、その中で
一番大きく目を見開いて聞いていたのが、前院長夫人だった。
それに気付いた野中は腹の中で感心した。それから野中は「医療情報は患者さんものだから、きちんと分かりやすい形で、患者さんに渡して上げる。そのお手伝いをこの〔レオニス・ケア・システム〕がやってくれます。」と説明した。
後は、古賀がシステムの説明をし、明日からデーターの入力をするために通ってくることを話し、終了したのは夕方だった。
終わったとき、前院長夫人が「近くで食事を予約している」と言う。
行ってみると、ちょっとした料亭のような所だった。座敷に通され、野中と古賀は上座に座らされた。
「奥さま。こんな立派なところがあるんですね。」前院長夫人のことを看護婦たちは「奥さま」と呼んでいたので、野中もそう言った。
「とんでもございません。田舎の店ですが、どうか召し上がっていってください。あ、失礼いたしました。その前に今日は本当にありがとうございました。」
野中と古賀は恐縮しながら、慌てて頭を下げた。
「小川先生からお聞きになっていると思いますが、主人を早くに亡くしまして、やっと息子がインターンを終え、跡を継ぐことがきました。でもまだまだ一人前じゃございませんので、どうか今後とも宜しくお願いします。」
野中は、岩崎さんが「若い人のセンス」と言ったことを思い出し、前田院長の顔を観たが、システムに対する反応はまだよく分からなかった。それよりか母親の必死さの方がよく伝わってくる。
野中は、ニューヨークのGYN病院の実情や、病院の玄関に堂々と掲示してあった【A Patient's Bill of Rights】に衝撃をうけたことなどを話した。
ここでは母子ともに熱心に聞いてくれた。
野中と古賀が、前田医院のことをまた社長に報告したところ、社長は頷きながら言った。「医者、弁護士、会計士、教師、坊主、政治家、ほんとうは代金をちゃんともらっているくせに、大きな顔をしている。そんな商売の方法もあるということだ。このコンピューターも、それでいけ。ハハハ」と言って笑った。
野中は、社長はちゃんと見抜いていたのかと思った。
一段落した健は、恵子と生まれてくる児のことを報告するために、九州の実家に帰った。
父親は「そうか」と言ったが、母親は返事をしなかった。予想通りだった。弟によると、母は自分が気に入ったお嬢さんを探していたらしい。
健は「恵子と子供のことを大事に思っているので、許してほしい」と手を着いて頼み、東京に戻った。
一週間したら、母から手紙が来た。開封すると、久留米の水天宮の安産のお守が入っていた。
健はほっとしてすぐに母に御礼の電話を入れた。
そしてニューヨークの恵子にも電話して、「母が安産のお守を送ってくれた」と伝えてから、送ってやった。
恵子は嬉しそうな声で、「ご両親へお手紙を書きます」と約束してくれた。
それから野中たちは子会社設立に向けて準備を進めた。
社長は野中の顔を見る度に「石橋を叩いて何かあっても、なお渡る。それが事業だ」と発破をかける。
野中は総務部長の所に行って「会社名はやはり〔ケアネット〕にしようと思っています」と言った。
総務部長は「牧田常務がおっしゃっている〔メディカル・ネットワーク〕にしないのか」と「気持が分からない」というような顔をして言ったので、野中は「メディカルでは自分たちがやろうとしていることと違うのですよ。」と丁寧に説明した。
すると、部長はムスッとして「預かっておく」とだけ言って、その日は決定しなかった。「それから、知っていると思うけど、今度の総会で、小田社長は会長に、牧田常務が新社長になられる」と追い打ちをかけてきた。
野中は寝耳に水だった。しかしそれを顔に出さずに、黙って頷いた。
廊下に出た野中は、(そうか!) と考えた。恵子が「ご両親に手紙を書きます」と言っていたことを思い出し、関係者へのアプローチを怠ってはならないと思った。
牧田常務の社長昇格は知らなかったが、設立予定のケアネットの社長には工場長の大田取締役が兼務する予定だと聞いている。野中は本社では課長、そのていどの者を社長にするわけにはいかない。せいぜい野中は常務取締役、古賀は取締役だ、ということらしかった。
部屋に戻った野中は大田工場長に挨拶の電話を入れ、「社名は〔ケアネット〕あたりを考えている」と言って、理由を説明した。
大田工場長は「分かった。野中君に任せる」と言ってくれた。
受話器を置いた野中はほっとした。これで牧田常務も、新社長の大田さんを差し置いて、無理押しはできないだろう。
前に、ニュービジネスの勉強会に顔を出したときだった。ある講師が「日本人は優秀だから、マニュアルは通用しない、必要ない。しかしながら、イエスマンは多い。」と言っていた。そして、こうも言っていた。「もし将来、マニュアル人間とイエスマンばかりになったら、日本は潰れるだろう」と。
講師が言うには、マニュアル人間とイエスマンの社会は考えない人間ばかりになってしまうということらしい。
マニュアル社会というのは、野中には想像もできなかったが、しかしイエスマンというのはよく分かる。だいたい会議というものがそうである。だから会議に出ない小田社長の気持がよく分かった。
とはいっても、社長は会議の存在を否定はしていない。「それが世の中だ」と笑いながら言う。
(そういわれればそうだろう。仮に自分がそのような席に座っていたら、心ならずも『イエス』と言うときもあるだろう。あるいは『メディカル』か『ケア』かと意見を求められたら、自分に関係ない場合は、牧田常務の言に従うだろう。あの席では常務が横綱で自分は十両だ。)
(世の中というのは理不尽そのものだ。だから、会議でも知恵を使って乗り切れ)と、小田社長は常々言っている。
岩崎から電話があった。「『医療とコンピューター』という雑誌の記者が来たので、〔レオニス・ケア・システム〕のことをチラッと話したら、『医療界の黒船じゃないですか!』なんて、面白いことを言ったよ。いま取材を受ければ、再来月発行の月刊誌に載るらしいけど、どうですか?」
子会社設立も再来月。タイミングがいい。野中は飛んで行って、岩崎に頼んだ。「その雑誌記者に、木村病院と前田医院を取材するよう持ちかけてください。取材テーマは〔情報医療〕」。
「いいね、いいね。データーの活用ということが、日本は実にプアーだからね。」と岩崎も手を打って喜んでいる。
「で、具体例として、木村病院はこれからの新しい医療に種々取り組んでいる中堅の病院として。前田医院は新規開業の医院として。いずれもコンピューターを使った〔情報医療〕に取組んでいる。その理念は〔患者の権利宣言〕。」
「そうくると思っていましたよ。」
野中はさらに付け加えた。「またニューヨークへ行きますから、GYN病院の【A Patient's Bill of Rights】の写真を撮ってきますよ。」
「うんうん。それはいい。」
野中は帰社してから社長に報告した。
すると、社長は「子会社設立のときは、記者発表もする。そのときはただの会社設立発表だけではなく、これからの医療のイメージを話せ。何だったら、岩崎さんにコメントを付けてもらえ」と指示した。
「分かりました。」野中もいい企画だと思った。
野中は木下院長に電話して、取材の件を話した。
前田医院は、古賀がデーター入力に行ったときに、前田医師か奥様に直接話した方がいいだろうと思って、古賀にそのことを伝えた。
古賀は「了解です」と返事してから、「子会社誕生が待ち遠しいですよ。」と顔を紅潮させて言う。
野中は何でもやらなければならなかった。開発、営業、経理、広報、総務なんて立派に業務が確立しているわけではないから、何でも屋だった。
しかも不思議なことに多忙に追われているときにかぎって、相談事まで飛び込んでくる。
大学の先輩からの相談もその一つだった。「ちょっと一杯、付合ってくれ」と強引に連行された。
卓に着くや、「おれ、子会社に飛ばされるんだ。皆、反対するけど、ノナさん、どう思う?」と先輩の部長は切り出した。
なおも聞いていると、「おれは本社の取締役になりたかったのに、子会社へ行けと言われている。ただし社長にということになっているので、迷ってるんだ」と言う。
野中は、「飛ばされる」なんて表現するようじゃ、(止めたがいい) と言おうかと思ったが、(後輩の自分に相談しているのは、違う解答がほしいのかもしれない)と考え直し、「受けたら、いいじゃないですか。オトコなら一度は社長をやってみるべきだと思いますよ。」
「そうかね。」
「親会社の取締役といっても、所詮はサラリーマンですよ。でも小さくても社長は違います。面白いですよ。ただし、オーナー社長には及びませんけどね。」
「そうか。最近のノナさんのイキイキした顔を見て、聞いてみたくなったけど、そうか、」とますます真剣な顔をする。
野中は頷きながら、恵子のことを考えていた。「先日NYに行ったとき、女の恵子だって「子供を産んだ後、落着いたら、銀座でデザイン・スクールを設立したいと望むようになった」と言っていたが、(ましてやアンタは男じゃないか) と言いたいくらいだった。
そう言う恵子も応援しなければならない。イヤ、その前にやることがある。一日も早くNYに飛んで、恵子と式を挙げなければ・・・。一昨日、恵子に電話をしたところ、エリザベス夫婦が教会を世話してくれているという。
それを聞いて健は、(やっぱり、挙式はNYにしてよかった。クリスの話は壮大だったが、その前に恵子の将来のデザイン・スクール運営のためにもNYの人たちは大事な人たちだ。)と思った。
「ノナさん、ありがとうよ。」そう言って、部長は勢いよく立った。どうやら、先輩は受ける方に傾いたようである。
その夜、帰宅した健に弟から電話があった。「兄貴。オヤジとオフクロが代わりにアメリカへ行ってこい、って言ってるよ。行っていいか。」
「そりゃ。お前が来てくれりゃ、助かるよ。」
「じゃ、行くよ。それからな、オフクロが『兄貴のことだから、花嫁衣装や指輪なんかまだ考えてないだろうから』って、オレが金を預かっている。それも東京に持って行くよ。」
「・・・・・・、」
「それからな、ベビー服を送るからアメリカの住所を教えろだって。」
(参ったな)と健は思った。実際、指輪もドレスも、ヘビー服のこともまったく考えもしていなかった。
健は恵子に電話をした。弟が式に出てくれることや、指輪やドレスやベビー服のことを話した。
恵子は「ドレスはエリザベスがプレゼントしてくれることになっているのよ。だから心配しないで、」と言ってから、(指輪も、普段からあまりしない方だから)と遠慮するつもりでいた。
しかし、それを口にする前に健が言った。「オフクロが指輪代を出すって言うんだ。」
健の母からもらったというお守はまだ飛行中、恵子の元には届いていなかったが、健の母の気持はとうに恵子に届いていた。「お母さまは、恵子をお許しになったのね、」そう言ったとたん、恵子は自分の母のことも思い出し、目から大粒の涙が溢れ出てきた。
「許すも何も・・・、心配するなって言っただろう。」と言いながら、健は(あの堅物のオフクロが・・・)とほっとしていた。
しかし、恵子は薄々感じていた。これまで健は両親のことをほとんど話したことがなかった。逆にいえば、健は両親の気持を大事にしていたからであろう。恵子は嬉し涙をハンカチで押さえながら「指輪も、ベビー服も遠慮なく頂きます」と健に言った。
そんな恵子の声を聞いているうちに、健はたまらなく会いたくなってしまった。「ああ・・・、」
「どうしちゃったの?」
「早く会いたいな。」
「恵子も早く会いたい。」
二週間後、健は機中の人となった。
そして、恵子と健は、ニューヨークの教会で、弟やエリザベスたちに囲まれていた。
祭壇の前で神父が二人に尋ねた。「永遠に愛することを誓いますか?」
健と恵子は互の眼を見つめながら言った。「誓います。」
神父が頷きながら言った。「愛だけが永遠です。」
このとき恵子は確信していた。〔And Everywhere I Am There You'll Be〕(私の行く所 いつもあなたと一緒ね♪)
《END》
*長い間、ご愛読いただきましてありがとうございました。
たくさんの方からは多くの励ましやアイディアを頂きましたことを心より感謝申し上げます。
なお、この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕