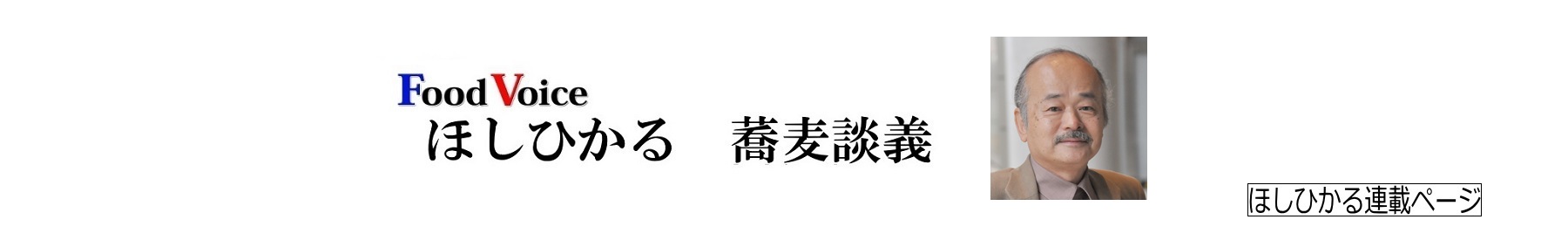第52話 「悠々とお茶を喫す」
2025/12/06
☆追悼茶会
七月の暑い朝、庭と玄関に水を撒いた。「露地」というしゃれた言葉があるように、水は露に濡れるていどに軽く撒いた。
今日は母が亡くなってから一ケ月余、裏千家の茶道を楽しんできた母のために、仲間の皆さんが追悼茶会を催してくれるという。 実家の、茶室(兼 応接間)の準備は皆さんにお任せし、私は母の部屋の床の間に大亀書の「一期一会」の軸を掛けてみた。その力強い一の字が人の一生を偲ぶにふさわしいと思ったからだ。
十時半、茶会が始まった。部屋に活けてあるルビー色のジュズサンゴが目をひいた。その小さな実は遠い異国からやってきたような魅惑的な赤だった。九十七歳になる老父と、私たち兄妹は茶室に座った。熾火の匂いが鼻先を掠めた。私たちは茶道の何たるかを知らない。それがこうした席に平然として座しているのだから、おそらく母は「なっていない」と笑っているだろう。
やがて白檀の香りが漂い、水色の番傘の絵のついた干菓子と蝸牛の形をした緑色の干菓子が回ってきた。一つずつ懐紙にとって口にする。それからお薄をゆっくり頂いた。一口飲んだあと、思わず心の中で「あ~」という声にならない声を吐いた。風呂の湯に肩までゆっくり浸かったときに、思わず「あ~」という声が漏れる、あの心境であった。
ゆっくりと、また一口お薄を味わった。お寺の鐘の音のような余韻が身体の中に広がった。美味しいお茶だと思いながら私は、庭の方に顔を向けた。狭い庭ではあるが、飛石、踏石、手水鉢、石燈籠があり、その間には名も知らぬ茶花が咲いていた。
☆「悠々とお茶を喫す」
「悠々とお茶を喫す」― そんな気分に浸っていたが、それはずっと前に読んだ遠藤周作のエッセイの題であることを思い出した。
話は、ウズベキスタン(胡国)の古代都市、サマルカンド近郊のある村のことらしかった。著者は、大きな樹の下に鳥籠をぶら下げて小鳥の声を楽しみながら茶を喫している老人を見たという。綿畠の向こうには青い山脈が拡がっている。白い雲も悠々と浮かんでいる。老人はその雲を見ながらゆっくりと茶を喫していたらしい。
それからの私は、シルクロードの中心都市であるサマルカンドの、大きな樹の下で悠々とお茶を喫すことに憧れていた。
考えてみると、お茶というものは不思議なものである。水やビールのようにカブガブと飲むものではない。ゆっくりと頂くものである。ゆっくり味わうと気持もゆっくりとなり、なぜか視線を遠くに移したりする。
遠藤は、そんな光景を目撃し、エッセイにしたのであろうが、そう考えはじめると、お茶以外の、たとえば食中にスープをスプーンで口にした後に遠くを見る、というようなことはあまりない。お茶だからありうる心理である、と感心する。
そのお茶と似たような気持になるものとして、われわれ蕎麦好きには蕎麦湯がある。蕎麦を食べた後に、あつい蕎麦湯を一口飲んだとき、「あ~」という至福の吐息を漏らし、思わず遠くを見たくなる。
しかし今日、実家に戻って母の霊前で、点てもらった抹茶をゆっくり頂いてみると、故郷で喫するお茶もまた格別だと思った。
このとき私は、久しぶりに故郷の夕焼けを見たいという気になった。子どものころ、家から数分の所にあるお堀の端に坐って、西の空を真っ赤に焦がしながらゆっくり沈んでゆく、大きな大きな太陽に見とれていたことを思い出したからであった。
【西方浄土の阿弥陀仏☆ほしひかる絵】
そういえば、遙かなる久遠の西方に〝浄土〟はあるという。それなら、お堀から見える、あの落日の彼方に亡き母がいるのではないかと、一服の茶を喫しながら想うのであった・・・・・・。
参考:栄西『喫茶養生記』(講談社学術文庫)、松本清張『小説日本芸譚』(新潮文庫)、岡倉天心『茶の本』(岩波書店)、熊倉功夫編『柳宗悦茶道論集』(岩波文庫)、肥前通仙亭(佐賀市松原4丁目)、遠藤周作「悠々とお茶を喫す」(『変わるものと変わらぬもの』文春文庫)、竹西寛子『日本の文学論』(講談社学術文庫)、折口信夫「山越し阿弥陀像の画因」(中公文庫)、中沢新一『イコノソフィア聖画十講』(河出書房新社)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員 ☆ ほしひかる〕