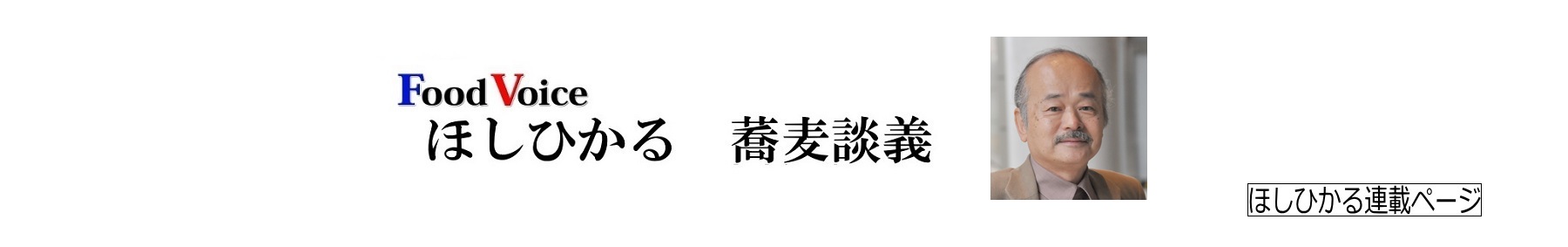第302話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅱ」
2025/12/06
~ Mr.Wonderful ♪ ~
カーステレオから、ライオネル・ハンプトンのヴァイブラフォーンの音が転がるように流れていた。
野中健は〔スカイライン〕のハンドルを軽く握りながら、自宅へと向かっていた。大村病院の接待ゴルフの帰りだった。
大村院長は千葉のゴルフ場から自分の〔ベンツ〕で帰ったので、陣内副院長と川口事務局長を野中が送った。ただ、事務局長は環七を越えた所で「ここからタクシーで帰ります」と言って下りたので、野中は副院長だけを練馬豊島園にある自宅まで送って行ったところであった。
野中はジャズを聞きながら、一人で車を運転しているこの時間が一番好きだった。
彼は5年前に営業所から病院部へ異動になった。世は田中首相がロッキード事件で逮捕され、列島中が煮えたぎった鍋を引っ繰り返したように大騒ぎしているころだった。そのとき野中は係長に昇進したが、ノルマが厳しい会社の割には年功序列的な人事だった。
後輩の佐藤たちから「ノナさん。病院部へいくと、ゴルフの機会が増えてお得意先の送り迎えをしなければならなくなりますよ」と言われ、思い切って〔スカイライン〕を購入した。
大学を出てからずっと営業だった野中にとって車は脚同然だった。だから運転は嫌いではなかった。そのころ、周りの若い者には〔スカイライン〕が人気だった。野中も迷わずそれを選んだ。
前の車のときは医者も卸のセールスも車種を無視しているか、「これ何?」ていどだったが、この車になってから、ちゃんと「〔スカイライン〕じゃないか」と言ってくれることに野中は満足していた。とはいっても、最近人気の外車とは比較にならなかったが。
異動して間もなく、後輩の佐藤と新宿のケロンパ・ママのスナックに遊びに行った。
野中は、昔から後輩を弟分のようにかわいがる傾向をもっていた。佐藤もその一人である。
「ノナさん。病院部はどうですか?」
「おれは地区担当の方が性に合ってるよ。」
製薬業界の営業は、一般的には地区の営業所の開業医担当より病院、とくに大病院や大学病院担当の方が格が上のように見られていた。
「数字に追われる毎日より、楽勝でしょう。」
「病院部はチーム制じゃないからな、いつも一人だ。何かモノ足りないよ。」
地区でのお得意先は、開業医の院長か、個人病院の院長であった。だから医師であり、経営者である彼らに自社の薬品を購入してもらうことが営業であったから、毎月の営業成績も明確であった。
加えて、こうした開業の医師らの趣味は多彩であった。車ならスーパーカーの〔ランボルギーニ〕や〔ミューラー〕や〔マセラティ〕とかが話題になった。野中も話題についてゆくのが精一杯であったが、耳にするうちにだんだん覚えてきた。ステレオとか、カメラとか、SLなどのメカに凝る医師もいた。いつかは鶴見線を走る「クモハ12型」の写真を早朝から撮りに行く医者に付合ったこともあった。テニス、ゴルフ、ヨットなどのスポーツタイプもいれば、麻雀、競馬、パチンコなどの賭事派もいた。だから「何でもあり」だというと遊び人と変わらないようだけれど、医者には理性が備わっているのか、それに溺れるような医師は一人もいなかった。「やはり趣味なんだ」と野中はつくづく思うのだった。それに、営業員としてこれらに付合えば、それなりの効果すなわち成績を得られることができた。だから、いま考えれば付合にも張合があった。
ところが、「大病院の医師はどうも様子が分からない。その営業はまるで大海を泳いでいるようで、今もって方向感覚が掴めないのさ。」
「そうは言っても、ノナさんは只では起きない人ですから、何かまたしでかしますよ。」
「しでかす、というのはひどいナ。」
野中は異動のころ、ちょうど足立区にある大村病院を開拓しようとしていた。いちおう規模形態としては個人病院であったから本来なら営業所管轄ではあるが、仕掛けたばかりのときの異動であったから、そのまま野中のテリトリーということになった。野中としては、いわば「張合のある」得意先になる可能性を感じていた。
野中は、先ず副院長の陣内に会った。初対面のとき見知らぬ人ではないような感じがしたので野中は尋ねた。「先生、ご出身は九州ですか?」
「おお、久留米だ。お前もか。」
「は、柳川です。」
「〔陣内〕という名前は福岡か、佐賀だとすぐ分かるな。〔野中〕も九州に多いな。」
「はい」
「ま、時々顔を出せよ。」
普通だったら、これからじっくりと営業が始まるだろうが、夜討、朝駆、自宅訪問などの攻撃力を得意とする野中の会社は、業界からは「野武士軍団」と言われているほどであった。
翌朝、野中は秋葉原のヤッチャ場へ行って、梨を段ボール一個分購入し、陣内医師の家に届けた。自宅には奥さまがおられた。多少田舎っぽい雰囲気のある陣内先生にしては品のいい奥さまだったので野中はちょっと驚いた。
翌々日、大村病院を訪ね、陣内副院長に会った。
「昨日は悪かったな。」
副院長は野中が同郷の好みでの行為と受取ってくれたようだった。それに副院長は外科系の医師らしくサッパリしていた。
「この病院はお前のとこのクスリは何がある?」
「何も採用されていません。」
「じゃ、何を入れたい?」
「抗生物質です。」
「それは、厳しいぞ。」
「病院にとってメリットのあるのがあります。」
「そうか。ところで院長をゴルフに連れて行けるか?」
「大丈夫です。」
「じゃ夕方、医局に来い。タイミングを見て、院長に話してやるから、」
「ありがとうございます。」
「院長は、他の奴の言うことは聞かないけど、おれの言うことはだいたい聞いてくれるから、」
野中は、副院長からアプローチしてよかったと思った。
医局へ行くと、誰もいなかった。今日はオペ日ではなかったから、大学から来ているアルバイトの医師たちも大学に戻るか、帰宅したためだろう。
間もなくして、副院長が病室回診から戻って来た。
「院長も、もうすぐ来るよ。」副院長は野中の顔を見ると言った。
野中は医局の冷蔵庫を開けて訊いた。「先生、何か飲みますか?」
「何が入っている、」
「何かドリンク剤があります。」
「じゃ、一本持って来てくれ。」
そんなことをしていると、院長も入って来た。
野中は院長にもドリンク剤を持って行った。
そこへ、「院長、こいつも九州の人間だって、」
院長は体格がいい。どっしりとソファに腰を下ろして、「何処だい?」とドリンク剤を飲みながら、訊いてきた。
「福岡です。」
「そうか。じゃ、副院長と同じか、」
そこへ副院長が口を挟んだ。「初代院長は佐世保だよ。」
野中は、なるほど〔大村〕姓なら、そうだろうと思った。
その初代院長は80歳代になってもまだ病院の医局に顔を出すこともあるという話は聞いていた。現院長は二代目なのである。
さらに「院長。ゴルフ、行こうって言ってるよ、」と副院長が言った。
「おれの言うことはだいたい聞いてくれる、」と言いながらも、副院長の会話ぶりには院長を立てている気持があることを野中は感じた。
「紫は取れるか?」院長が言った。
名門〔紫カントリークラブ〕のことだ。
「はい。やってみます。」
「よし。取れたら行こう。」
野中は病院の外に出て、赤電話から会社へ電話を入れた。〔紫カントリークラブ〕を押さえてもらうためだ。
玄関へもう一度戻ると、患者さんが受付で何やら文句を言っているところだった。
樹の下に車を駐車したら樹の葉が落ちてきて、車が汚れた。だから駐車場に立っているプラタナスの樹を伐ってほしいと言っているようだった。
野中は患者さんのわがままを胸の内で笑いながら、医局へ行って、「たぶん、取れると思います」と報告した。
翌月ゴルフに行って、野中の望む抗生物質が採用になった。川口事務局長が「こっちの方が、病院にとってもメリットがあります」と言ってくれた。
当然、今まで使用されていたメーカーのものは一気にゼロになった。そのメーカーは、今まで院内のトップであった。
ある日、病院の廊下でじっと野中を見ている男がいた。たぶんそのメーカーの者だろう。だからといって野中は別に見返したりはしなかった。ただ「あの湿気をふくんだ視線は誰かと似ている感じがするが、誰だったろう」と思いながら、知らんぷりしていた。
後刻、駐車場に行ってみると、野中の〔スカイライン〕のドアには、ガッチリと鍵で引っ掻いたような傷が付けられていた。十中八九、犯人はアイツだろうと思った。野中は、捕まえてぶん殴りたかった。しかし、営業上のことである。騒げば見っともない。ここは黙るしかないだろうと怒りを抑えた。
数日してから、そのメーカーの担当者は異動になったという話を卸のセールスから聞いた。
それから、野中は半年に一回は大村院長、陣内副院長、川口事務局長とのゴルフに付合った。陣内副院長は大村院長の医大の同級生、川口事務局長は大村院長と高校の同級生だった。院長は、野中の会社の社長と同じで、人の話を聞かないタイプであった。代わりに、副院長と事務局長は人の話をよく聞いてくれた。そんな二人だから二代目院長を見事に支えることができるのだろうと思っていた。
カーステレオの、ライオネル・ハンプトンのテープが終わった。次に野中はミルト・ジャクソンのカセットを差し込んだ。すぐに涼やかなモダン・ヴァイブの音が流れてくる。ジャズは中学のころからラジオでよく聞いていたせいもあるが、野中は好きだった。「趣味は得意先との橋渡し」と先輩が言っていたが、橋になる趣味と、ならない橋があるようだ。というのは、医者にはクラシック・ファンは多かった。当人か、奥様か、お子さんかが、クラシック音楽の何かに関わっていることが多いのである。だが、ジャズが好きだという医者はあまりいなかった。だから、ジャズが流れている間、野中は自分だけの時間のような気がして心地よいのであった。
野中は〔マイルドセブン〕の煙を吐きながら、ミルト・ジャクソンの語り合うような「ブライト・ブルース」の軽快なリズムに合わせて指でハンドルを叩いた。そして思った。大村院長、陣内副院長、川口事務局長、この三名はゴールデン・トライアングルだな、と。
ところが、半年後の晩秋だった。野中にとって想像もしていなかった事件が起きた。
野中は大村病院へ行く前に〔キャラバン〕に寄った。今朝、病院部の部長に電話したとき、信じられない話を聞かされた。
野中は車を塀の所に停めて、〔キャラバン〕のドアを押した。珈琲の香りが流れてきた。
「いらっしゃい。」奥さんがホット珈琲を運んで来てくれた。
オヤジさんは、生豆を一つひとつ選りすぐっているところだった。
野中が見ていると、オヤジさんは真剣な目をして言った。「生豆は、欠けた豆、老いた豆も入り混じっているから、それを取り出してから焙煎しないと濁った味になる」と。
それは今までもオヤジさんから何度も聞いていることだったが、その真剣さを見ると、今日は殊更感じるものがあった。
野中は珈琲を含みながら部長が言った台詞をもう一度繰り返した。
「大村病院の、川口事務局長が病院の薬剤購入費用を着服していたらしい。」
「野中係長さんに至急連絡してほしい」との卸の担当セールスからの伝言だということで、後輩の佐藤から病院部長へ連絡があったというのである。
大村病院の薬剤費は一カ月数千万円である。
「そんなバカな!」
口に含んだ珈琲が苦い。野中はすっかりブルーな気持に墜ち込んでいた。
一生懸命に豆を選別しているオヤジさんを見て野中は、「ここにいても始まらない。とにかく大村病院へ行ってみよう、」と溜息を吐きながら腰を上げた。
病院へ着いた野中は診療室の前に立った。何とかして副院長に会いたかった。いや顔を見るだけでもいい。状況が分かる。
野中は名前を呼ばれた。馴染みの看護婦が副院長に野中が来ていることを言ってくれたようである。
診察室に入った野中に、副院長が言った。
「もう聞いたか、」
野中は頷いた。
「夕方、おれを家まで送ってくれ、」
野中は「はい」と肯いた。
副院長の口調には院長を気遣っているような気配が感じられる。
野中は院長や副院長のことも気になっていたが、同時に事件によって病院自体がおかしくなり、自分の仕事まで飛び火するのではないかと心配した。でも、副院長の表情からすれば、それはなさそうだ。野中は杞憂の半分は解決したような気がした。
院長は人が良くて、何事も明快なところがあるが、やはり二代目らしくプライドは高い。事件後、そのプライドをどう守ってあげればいいか。たぶん副院長はそれを相談しようというのであろう。
外に出た野中は、公衆電話から大村病院に納品している卸の所長に電話し、「会いたい」と言った。
所長は2時に営業所で待っていると返事をした。
時計を見ると、少しだけ時間がある。かといって、昼飯はあまり食いたくない。車を走らせていると〔モスバーガー〕の看板が目に入った。「あれでも食うか」と野中は店の前に車を停めた。
卸の所長は担当セールスも呼び戻し、野中を待っていた。
「驚きましたね。」
「ええ、」
会ったものの、野中はこんなことは初めてだから、話をどう切り出したらよいのか分からなかった。
所長も用心をしている。あの病院で一番強いメーカーである野中に下手なことは言えないと思ったからだった。
「うちの社長がね、こんなことを言ってました。」
えっ、もう社長まで伝わっているのか、と野中は内心驚いたが、よく考えれば当然だ。卸にとっては金額回収に関わる大事件なんだから。
所長が続けた。「〔事務局長〕という役職名はあまりよくなかった、と。」
野中は、この所長は何を言ってるのかと思った。
「〔局長〕というのは偉いんだそうですよ」。
担当セールスも口を開いた。「川口事務局長は、家を新築されているのです。それもご立派な、」
ははん、と野中はやっと読めた。それへの流用。それは全て〝分不相応〟な勘違いによると指摘しているのか。
「そうですか。あの病院クラスなら、せいぜい〔事務長〕だった、というわけですか、」
思わず野中は立ち上がって、窓の方を見た。
この所長は大村病院の組織を改革をしろと言っているのだ。それも社長と相談の上で、そういう結論を出している。この所長は狸だなと感心した。
そこで問題となるのが、いわゆる「誰が鈴を付けるか」だ。
「あの病院は先代のときから支払はいいのです。今後も変わらないでしょう。卸にとってはありがたいお得意様です。ただ、今回のことは交通事故みたいなものと思っていますが、二度とこのよう事故が起こらないためには、」
「・・・・・・。」
「しかし、卸の立場としては病院の院長にそのようなことはとても申し上げられません。」
「・・・・・・。」
「私たちは野中さんを応援しますよ。」
また、先手を取られた。自分から電話したのだが、この所長は端から私が電話してくるのを待っていたのではないか。野中は、所長に、一本も、二本も取られたと思った。しかし、その代わり道が見えてきた。
夕方、病院の駐車場で待っていると、副院長がコートの襟を立てて首を肩に埋めたようにして、乗ってきた。
「ふう、今日は寒いな。」
野中はキーを回した。
二人とも暫く黙っていたが、やがて副院長がぽつんと言った。
「院長は一見豪放に見えるけど、シャイなんだ。友人と思っていた奴にやられて、相当ショックだったと思うよ。」
「そうですね。」
「お前はいつものように顔を出せよ。ただし川口のことは触れるな。」
「はい。」
また二人の会話は途切れたが、今度は野中が口を開いた。
「今後、支払はどなたが担当されるのですか。」
「さあ、おれは経理のことは分からん。」
「院長の奥さまが、ということはありますか。」
「それはないだろう。今まで病院経営はまったくノータッチだからな。逆に、どうしたらいい?」
「う~ん。やっぱり院長先生でしょうね。」
「院長がいちいち金を支払うのか。」
「いいえ、そういう実務は経理の担当者です。権限は院長ということです。」
「今までもそうだったろう、川口はちゃんと報告していたぞ。」
「いいえ。かなり信頼して、任せられていました。」
「そうか。信頼していたからな。ある意味川口は有能な男だったから、」
その有能な人はこのくらいの規模の病院ではいらないのですよ、とは言わなかった。それは先ほどの卸の社長の台詞だ。
代わりに、野中は「経営のことは院長が握っておかなければならないでしょう。」
「あいつがお坊ちゃんだったからこうなったというわけか。お前もよく言うよな。」
「いえ、そんな、」
車は副院長のお宅に着いた。しかし、陣内は家に入らない。
「そこでラーメンでも食って行こうか。車はここに駐めといていいよ、邪魔にならないから。」
「はい。」
陣内宅から1~2分歩くと豊島園駅である。その駅前に赤い暖簾が風で激しくはためくラーメン屋があった。
陣内が戸を開けて先に入った。
「熱燗。それと餃子と札幌ラーメン、二つ。」
すぐに酒がきた。
野中は陣内のコップに酒を注いだ。
「すまん。お前も少し飲めよ」と陣内が言っているところに、もう熱々の餃子と山のように盛られたラーメンがきた。見たところモヤシばかりである。
「おれたち九州モンのラーメンは、これじゃないけどな。ま、食えよ。」
「学生時代、東京にやって来て、真黒の醤油うどんとラーメンを見たときは驚きましたよ。」
「そうだよナ・・・。」
「でも、冬の寒いときは無償にラーメンを食いたくなるときありますよね。」
「さっき思い出したけどな、今月はあいつの誕生日だ。」
「・・・・・・。」
「励ます会をやるか。」
「いいですね。」
「今回は野中から言った方がいいかもしれない。」
「何て言いますか?」
「普通に誘えばいいよ。」
野中は、ステーキハウス〔六本木倶楽部〕へ大村院長と陣内副院長を誘った。
焦げたニンニクの匂いが香ばしい。赤い肉の表面がジュッジュッといい色に焼けていく。匂いと音だけでも、もう堪らない。
院長は「旨い、旨い」を連発しながら、人の倍ほどのステーキを食べて、いつものようにベンツで帰った。
野中は、副院長はいい提案をしてくれたと感謝した。今までのようなゴルフ会を続けていいのかと考えていたところであるが、定期的な食事会に切り替えるチャンスにもなると思った。
それにしても、偉いのは院長も、副院長も川口さんの悪口を一言も言わないことだ。
野中は〔キャラバン〕の珈琲を飲んでいた。
一段落したので、先ほど後輩の佐藤と同行して、卸の狸所長と会ったばかりであった。
所長は言った。「『適材適所』という言葉ありますが、今回は規模に見合った組織のあり方があるということを学びましたよ。」
「あの狸所長、よく言うよ」と野中は思った。
このとき、野中はライバル会社のあの担当者のじっと見詰める湿気をふくんだような視線と、川口さんの視線が似ていたことに初めて気が付いた。
サッパリしている陣内副院長と同じ院長補佐役でも、そこが違っていたのか、と野中は珈琲カップに向かって呟いた。
「それにしても、川口さんは今ごろどうしているだろう。もしかしたら院長だって、副院長だって、心の中ではそう思っているかもしれない。」
野中は、4人でゴルフをやっていた、あの時に戻りたいと願った。
そう思うと、なにか目頭が熱くなるのであった。
(Ⅲへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる:作〕