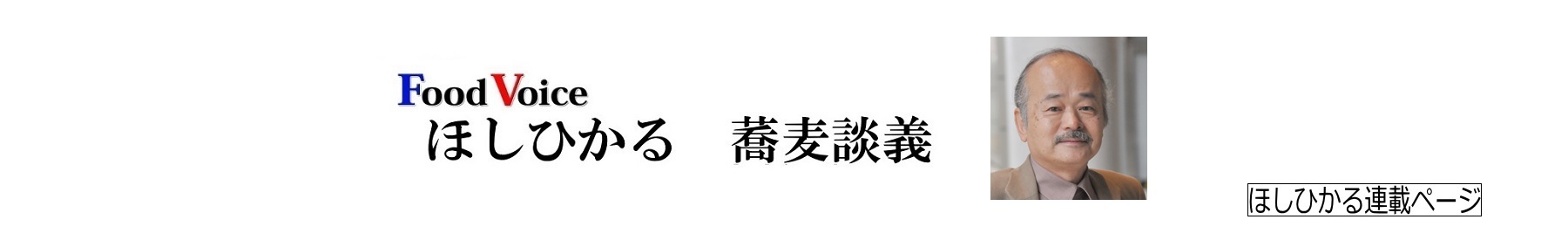第212話 どうづきそば
2025/12/06
お国そば物語⑰
穀類を粉にするには臼が欠かせない。その臼には、杵で搗いて潰す「搗臼」と、石臼と石臼を磨って粉にする「碾臼」があり、漢字も分けて使う。
搗臼は「臼」「碓」と記し、碾臼は「碾」「磑」で表すのが基本であるが、「臼」の方は一般的に使用するようになってきた。
そういえば、古代に日本武尊という英雄がいた。諱を「小碓尊」というから、碓=搗臼は古代から日本にはあったのだろう。その古代とはいつのころかというと、日本武尊の子が仲哀天皇、孫が応神天皇だとされているから日本史の原初のころの人物であるということになる。ただ、そのころ「小碓尊」なんていう立派な名前があったとは考えにくい。
となると、『記』『紀』が作成された天武天皇時代に「小碓尊」の諱がおくられたのであろうから、天武朝のころに「碓」という字があったということになる。
しかし「臼」自体は、香川県から出土した袈裟襷文銅鐸(弥生時代)に臼と竪杵の絵があることから、搗臼は稲の伝来とともに大陸から伝わったとされている。
ただ、今では麦や茶、それから蕎麦の実などは鎌倉時代の僧円爾(1202~80)が宋国から持ち帰ってから普及したと伝えられる碾臼で粉にする。
これは石の重さを利用して粉にするわけであるが、用途を離れてその重さが何かしら象徴的なことに結び付けられこともある。
先日、マーガレット・ドラブルの小説『碾臼』を読んでみた。この場合は人生の重荷の象徴として碾臼を題名としていた。
また、『マタイ伝』18-6には、「されど我を信ずる此の小さき者の一人を躓かする者は、寧ろ大なる碾臼を頸に懸けられ、海の深處に沈められんかた益なり」とある。この場合の碾臼は、それを頭に懸けて海に投ずるという最も残忍なる処刑に用いられたらしいが、とんでもない話である。
マそんなこともあるが、製粉が食糧の中で大きな分野を占めている今日、臼といえば碾臼ということになっている。
ところが、八ヶ岳山麓の茅野には、搗臼による蕎麦《どうづきそば》という驚愕の蕎麦がある。
それは、蕎麦の実を甘皮付きのまま低温水に漬けて、胴搗機で直捏ねして、生地にし、あとはそれを打って、《胴搗きの蕎麦》を完成させる。
蕎麦の香りと甘味が実に豊かで、しかも極粗挽きのため舌触りもかなり個性的だ。
茅野といえば、縄文のヴィーナスの故郷だが、胴搗きという超古式蕎麦は縄文の空気をも織りこんだような味がする。
私の舌学コレクションに加えておきたい蕎麦のひとつだ。
参考:お国そば物語シリーズ(第211、167、128、124、121、120、119、118、89、66、48、44、42、24、9、7話)、M・ド゜ラブル『碾臼』(河出文庫)、『聖書』、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕