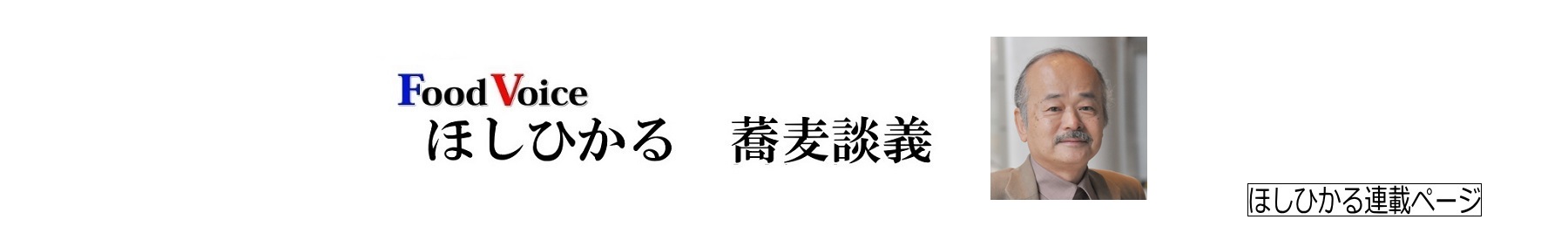第463話 人間にとっての和食
2025/12/06
映画『千年の一滴 だし しょうゆ』より
酵母「アスペルギルス・オリゼ」 は和食の味を決める味噌・醤油・酒・味醂・出汁をつくる、日本だけにある黴だそうだ。だから「国菌」ともいわれている。
そのミクロの黴の世界を、映画『千年の一滴 だし しょうゆ』では実に美しく描いていた。
二年前に一度観ていたが、いい映画だと思ったので、ソバリエさんたちを誘って今日の上映会に参加した。
今回は、和食文化国民会議の伏木亨会長(江戸ソバリエ講師)とこの映画を作った柴田昌平監督とのトークセッションも催された。映画観賞後に制作者と旨味のオーソリティのトークとは贅沢な企画だが、その内容はなかなか濃い味のものだった。
映画では味噌・醤油・酒・味醂・昆布・鰹節を作る、多くの職人や老舗が登場したが、監督は「この映画は人間のドキュメンタリーでもなく、料理の映画でもない。日本という自然を撮りたかった」と言い切った。そこがもう《和食文化》であると思う。なぜなら、和食には《自然崇拝》の精神が満ちているからだ。
諸外国の料理は甘・鹹・辛・酸・苦味を主張するソースが決め手であるから、こういう映画を製作するとなるとシェフが主役になりがちであるが、控えめな日本の出汁やつゆの話では、自然風景との関わりから入っていかなければならない。その自然には黴もある。「枯れ木に花を咲かせましょう」とばかりに、黴を活かして日本は鎌倉・室町時代に【旨味】を発見した。それは良くも悪くも日本は独自の料理文化を繰り広げていくことになった。
しかし、サムライ時代に完成した【旨味】を中心とした和食は、近代料理の自由・拡散化によって、歴史的にはいま危機に晒されている。
その上、近年は旨味より甘味や油味や激辛味が受けている。
日本人というのは、江戸時代までは甘味は、味醂か酒で味付けしていた。また日本の江戸時代までは油物を摂ることが少なかったから、半世紀ぐらい前までの日本人は油脂物の料理を食べるとお腹が痛くなる人さえいた。それに『冬ソナ』つまり韓流ブーム以前までの日本人は激辛を避け、上品な辛味を好んでいた。
また、蕎麦の食べ方でいえば、猪口を手に持って、蕎麦をつゆに付け、啜って食べることは日本の文化であった。
それを「なぜ、碗を手に持つのか?」「なぜ、啜って食べるのか?」などの他国の批判に日本人ですら同化し、「マナーが悪い」みたいなことを言っている人がいるのは、困ったことだ。
世界は違うから、面白いはずだ。それが、何もかもグローバル化し、均一化していったら、独自の文化はどうなるのか?
この映画を観た人は、「旨味って凄いなあ」「和食っていいな」という感想をもたれたと思う。
だから、最後に伏木先生がおっしゃったことが心に残った。
「甘味の美味しさ、油味の美味しさは病み付きの美味しさです。対して、日本人が発見した旨味は飽きない美味しさといえます。これからもこの旨味を中心にして、人間にとっての和食ということを考えていきたい」と。
《参考》
*平成29年11月24日 映画会『千年の一滴 だし しょうゆ』
〔文・挿絵 ☆ エッセイスト ほしひかる〕