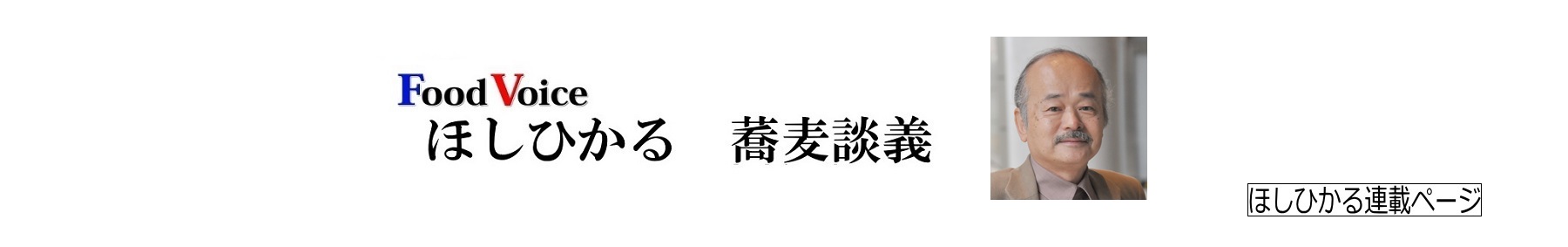第220話 絵の声を聴く
2025/12/06
『江戸名所図会』―「深大寺蕎麦」
―――「オーイッ」と呼わって船頭さんは大きな口をあいた。晩成先生は莞爾とした。「今行くよーッ」と思わず返辞をしようとした。
絵を見ることが好きな私は、ときどき絵画に関する読物に目を通すことがある。冒頭の幸田露伴の短編『観画談』もその一つだ。
主人公が画を観ていると、絵の中の船頭が立ち上がって、今も船を出そうとしながら、片手を挙げて、「乗らないか、乗らないか」と人を呼ぶ。船頭の顔がハッキリしないので、主人公はその絵に顔を近づける。すると船頭が「オーイッ」と呼わって大きな口をあいた。
私は、この『観画談』が非常に面白いと思った。なぜなら、絵画に関する本といってもたいていは、その絵がどんなに素晴らしいかを理論的に解説している物が多い。その点、この『観画談』は絵の中に入っていくという手法によって、絵を愛する心を表現しているのである。
立ち位置的な見方をすれば、前者は右から左へとなされる客観的な説明を傍観的に聞いているということになるだろう。対して、後者は向こう(絵)とこっち(読者)のやりとりを主体的に行い、そして自らが向こうに入り込もうとするという状況になったのだといえる。
そんなことを考えていたとき、一枚の絵と対峙することになった。『江戸名所図会』の中の「深大寺蕎麦」の絵である。
理由は、『蕎麦全書』と『江戸名所図会』が「深大寺蕎麦学」のテキストだと思い至り、それなら『江戸名所図会』の「深大寺蕎麦」の絵の中に入っていくことが、深大寺蕎麦の研究になると考えたからであった。
そのための研究舞台は、絶対「深大寺そばの学校」でなければならなかった。さっそく、学校側の方にご提案し、賛同をいただいた。
そして実際には、今年の受講生の皆さんを四組に分け、各々の組で研究・議論し、この絵から何を知ったか、どう想ったかなどを発表してもらおうということにした。
結果発表は、皆さんよく議論されており、なかには驚くべき視点をもっておられる方もいた。また学校長、副校長、深大寺執事長のコメントも素晴らしかった。
ここでは、その結果を「いつ、何処で、誰が、何を、どのようにして」という観方でまとめてみたいと思う。
◎いつ
絵の情景から秋であることは間違いないが、十三夜とした人もいた。
◎何処で
深大寺塔頭のひとつ多門院の接待茶屋(広さ二間半×九尺)ではないかという意見もあった。
◎誰が
一人は、深大寺79世住職とみて間違いないだろう。
古刹深大寺の客は上層階級、伝わっている人々も公弁法親王や大田南畝などの知識階級の人ばかり。これが深大寺の特徴でもある。
絵は、『名所図会』の発刊者齋藤月岑と絵師長谷川雪旦か、あるいは檀家の人かが描かがれているとみる人が多い。いずれにしても煙草盆の位置からして、右側の人物が主客だろう。なかには羽織の七つ梅の柄から判断して酒蔵関係の人かという説もあった。
◎何を
大笊のような器に盛った冷たい蕎麦を椀に小分けした《ぶっかけ蕎麦》として食べているのは間違いない。
料理は、精進料理が中心で茄子、里芋、味噌煮などと、多摩川の鮎もあったろう。
真ん中の水差に入っているのはお酒だろう。深大寺級なら、このような高価な器が在ってもおかしくない。
◎どのようにして
深大寺蕎麦は早くから(江戸初期の江戸蕎麦初見の常明寺のころとほぼ同時期)打たれていた。深大寺にとっても蕎麦は自慢の接待であり、何かにつけて行われていた。この絵の日も、豊作に感謝しての接待だった。
断っておくが、観画談的アプローチは理論や理屈や知識ではない。トコロジスト⇒Jindaistの感性で、絵の声を聴いて、語り合わなければならない。
地元の人が「ああいうときは茄子、里芋、鮎をご馳走しただろう」といった思いを大切にしなければならない。
そこに、深大寺そばの学校の皆さんによる観画談の価値がある。
これを元に物語などを想像したら、なお面白いだろう。
〔深大寺そばの学校講師、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕