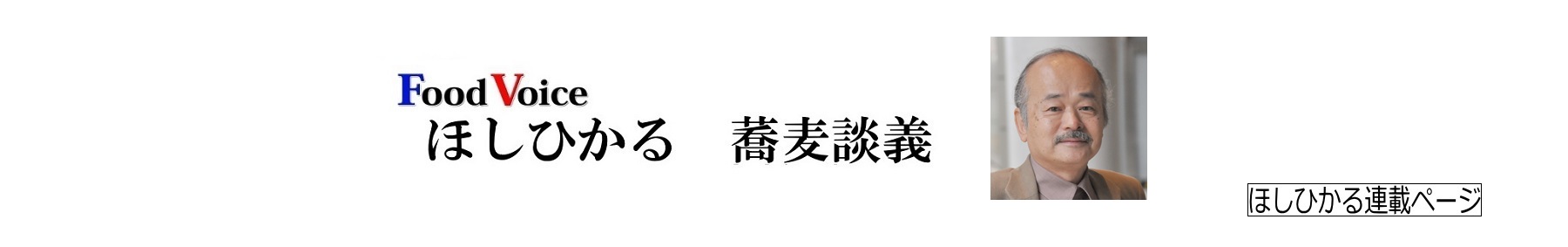第706話「赤い靴はいてた女の子」
『世界蕎麦文学全集』物語 (中締め)
四季に一度開催していた更科堀井の会に、ソバリエの畑さんが大事な一人娘の菜桜ちゃんを何度が連れて来られたことがあった。初対面のときから菜桜ちゃんは人懐こくて賢くて、可愛い子だった。最初に会ったのは小学1年生のときだったけど、今は2年生、そして明日からは3年生だという。
このコロナ禍では、世間のたいていの会がそうであるように、私たちも会を開くことが難しい状況になった。そんななか、菜桜ちゃんから何度もお手紙をもらった。嬉しかったからご返事を出さなければと思ったが、正直にいうとこれがなかなか難しかった。何て書けばいいのだろうか。小学生時代というのは大人はみんな通ってきたはずなのに、まるで異星人へ出す便りみたいな心境である。でもとにかく書いて、読み直した。すると、しまった! 私は普通に漢字を使って書いていた。苦笑いをしながら、菜桜ちゃんの手紙をもう一度見直して、彼女が使っている漢字以外はひらがなに直した。そうやって5通ほどのやりとりをした。
でもやはりお手紙だけでは申訳ない、そんな気持がわいてきて「今度お蕎麦を食べましょう」ということになり、今日、更科堀井さんにお邪魔しているわけである。もちろんママさん同伴のデート。
さて、お蕎麦は菜桜ちゃんは《ざる蕎麦》、大人たちは《桜切り》を食べながらいろんなお話をしているとき、近くに「赤い靴の女の子」像があったことを思い出した。麻布永坂は童謡の「赤い靴」ゆかりの所として知られているが、今の小学生はこの童謡を知っているだろうかと思って尋ねてみたら、「知らない」と言う。やはり、そうか。
それにしても、赤い靴、赤ずきん、赤毛のアン・・・なんて、たくさんのお話があるけれど、女の子って赤が好きなのだろうか。
うちのチビ(孫)は歩けるようになったころ「クチュ、ママ(娘)と一緒、銀色」というようなことを言いながら、自分の小さな銀色のスニーカーとママの銀色のスニーカーを自慢げに並べていたが、女の子というのは靴が好きなんだろうか、それともママと一緒というのが嬉しいのだろうかと思ったものだった。
そんな話をしたものだから、帰る途中、菜桜ちゃんを赤い靴の像のある所へ案内した。すると写真のとおり、女の子はマスクを着けている。何か、コロナ禍の子供たちと重なって憐れに見えてきた。
赤い靴 はいてた 女の子
異人さんに つれられて 行っちゃった
横浜の 埠頭から 船に乗って
異人さんに つれられて行っちゃった
今では 青い目に なっちゃって
異人さんの お国に いるんだろう
赤い靴 見るたびに 考える
異人さんに 逢うたび 考える
野口雨情作詞・本居長世作曲
これが野口雨情作詞の童謡である。
実は、この赤い靴の少女には哀しい物語がある。
菜桜ちゃん向けの話ではないが、物語はAさんという人が未婚で女児を生んだところから始まる。後にAさんは北海道開拓の男性と結婚することになるが、開拓は仕事も生活も過酷なことでよく知られていた。とても幼児を連れては海峡を渡れない。そこでAさんはアメリカ人の神父さんに女児を養女として引き取ってもらうことにした。
しかしその神父さんが帰国しようというとき女の子は結核に罹ってしまった。やむなく神父は麻布鳥居坂の「永坂孤女院」に預けて帰国したが、女の子は明治44年に9才で早世したらしい。
後年、野口雨情はその子の母と知り合うことになり、話を聞いてこの童謡を作った。ただしこの時点では、母親も雨情も、女の子が亡くなっていたことは知らなかった。だから、あの子はいまごろ他人同然の青い目の女の子になっているだろうというのは、母子の縁を切ったことへの痛恨の思いであった。
ところが、この「赤い靴」の童謡が発表されると、「赤い靴を履いた女の子は、私の姉です」と名乗り出た女性がいた。その人は母親が結婚してから生まれた女子であったから、赤い靴の女の子は異父姉というわけである。
この逸話に関心をもったのが北海道出身の菊地寛だった。彼は5年にわたる取材の後に小説『赤い靴はいてた女の子』を発表した。
これが「赤い靴」にまつわる話であるが、明治大正は現代とちがってある人たちにとっては生きていくのに辛苦の時代であった。そのなかで、野口雨情や菊地寛が創作(童謡・小説)を通して言いたかったのは、幼児にとって母とは、この世で一番大切な存在だということにちがいない。
『世界蕎麦文学全集』
*野口雨情「赤い靴」
*菊地寛『赤い靴はいてた女の子』(1979年)
江戸ソバリエ認定委員長 ほし☆ひかる