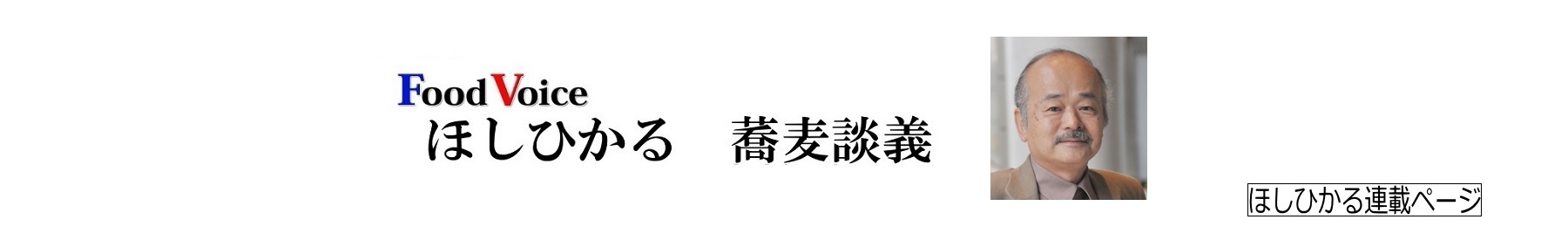第717話 青春の白鳳仏
2025/12/06
~ 吉永小百合と深大寺白鳳仏 ~
土門拳(1909~1990)という写真家の話です。彼は寺院や仏像、古陶など一貫して日本の美を撮り続けた写真家です。日本人が造った物に深い愛情と憧憬を抱き、古いものから新しいものを掬い上げていたといいます。
その土門は、作品発表の場として、展示会より写真集を重視していたそうです。なるほど、一つひとつの作品が主役かもしれない展示会と、主題をもった一冊の写真集はたしかに違います。
そんなことから上梓したものに『古寺巡礼』という写真集があります。それはカメラによる古寺巡礼です。開始したのは昭和15年5月からだったと本人は述べています。またある人が土門拳さんはこんな人だという逸話を紹介しています。
~ 若い人のなかには「古寺」を「ふるでら」と言う人がいるが、だからといって「こじ」とフリガナをふるのではなく、「こじ」と読んでほしいときちんと文章にして書く人だ ~ と。
私も賛成です。漢字が読めないからと言われて、ひらがなで書いてやるとか、フリガナを振ってやるとかではなく、「古寺」は「こじ」と読みなさいと言うこと。
それが日本人が造った物に深い愛情と憧憬を抱くことだと思います。
さて、もちろん土門の古寺巡礼には深大寺の白鳳仏も入っています。そのうちの釈迦の手の写真は第3指、第4指が折れているところを土門らしくリアルに撮っていますが、その折れた指に深大寺白鳳仏の千年の謎、すなわち江戸末期になって初めて存在が語られるようになった深大寺白鳳仏釈迦像の謎が込められています。
しかし、世間を驚かせた土門の仕事は「女優と文化財」シリーズです。土門が1964年(昭和39年)から2年間、月刊誌『婦人公論』の表紙を飾った作品です。岡田茉莉子、若尾文子、佐久間良子、三田佳子、岩下志麻など、当時のトップ女優と国宝級文化財との組み合わせを撮った作品は、土門作品の中でも異色作だといわれています。話を持ち込まれた当初、土門は断ったそうですが、昭和39年というのは東京オリンピックの年、当時の編集長三枝佐枝子は五輪で来日する外国人にも日本の文化財を紹介したいということから、「一流女優+国宝級文化財」を熱心に口説かれてスタートしたということらしいです。文化財の選定は土門拳。衣装デザインは森英恵。契約は1年の連載でしたが、大好評につき2年に延長され、24点の作品になりました。このなかでわれわれが目を引くのが、吉永小百合(1945~)+深大寺釈迦倚像です。掲載は『婦人公論』1965年(昭和40年)8月号ですから、撮ったのは1965年の春ぐらいでしょう。吉永小百合さんは20歳です。
白鳳仏というのは〝青春性〟が感じられます。つまり飛鳥の渡来仏から奈良・平安の国産仏への過渡期、人間でいえば青年期の仏像です。亀井の「豊頬の美」はそれを言っています。
また、『万葉集』には主として白鳳・天平時代の歌が収載されていますが、最古の歌として仁徳天皇の皇后磐姫と雄略天皇の歌が載っています。そして聖徳太子時代が少し入って、白鳳・天平時代が満載になります。
その点について、万葉学者の中西進は面白い指摘をしています。『古事記』も五世紀から始まり、それ以前は神話の時代となっている。つまりは『古事記』も『万葉集』も同じ歴史認識で編纂されていると言うのです。
なぜそういう編纂方針なのでしょうか?考えられることは、
❶当時の人たちは、日本の歴史は五世紀の古墳時代に産声をあげ、いま(白鳳・天平時代)は青年期にあると認識していた。
❷あるいは現在霧の中と呼ばれている三世紀・四世紀も分っていながら、何らかの理由であえてこのような歴史認識をとった。
そのどちらなのかは、分かりません。ただそのため日本史の三世紀・四世紀は、いまもって霧の中のままということです。
そうした歴史認識を、写真家は写真家の感性で理解していたのでしょう。だから土門拳は20歳の吉永小百合の内面の張りを日本仏像の青春期として表現したのでしょう。
深大寺とは、私たちに日本の歴史を認識させてくれる所かもしれません。
参考:土門拳『古寺巡礼』(美術出版社)
〔深大寺そば学院 學監・江戸ソバリエ認定委員長 ほし☆ひかる〕