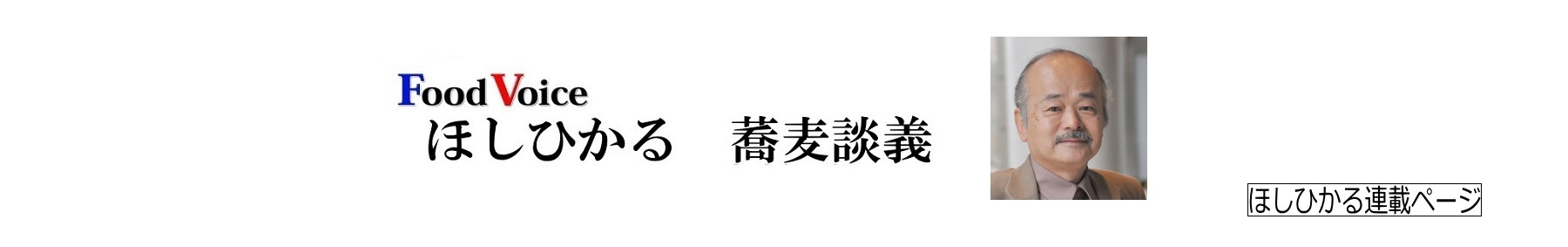第261話 ミレー〔種を播く人〕
2025/12/06
~ 蕎麦を播く人 ~
ミレーの〔種を播く人〕(1850年画)は何の種を播いているのか? 小麦か? 蕎麦か? と話題になることがある。
ミレー絵画の研究家は、背景の急な傾斜はバルビゾンとは異なるから、画は故郷のノルマンディーだといい、一帯は痩せた土地で小麦は育たないから、播いているの蕎麦だという。
そうかもしれないが、それより重要なことは、種播きは『聖書』の中の重要なキーワードであるということだ。
たとえば、15世紀制作の〔ベリー公のいとも豪華なる時祷書〕 などには種播く人が描かれている。しかも驚くことにその種播きの格好を見ると、ミレーも参考にしたのではないかと思われるほどよく似ている。ミレーは、これに信仰深かった父の姿を重ねたのではないだろうか。父の種播きは、農夫のあるべき姿、そしてキリストの言う人間のあるべき姿として描いたのである。
だから、小麦とか、蕎麦の問題ではなく「種」でいいのである。
蕎麦といえば、ミレーには〔夏、蕎麦の収穫〕という作品がある。この度も一緒に来日していた。
ミレー絵画の研究家は、遠くにシャイイの教会が見えるから、これはバルビゾン村の絵だというが、どうだろうか。
ただ、この絵の原題は〔Lete,les batteurs de sarrasin〕となっているから、 〔夏、蕎麦を打つ人々〕と題している場合もある。「Sarrasin」はフランス語で「蕎麦」、「batteurs」は「打つ」の意だから、後者の題が相応しい。「Sarrasin」は蕎麦をサラセン人あるいは異邦人がフランスに持ち込んだところに由来するという。
ちなみに英語では蕎麦は「Buckwheat」、「ブナに似た形の実を付ける小麦」という意味の造語。造語ができたということは古代ヨーロッパには蕎麦はなかったという証拠。中国四川・雲南の蕎麦の起源地から、多くの異邦人の手を経て伝えられたのだろう。その時期は13世紀ごろであったらしい。
〔夏、蕎麦の収穫〕の絵は、手前に蕎麦が島立てに積んである。蕎麦は稲のように一斉に実を付けないから、未熟のうちに刈り取って、穂先を上にして束ねて乾燥させる。これによって茎や葉の養分が実に転流し、未熟の実を完熟へと導く。とは、私の尊敬する氏原暉男先生がご著書の中で解説されていることである。干し上がった束は女性たちが籠に入れて運び、その向こうで男たちが叩き棒で脱穀している。これが「batteurs de sarrasin」である。左手には白い煙が立ちのぼっている。殻を燃やし、その後に灰は肥料となるのである。
ところで日本では「蕎麦を打つ」というが、なぜ「打つ」というのかは分かっていない。蕎麦を作るとき、延し棒をドンドン打ちつけるからという説もあるが、どうだろうか。打開、打算、打ち破る、打ち明ける、打ち消すなどという言葉があるが、これらは実際に〝打つ〟わけではなく、行動を強調するような使い方である。「蕎麦打ち」もそこからきているのだろうか。しかし今日、ミレーの絵を観ているうちに、収穫の際の言葉をそのまま使っているのだろうかとも思った。
さて、フランスでは収穫された蕎麦は当初《蕎麦粥》や《蕎麦掻》のようにして食べていたらしいが、そのうちにブルターニュ地方で初めて《ガレット》が誕生し、各地に広がった。ミレーが描いた蕎麦もノルマンディーの農民たちは《ガレット》にして食したにちがいない
一方の、山梨に辿り着いたミレーの蕎麦の種は当然《蕎麦切》にして食べられたのだろうが、アメリカに渡ったミレーの蕎麦の実は《蕎麦粉のパンケーキ》としてアメリカ人に愛されたのだろう。
フォスターの曲「おゝ、スザンナ」(1848年)の歌詞や、オー・ヘンリーの小説「献立表の春」(1904~05年)、ヘミングウェイの『われらの時代』には《蕎麦粉のパンケーキ》が出てくる。
とくに『われらの時代』ではパンケーキを焼いてコーヒーを淹れる場面があるが、それはヘミングウェイの1919年ミシガン州フォクス川での体験が基となっているという。
というわけではないが、その日は私も蕎麦粉を焼いて食べた。形はガレットとも、パンケーキともつかぬものだったが、メープルシロッブをかけて食べると美味しかった。
参考:レイモンカザル『ベリー候の豪華時祷書』(中央公論社)、氏原暉男『ソバを知り、ソバを生かす』(柴田書店)
〔エッセイスト ☆ ほしひかる〕