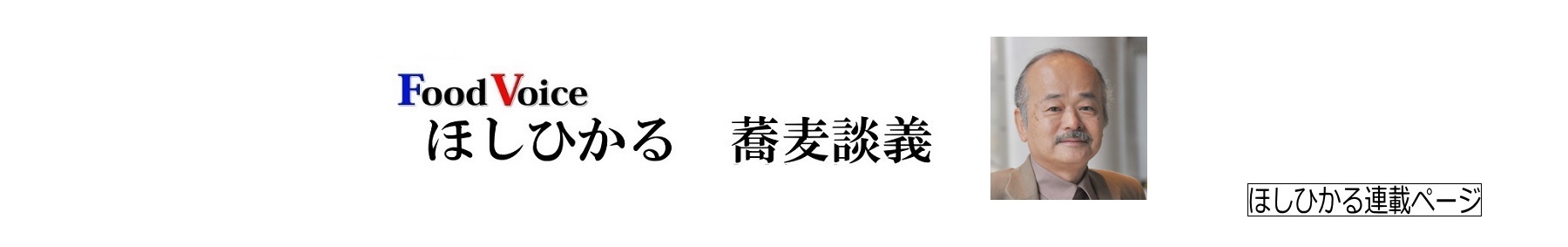第940話 竹馬の友の味
2025/12/06
人間の交友関係について、作家の吉本ばななさんがNHK『アカデミア』という番組なかで、「10年たったら誰もいないです。残っている人は本当に仲のいい人で、10年たったら毎日遊んでいた人は、誰も一緒に遊んでないです」とおっしゃってました。
友人関係を一概に年数だけで決めるわけにはいきませんが、それでも幼いころから長年付合っている古い友を、「親友」では物足りなくて兄弟同様の「竹馬の友」と言ったりしますから、吉本ばななさんの10年説も一理あるわけです。
竹馬の友といえば、私にもそういう男がいました。
ただ残念なことに、数年前に先に逝ってしまったので「いました」と悲しい過去形なのです。その友は「哲」といいましたが、近所どうしで小学校に入る前から一緒に遊び、小・中・高・大と同じ学校に通いました。
中・高のころはお互いの家に泊まり込むことも多く、母親たちは朝、布団から出ている子供たちの頭数を数えて、朝飯の支度をしていました。
子供時代というのは、成績表を見れば判るところがあります。私も彼も、5段階中3~4といえば、想像はつくでしょう。それに、そのころは各家庭の兄弟は三、四人ぐらいいましたので、上か中か下かによって、見事に性格がちがっていました。私は長男、彼は末っ子。この差からもだいたい性格が想像がつくと思いますが、長男の私は年上の人とはあまり付き合わないところがあり、末っ子の彼はたいていの人から好かれていました。ただそのなかにチンピラ系の人間もいました。しかし私たちは兄弟同然ということをみんな知っていましたので、私はチンピラ系にも顔を出していたし、哲は私の友人とも話しました。そこで私の友人たちが驚いたのは哲の頭の回転の良さでした。
だいたいが私はしなければならない受験勉強のようなものには手を付けず、好きなものだけに関心を寄せていました。作文なんかは先生によって上手と言われたり、下手と言われたりしていましが、後になってこの矛盾が分かりました。どういうことかといいますと、国語の先生はお前は作文が上手だと言い、算数などの先生は作文が下手だと言うのです。絵もまったく同じでした。絵の先生は褒め、そうでない先生からは貶されました。何のことはありません。見る者が専門家か、そうでないかの違いだったのです。中高生ながら、人間の勉強になったと思いましたが、私はこういうのが得意でした。一方の彼は勉強をまったくしませんでした。試験前夜だけ、サッと目を通しますが、それだけで理解するのです。
そんなことで、受験勉強というのをまったくやったことのない二人は東京の私立大学へ通うようになりましたが、二人の学生生活4年間はほとんど一緒で、しかも麻雀に明け暮れていました。
そして夏休みと冬休みは一緒に夜汽車で帰郷します。新幹線はまだ世に登場していませんでした。東京駅午前10:30発の急行〝雲仙西海〟に乗りますと、下関駅に5:10に着きます。懐かしの九州入りです。そして佐賀駅のホームには7:51降り立ちます。懐かしの故郷の空気を思い切り吸います。なにしろ座席に21時間20分座ったままです。でも車内では若者も大人も、男も女も、すぐ仲良くなります。出会った人の話を笑いながら、驚きながら聞き、本でも読むようにその人たちの人生を想像したりします。
東京に戻るときは、運賃は親に出してもらえますから、格上の特急〝さくら〟の寝台列車に乗ることができます。佐賀発18:57➡東京着11:27、16時間30分です。急行列車と比べようもなくリッチな気分です。
私たちは兄弟喧嘩はしても、園児のころから、成人過ぎまで一回も喧嘩をしたことがありませんでした。幼いころから20才までの長い年月が互いを認め合い、信頼というものが醸し出されていたのだと思います。これが「竹馬の友」というのでしょう。
こうした二人が得意だったのは、友だち作りでした。学生時代は友だちにあふれていました。
が、やがて卒業です。哲は九州で就職し、私は東京に残りました。
それから、ウン十年経って孫ができたころ、哲が漏らした言葉がありました。
「お前がいたから、オレはチンピラにならなかったと思っている」。「それを言うなら、お前がいたから、オレはそういう社会を覗き見ることができた。それは大きかった」と思いました。実際、そうでした。ダチのダチが、インネンを付けたことを得意気にしゃべるのを聞いて、インネンを付けられないスベを知りました。そういうようなことはたくさんありました。
そんな哲が70才過ぎたころ、病で急逝しました。
両親の訃報にも涙しなかった私は、押さえ切れずに泣きました。
そのとき私は、学生時代によく二人で食べた練馬の中華料理屋に行ってみたくなりました。
かつてその店は、西武線の練馬駅と桜台駅の中ほどにありました。
九州出身の私たちは東京のラーメンはあまり口に合いませんでした。そこで食べていたのが主に湯麵だったのです。しかも店主は九州出身ということでしたから、味が合っていたのかもしれません。しょっちゅう食べていました。値段は確か100円とちょっとぐらいだったと思います。
その日、私は練馬駅で下りました。もちろん今、その店があろうはずがありません。しかも、当時は20才前後のころの舌です。そして今の言い方をすればたかが「街中華」です。その湯麵が美味しいとか美味しくないとかの話ではありません。それでも今の私にとっては最高の湯麵になるでしょう。私は、半世紀以上もの昔、哲と啜った湯麵の香りと湯気を夢見ながら桜台駅まで歩いていました。
(竹馬の友「哲」の命日に書く)
写真:佐賀新聞
エッセイスト
ほし☆ひかる