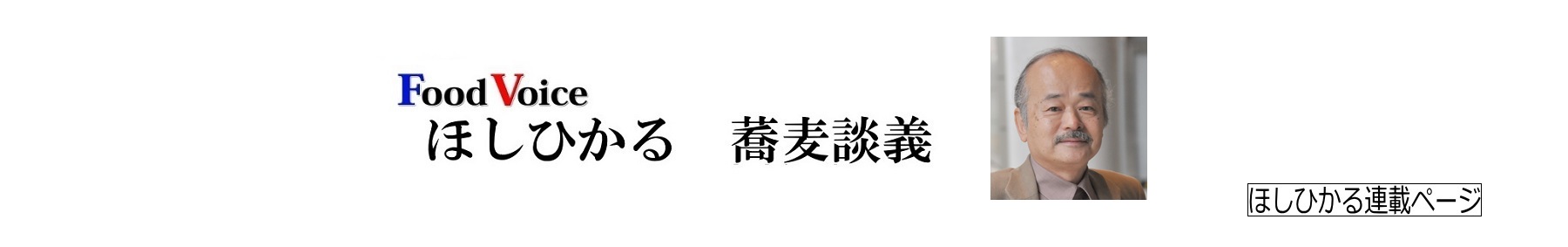第349話 春は曙、蕎麦は《桜切り》
2025/12/06
『枕草子』にならって、「春は曙、お蕎麦は《桜切り》」というコピーを「協会だより」の4月号に載せたからというわけでもないが、この春も《桜切り》をすいぶん頂いた。
「更科堀井」(麻布)「車屋」(八王子)「松翁」(神田)で2回、「小松庵」(駒込)で1回、江戸ソバリエの皆さんとの打合せ、朝日カルチャーの蕎麦講座、そしてニューヨークからのお客様との打合せしたときだった。
桜といえば、思い出す味がある。
十年ぐらい前、私は麻布にある広報会社に勤務していた。その会社のクライアントは外国の会社だったから、社長はじめ社員の半数以上が帰国子女だった。当時は、カルフォルニアのワイン、アメリカの肉、ノルウェーのサーモンなどの広報を手掛けていた。
会社ではハワイ生まれだとか、イギリス人とか、アメリカからの帰国子女とかのスタッフに囲まれて、私は戸惑うことばかりであった。幸い、助けてくれる親切な女子社員がいたからよかったものの、彼女がいなければ落ち込んでいただろう。
そんなある日、お昼の弁当を買いに行ったときだった。先に彼女が来ていた。とうぜん帰りは一緒になって歩いて社へ戻ることになるが、途中小さな公園を通れば近道だ。そこを通りかかったとき「ここで食べていきましょうか♪」と彼女が言った。彼女は日ごろから人一倍気遣いのできる人として社内でも人気者であった。それでなくて若くてカッコイイ女性がそう言うのだから、断る理由がない。
二人は桜樹の下に設置してあった椅子に小学生みたいに並んで坐って、弁当を頂いた。そのとき私はなぜか彼女の靴に目がいったので、訊いてみた。すると「イタリアに行ったとき、気に入ったから買ってきたの」と照れたように、嬉しそうに話してくれた。桜の花弁が乱舞する中でだ。そのとき私は、舞い落ちてきた桜の花弁も食べてしまったが、何となく桜色の味がした。
そこで思いついたのが、《桜切り》の話でも書いてみようかということだった。
それから、《桜切り》を考案した浅草の蕎麦職人の小説を書き始めた。設定は蕎麦食地蔵尊が浅草に在したころということにした。
最初は更科粉に桜の花弁を練り込んでみたが、うまくいかない。そこで菓子屋の桜餅をヒントに裏漉した桜の葉を使うことにした。蒸して塩抜きして葉脈の硬い部分を取り除いたりして、完成させるというストーリーだった。
最後は、主人公の蕎麦職人に「春の蕎麦切りができたので、秋の蕎麦切りも」と発想させた。
『枕草子』には「秋は夕暮。山の端、烏、雁、風の音、虫の音」とあるがこれを活かすのは難しい。このうちの、雁ならぬ《鴨南蛮》の開発物語は歴史上存在するから、勝手に創作するわけにはいかない。
そこで、春は桜、秋は紅葉の日本らしく「今度は、《紅葉切り》に挑戦してみるか」というところで終わらせた。
そんなわけで、駄作ながらも一つの作品ができたのも彼女のお陰だった。
よく、「君は何でも参考にして採り入れる」と人様から笑われるが、少し弁明しなければならないことがある。
「何でも」というのはちょっと言い過ぎで、感性のある人の言動が参考になるのだと思う。彼女もそういう人だった。現に今、彼女は日本画の修業中だと聞いている。そのうちに桜満開の日本画を拝することができるだろう♪
参考:ほしひかる「桜咲くころ桜切り」(『BAAB』)
〔エッセイスト ☆ ほしひかる〕