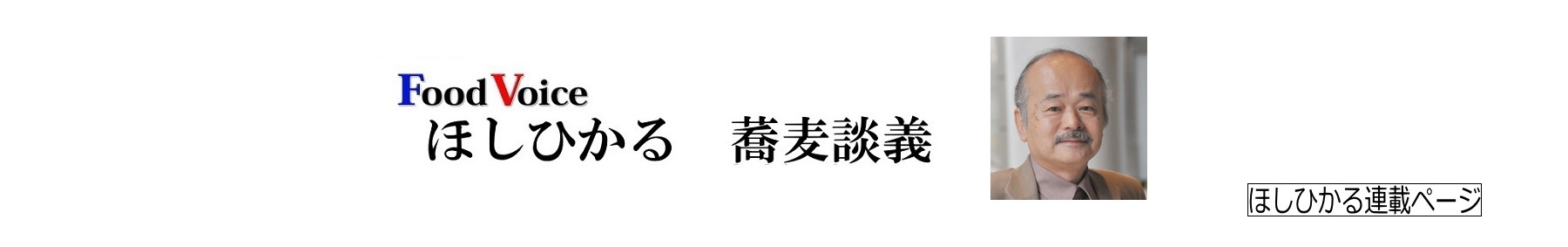第153話 陶然亭談
2025/12/06
《 蕎麦膳 》二
青木正児(1887-1964) が論じる京都の「陶然亭」、大久保恒次(1897-1983) が贔屓にする大阪の「田舎亭」、神吉拓郎(1928-)が描く東京の「柳亭」。
三人の食通が語る、この「三都 - 男の隠れ家」については、【フードボイス「蕎麦談義」(93話)】で述べたことがあるから、ここでは繰り返さないが、その紹介駄文を見た、京都の蕎麦仲間が「三条辺りに『陶然亭』という料理屋があるから、来なさいよ」と勧めてくれたことがある。もちろん大いに興味をそそられるが、なかなか機会がなくまだ訪ねるまでにはいたっていなかった。
ところがである。昨年、ある仲間と中国へ行ったときの最後の夜、ホテルで北京市内の地図を眺めていたら、「陶然亭公園」という文字が目に飛び込んできた。思わず私はベッドで上半身を起こし、目を凝らして見ると、場所は昨日訪ねた「天壇公園」からそう遠くない所だ。しかも地下鉄「陶然亭駅」までもがある。「へえ!」と一人で呟きながら、今度は室内のインターネットで検索してみた。すると中国語で書いてあるからよく分からないが、白居易の詩「共君一醉一陶然」から採って名付けた公園というようなことが説明してあった。
《与梦得沽酒闲饮且约后期》
白居易
少时犹不忧生计, 老后谁能惜酒钱。
共把十千沽一斗, 相看七十欠三年。
闲征雅令穷经史, 醉听清吟胜管弦。
更待菊黄家酝熟, 共君一醉一陶然。
当然、「陶然亭公園」とやらへ行ってみたい気持もわいてきた。だが残念ながら明日は、帰国のため空港へ行かなければならない。ただ幸いなことに、この度の旅行では多くの公園を訪れていたから、中国の公園のだいたいの雰囲気はつかめていた。それに、白居易の詩に由来するという「陶然亭公園」が北京にあることを知っただけでも十分意味があった。
これはもう、お誘いの京都の陶然亭まで行かなければならないと、そのとき心に決めたほどであった。
そして、イザその日になったとき、せっかく教えてくれた知人はヨーロッパへ旅行中ということでご一緒することはできなかった。が、ともあれ私は京都の骨董通りのような小道を探し歩いていた。すぐに大きな暖簾が掛かっている店が見えた。私は足を速め、そして「ついに来たか」とばかりに店の前に立って暖簾の字をしみじみ見つめたものだった。後で聞いたところによると、字は女将さんが書いたのだという。
暖簾を分けて店内に入ると、カウンターとテーブル席が二つ、その一隅には倉本聡さんが書かれた字が架かっていた。奥には小さな石灯籠と木のある空間があった。青木が紹介していた建仁寺垣も見える。そこからの爽やかな風が届いていた。
店主に尋ねると、やはり青木の「陶然亭」に触発されて店名を同じにしたのだという。
思った通りだ。そこに、何故この《蕎麦膳》シリーズに「陶然亭」が登場するかの訳がある。実は、「陶然亭」を紹介した青木正児こそ、麺や蕎麦をかじっている者にとっては古典的必読書の一つとされる『華国風味』の著者だからである。だから、何か通じるものがあるのかもしれないと、前々から「陶然亭」を訪ねてみたいと思っていたのである。
さてさて、お待ちかねの料理である。最初に出てきたのは、ガラスの器に盛られた稲庭の素麺であった。いかにも青木ゆかりの「陶然亭」らしいではないか。それにコシっぷりがいい。
日本人のコシ感というのは、この素麺(乾麺)を口にしたときから目覚めたのではないだろうかと、理由もなく思った。そういう初体験を経た日本人が蕎麦というものを知ったとき、蕎麦の性質上をコシのある麺に茹でた方がよいことを自然に見い出したのではないだろうか。と、素麺を二、三口啜る間に想ったりした。
そういえば、麺関係の本を専門に出している幹書房の編集の人たちは、「最近は、うどんも、ラーメンも限りなく、蕎麦に近づいてきている」と話していた。つまり「うどんもコシをいうようになり、そしてうどんもラーメンも付ける麺になって、まるで蕎麦そっくりだ」というのである。私は、それはそうだろうと思っている。なぜならば「蕎麦」は日本人好みの麺として完成したものだからである。故藤村和夫先生は「江戸時代は、うどんというのは、だいたい軟らかいものだった。だから江戸っ子はうどんを嫌った。だからこそ、蕎麦はうどんとはちがう世界を目指した」とおっしゃっていた。私の故郷は、島原の乱のころにはすでにうどんを作っていたというほど古い麺史をもつクニであるが、そこにどっぷり浸かって90歳で亡くなった母もまた「うどんはフワ~となるように茹でなければ」と言っていた。うどんとは、そんなものだった。なのに最近は、コシだ、コシだというようになった。まさに全麺が蕎麦を目標にしている感である。
ところで、九州生まれの私は、どちらかといえば薄口醤油、白味噌に馴染んだ西日本の舌を持っている。そしてここ上方も西日本の味の部類に入るだろうが、住んだことのない私は、上方料理の何たるかを知らない。よく、京都の食材は乾物、野菜、豆腐、湯葉、麩、白身の魚。そして大阪は魚介類が多いときくが、今は京都も大阪もそんなにちがいはないだろう。と、爼板の上で捌かれる白身の魚を見ながら思ったりした。
次に出てきた、紋甲烏賊の刺身は塩と酢橘で食べる。これは醤油文化に浸った東京人の舌には新鮮である。しかも極細に切ってあるから、柔らかくて食べやすい。
鱸も旬は夏、今の季節は、洗いを山葵醤油で食べるのが一番いい。川海苔の香りが顔を離しても漂ってくる。
青木の言う「陶然亭」では、御撮肴として、浅草海苔を炙って揉んで小皿に入れ、花鰹を一撮みつまみ込んで醤油をかけ、擦山葵を多量に副えて出すという。つまり、花鰹の味と海苔の香りと、山葵の新鮮な気 ― これが和食の基本だと主張しているのである。江戸時代の林信篤が『本朝食鑑』で、「およそ食に形あり、色あり、気あり、味わいあり」と述べていることと通じるところであろう。
鱧の真っ白い身とコンガリした皮は梅肉で頂く。六月に一番脂がのる鶏魚は餡かけ。みんな西日本に多い旬の魚ばかりだ。
そういえば、「田舎亭」の大久保は「〝はかない〟のが日本料理」だと言っていた。しかし、私は「京料理が〝はかない〟」のであって、日本料理全体をそう断定するのは少し違うのではないと思う。江戸料理には〝はかなさ〟より、むしろ〝骨太さ〟の感触があるし、また江戸前の寿司、天麩羅、鰻を見ても〝はかない〟食感はない。
京料理の〝はかなさ〟というのは、今日の料理のように口にしただけでホロリと崩れる少片の鱧のような白身の魚や、極細の切身に見る繊細さであろう。
その時もっとも相応しい音楽が聞こえてくるとしたら、ショパンのピアノ協奏曲第一番第1楽章♪ 絵を描けば、満開の桜の花びらが風に舞い散る景色♪といったところだろうか。華麗であっても、こわれそうな〝はかなさ〟、それが原大和民族の饗宴。そして新大和民族のそれが〝粋〟で〝一本筋が通っていそうな〟江戸料理。われわれ日本人は、この二層の舌を自在に操っているのかもしれない、と京の都の三条で思ったりした。
そういえば、「京三条砂場のお万」という美人画が『虎ノ門砂場』の二階に飾ってあった。栄里という浮世絵師の「三都美人絵」のうちの一枚だそうだ。
そんなことを想い浮かべながら、「ご馳走さま」を言って席を立つと、ご夫婦が外まで見送ってくれた。こういう心遣いを「後味がいい」というのだろう。
今日は、これから嵯峨野の落柿舎を訪ねるつもりだ。元禄時代の松尾芭蕉が「俳諧と蕎麦切は江戸の水によく合う」と予言した所だ。
参考:青木正児「陶然亭」(岩波文庫)、大久保恒次「田舎亭」(柴田書店)、神吉拓郎「二ノ橋 柳亭」(文春文庫)。「蕎麦談義」(第138、93話)
《 蕎麦膳 》シリーズ(第153、150話)
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕