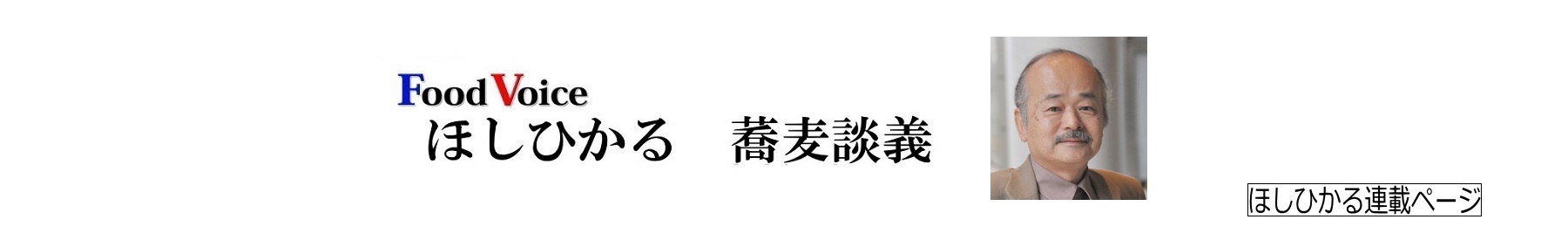第561話 三笠の山にいでし月
2025/12/06
722年の詔
奈良へ行ったので、元正天皇の御陵にお詣りしてきた。
蕎麦通を自称するなら、救荒作物として蕎麦栽培を初めて奨励した元正天皇の御陵にお詣りすべきだが、京都・奈良旅行にはいつも連れがいるため「お墓へ行こう」とはなかなか口に出せなかった。
ところが、今回は一人旅、いい機会だ。
近鉄奈良駅からバスに乗って奈保山御陵で下車。辺りにに何もない。ただ御陵を拝し、小高くなった古墳を仰ぎ見るだけである。
ここに眠る天皇は諱を「元正」、生存中は「氷高皇女」といった。生涯独身で通した女帝である。そのためかどうか、史書も伝承も〝美貌の女帝〟と伝え、永井路子、三枝和子、里中満智子らの創作意欲を刺激して、多くの作品に描かれてきた。
私も、かつて拙い小説に書いたことがあるが、そのときは新天皇即位の大嘗祭について想像しながら書いた。今年は新天皇が誕生し、大嘗祭が行われる予定であるから、その様子が今から大いに気になっているところである。
そんなわけだが、それにしてもずいぶん前に書いたというのに、なぜ今日になってお詣りする気になったかといえば、昨秋に開催された中日蕎麦学国際フォーラムにおいて、北京大学の賈蕙萱先生が胡銓の詩に「蕎麦が救荒作物」だったことを証明する詩があると紹介されたからに他ならない。
胡銓《夏旱至秋田家種蕎麦以補歳事》
千里還経赤地連 老農作苦也堪怜
来牟不復歌豊歳 蕎麦犹能救歉年
山色浅深秋潑黛 田毛上下暁披綿
天公莫遣霜如雪 赤子嗷嗷要解懸
題の《夏旱至秋田家種荞麦以補歳事》は「夏の旱から秋にいたるまで農家が蕎麦を植えてその年を凌いだ」という意味。詩の「荞麦犹能救歉年」は「蕎麦は凶作の年をよく救う」という意味である。
胡銓は、文学者であったが、政治家でもあったから、「救荒」に視点を当てた詩を創ったのだろう。
ただし、胡銓は1102年〜80年の人である。一方の元正天皇(715~724)が救荒を勧めたのは、722年の詔である。じゃ、救荒作の考え方は日本が早かったのかというと、そんなことはあるまい。この頃は多くの遣唐使たちが往還している世紀である。
そうした日中交流の中で、蕎麦が救荒作物という考え方も中国から伝来したことはまちがいない。
おそらく、8世紀前頃から蕎麦は救荒作物としての位置にあったのだろう。
それゆえに中国の正式料理には蕎麦が食材として使われることはなかった。
見上げれば、昼下がりの淡い月が奈保山西陵に眠る皇女を見守っていた。
そういえば、717年に渡唐した阿倍仲麻呂はついに帰還できず、望郷の念を歌にしている。
~ 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に いでし月かも ~
「中国で見る月も、日本で見る月も同じ月なら、やはり故郷で月を眺めたい」と仲麻呂が慟哭した、あの月である。
後記:これまで寺社の「御朱印」を頂くことがあったが、この日は「御陵印」があることを知ったので、事務所を訪ねて初めて捺した。
〔文・写真 ☆ 江戸ソバリエ認定委員 ほしひかる〕