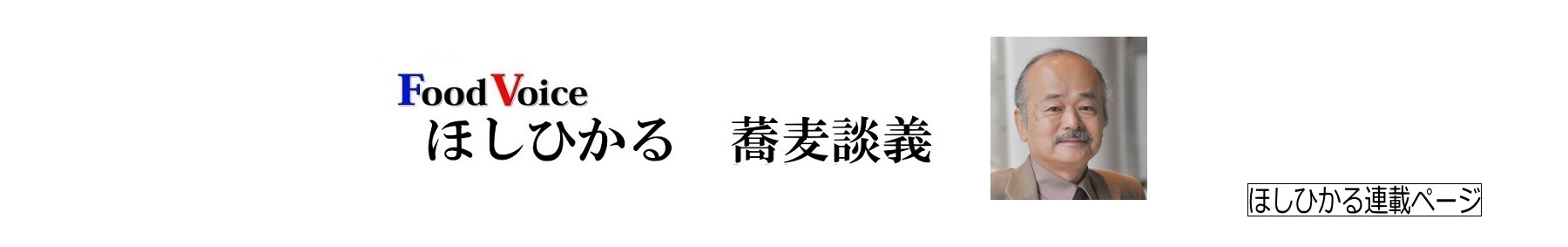第661話 「渋さ」について
2025/12/06
~ 『世界蕎麦文学全集』物語3 ~
前の659話で気になることがある。それは粋の舞台は「土間で・・・」という点である。江戸では皆、「土間で、粋に啜っていたのか?」という疑問が生じてくる。
そうだとすれば、座敷で蕎麦を食べている絵として有名な重政の『絵本浅紫』(1769年刊)や雪旦の『深大寺蕎麦』(1815、16年ごろ取材)はどう解釈すればいいのだろうか。
賢明な江戸ソバリエ、とくに江戸ソバリエ寺方蕎麦研究会の人ならば、江戸時代には座敷の「寺方蕎麦」あるいは「御前蕎麦」と、土間的な「町方蕎麦」の二つの流れが在ったとおっしゃるだろう。

それなら、前話で述べたように「町方蕎麦」が〝粋〟を信条としていたのならば、座敷の蕎麦はどういう世界であったのだろうか?
それを考えるにあたって、先ず江戸の人口構成を見てみよう。
江戸は100~150万ぐらいであったといわれるが、正確なところは分からない。というのは各藩の武士人口は軍事機密上、明らかにされていないからである。それでも、人口の約6割以上は武士などの支配者層であったことが推定されている。したがってほぼ4割が農・工・商の民の被支配者層だったということになる。
ただ、外食という視点で見た場合、外食と縁のない水飲み百姓を外し、また例示した二枚の絵に描かれているように羽織を着た町人は同じ町人でも上流階級の人たちになるから、そのことを計算に入れれば、身分的経済的な町人は約3割となり、上流階級は約7割だったという見方ができる。
言葉を換えれば、この3割の町人たちが粋の世界となる人たちであり、7割の武士や上層階級の町民たちが〝土間の粋〟とは違う〝座敷〟蕎麦を味わっていたということになる。
ここでの問題は、その座敷蕎麦はどういう世界なのかということであるが、たまたま九鬼周造は、〝粋〟に類似する言葉として〝上品〟と〝渋味〟を挙げているが、これが座敷蕎麦の世界に近いのではないかと小生は考える。
ちなみに、〝渋〟とは、茶道から生まれた日本の味である。と、よく言われるが、赤ワインの渋味はどうなんだろう。今度ソムリエさんに伺ってみよう。
話をお茶に戻して、栄西が宋の国から伝えた茶は「酸・辛・甘・鹹・苦」の五味のうちの〝苦〟なる飲み物であった。しかしそれが日本に土着すると、和食の〝旨味〟を引き出すための〝渋味〟を求める不発酵茶となったのである。そしてもともとは味覚の渋味であったが、深みのある美の基準へと発展して「渋し・渋き・渋い(形容詞)、渋さ・渋み(名詞)、渋く(副詞)」という言葉が生まれたのは江戸中期ころだという。
もちろん、蕎麦に〝渋味〟はない。だが〝渋〟という美はある。
では、〝渋さ〟とは何かといえば、柳宗悦は、〝渋さ〟の要素は簡素、深み、謙虚、静寂、自然さ、健康である・・・と、述べている。
私は、この簡素、深み、自然さ・・・こそが座敷蕎麦の世界にふさわしいと思う。
そんなとき、日本橋人形町の「蕎ノ字」という蕎麦屋で、ある蕎麦会が開かれた。この店は天麩羅が美味しいと評判の店であったが、締めに供された静岡の《川根在来》は記憶に残る蕎麦だった。詳しく言えば、在来種らしく野趣性あふれる蕎麦だったが、店主の腕によって細切りに仕上げてあった。その《川根在来種》の原始性が喉の奥へと渡っているのを感じた私は、平出隆という詩人がエッセイの中で《対馬在来》を「原始の蕎麦」と讃えていたことを思い出した。詩人である平出も蕎麦の深い世界を彷徨したのだろうと思った。
ともあれ、蕎麦には粋の世界と渋さの世界があることは確かなのだ・・・。
【世界蕎麦文学全集】
5.北尾重政 画『絵本浅紫』
6.齋藤三代 筆・長谷川雪旦 画『江戸名所図会』
7.栄西 著『喫茶養生記』
8.柳宗悦 著「渋さについて」
9.平出隆 著「原始の蕎麦」
文 ☆ 江戸ソバリエ認定委員長 ほしひかる
写真:雪旦「深大寺蕎麦」と再現図
対馬より朝鮮半島をのぞむ