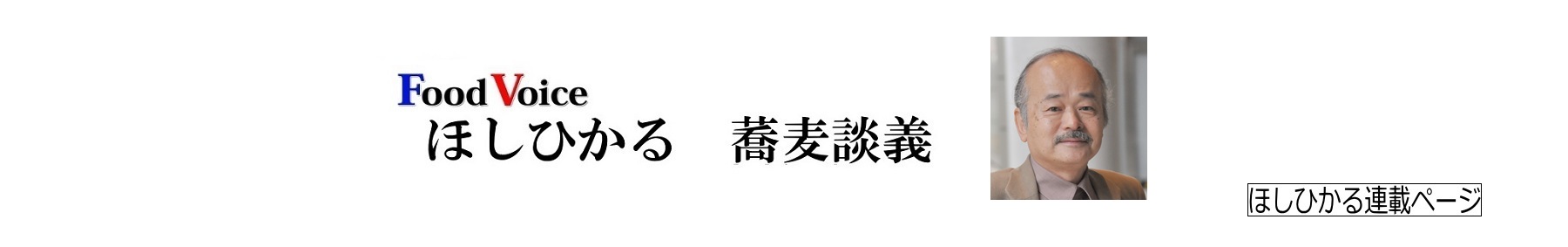第270話 平成:吾輩ハ猫デアル
マンションのわが家のベランダで「ミー・ミー・ミー♪」と子猫の鳴き声がする。覗いてみると三匹の赤チャンが生まれていた。今から11~12年前のことだったが、その内の一匹はすぐ死んだ。残る兄と妹は庭でママ猫に見守られながら、いつも仲良く戯れ合っていた。ママは気品があって女王のような美人、イヤ美猫だったから子猫たちもいい顔をしていた。兄妹はすくすく育ち、親子の行動範囲は庭からマンションの周囲まで広がって、道行く人たちを振返らせていた。そのうちに、とうとう美猫のママと、血筋を受け継いだ妹は可愛らしく甘え上手だったから、通りかがりの猫好きの人にもらわれていった。おそらく母娘とも、今も猫可愛がりされているのだろう。「人間も、猫も、美人は得だ」と管理人さんと話したものだった。
残ったお兄ちゃんは、「シロ」という名前をもらい、管理人さんが「猫をイヤがる人もおられるだろうから」と館内に入らないように躾し、ゴミ収納室でトイレと食事と寝るように教えられた。シロは利口でいい子だったから、それを守っていた。だから皆さんから好かれ、マンションの住人の一人(一匹)として認められるようになった。
しかし彼は雄であった。他の猫が縄張に入ろうとすると、シロは許さない。猛然と襲いかかる。お蔭で当マンションはシロ王国となった。
その一方では、私がゴミを捨てに行くと、私の足音を耳にしただけで出てきて「摩ってくれ」と猫撫声で要求する。
私といえば、まるで夏目漱石にでもなったようなつもりでシロが気にいって、それに応えていた。何せ漱石は、あの『吾輩ハ猫デアル』を生み出し、大文豪になった人である。なぜ大文豪になったかといえば・・・。
その一、漱石は「吾猫」を家族の一員として扱った。それまで文学などに登場する猫は、a)「猫化騒動」のような怪猫か、b)あるいは飼猫であった。あの桃太郎は雉・猿・犬を部下にしたが、だいたい飼われた動物というのは紐で繋がれるか、小屋に入れられかして、餌を与えられる動物であったが、c)漱石の「吾猫」は家族の一員として家の中で自由を与えられていた。これはまるで猫に人権を与えたかのような画期的なことであった。
そう思ってあらためて見回すと、a)今はもう怪猫もいなくなったし、b)紐で繋がれた猫も少なくなった。c)ほとんどが家族の一員ばかりである。猫の立場から言わせてもらえば、やはり漱石先生は百年後を見据えたエライ人だったのである。
その二、漱石先生は『吾猫』の中で「蕎麦の食べ方」を披露している。なにしろ当時は「蕎麦の食い方ぐらいでガタガタ言うな」という時代であった。それを敢えて真向から挑んだものだから、話題になって、やがては落語に採り入れられ、笑いの対象にされてしまった。お蔭で世間でも広く知られるようになったところから、漱石先生は時代と日本文化を深く見通す眼力をもった偉い作家であると、蕎麦の立場からも思うのである。
そんなわけもあって、【猫 ⇒ 漱石 ⇒ 蕎麦】のイメージをもつ私としては、シロを可愛がることが任務だと思うようにもなったし、その気持をシロも受けとめてくれた。そのためシロは私に撫でてもらうのが一番のお好みだった。私が出ていくと、身を任せるようにゴロッと横になるのである。そういうアヤシイ関係を皆さんは呆れていたものだった。
ところが、キミマロの台詞ではないが、あれから十年! 突然、シロの最期のときが訪れた。たぶん病気だったのだろう。管理人さんが涙ながらに、そのことを振れ回ったため、日ごろシロに癒された人たちがゴミ室に集まった。
弱ったシロは目を閉じていた。「気付かなくてゴメン」みんながそう思った。管理人さんが瞼を広げてやると、私をジッと見つめた。十年前の赤児のときと同じ目であった。シロは最期の声を出した。「ミャオ!ありがとう」と。そして夜更にあの世へ逝ってしまった。
翌朝、ゴミ室には多くの花束が積まれた。そして昼にささやかなお葬式が行われ、マンションの人に見送られてシロは火葬場に行った。
翌日、お骨となったシロは自分の部屋=ゴミ収納室に戻ってきた。それから四十九日の間、花だけは供えられていたが、皆さんは歯が欠けたようなモノ足りなさを感じていた。たしか城山三郎に『そうか、もう君はいないのか』というエッセイがあったように思うが、まさにそういう心境だった。
四十九日が経って、お骨はペット寺に納骨されることになった。だが、管理人さんは「縁のない場所にシロが永眠することに気持的にしっくりこない」と言って、お骨を少し持ち帰った。
「それならば」と、シロが生まれたわが家の庭に葬ってやろうということになった。たまたま庭にはお地蔵さんを祀っていたから、そこに埋めてやった。
いわゆる分骨であるが素性的にはここが何よりも安住の地であると思った。私は「どうだ、シロ。漱石先生が作った猫の墓よりいいだろう」と言いながら線香を立てた。
そんなことがあったからなのか、それとも月日の経過からか、皆さんのお心もだいぶおさまってきて、新しい年を迎えようという気持になってきた。
数日後、私は久しぶりに柏の「竹やぶ」さんを訪れた。店主の阿部孝雄さんは蕎麦屋を越えたアーティストであることは、業界でも知られている。
行ってみると、相変わらずお店全体がアート作品の群れである。そんな阿部さんに私はいつも刺激を受ける。言ってみれば、そのために行くようなところがあるのかもしれない。
そして幸いなことに、いつも私は何かしらのお土産をいただいてしまうのだが、この度いただいたのは、何と! 光背につつまれた招猫だった。やはり【蕎麦 ⇒ 猫】のご縁は深かったのである。
参考:夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』(大倉書店)、夏目鏡子「猫の墓」(文春文庫『漱石の思い出』)、半藤末利子『夏目家の福猫』(新潮文庫)、内田百閒『贋作吾輩は猫である』(福武文庫)、城山三郎『そうか、もう君はいないのか』(新潮文庫)、
〔エッセイスト ☆ ほしひかる〕