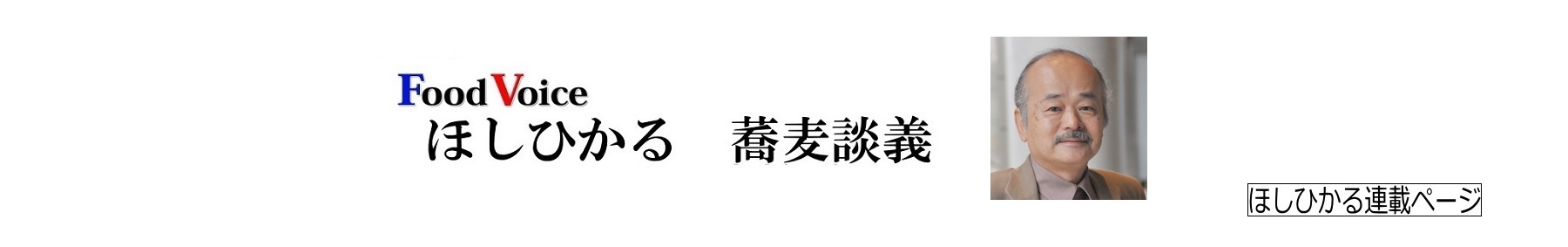第187話 地 元 力
☆日本語
「生蕎麦」は何と読むのか? と、時々尋ねられることがある。つまり「きそば」か、「なまそば」かというわけだ。答は、お酒の「生一本」と同じ「き」、「きそば」である。
要するに、江戸時代は〝音〟が主の、《読む>書く》状態であったから、たとえ漢字で表記してあったとしても、発音からくる当字と思った方がいい。だから「起蕎麦」とか、「キそバ」と書いてあるものもあり、漢字、カタカナ、ひらがなを無秩序に使っていたのである。というか、各藩が主体性をもって自國の治政を行っている云わば「合州国日本」では統一された国語がなかったから、とにかく知っている字を自由に使うというルール以前の段階だったのである。
それが明治になって中央集権国家となり、そして教育も一般庶民級までが徹底され、国語を勉強して漢字の意味を知ったため、「きそば」は「生蕎麦」と書こうということになった。
以来、日本人は《読む>書く》を脱して《読む+書く》へと進化したのである。
たとえば「そばやのそば」は聞いただけでは「蕎麦屋の蕎麦」なのか、あるいは「蕎麦屋の傍」なのか判断できなかったのが、漢字を見て「蕎麦」と「傍」を判別できるようになったのである。
☆朗読会
そんなことをある所で話しているとき、大変な電話がかかってきた。舞台演出家の小山ゆうな様という方が、私の書いた民話を朗読会のテキストに使いたいとおっしゃる。驚いた。しかしよくよく聞いてみると、それが文京区の事業ということから、私の「文章」というより、「文京の民話」に注目されたためということが分かった。それでも人様の目にとまるということは嬉しいことだ。
その会は6回連続の講習会になっていた。興味深々の私も、うち3回だけ顔を出させてもらった。
テキストとしては私が書いた「八百屋お七」や「文京の民話」、また他の民話などが準備されていた。参加者おのおのが好きな作品を選んで朗読をしよう、というわけである。
先ずは参考のためにということで、1日目は舞台俳優の松村良太さんと川島拓さんが読んでくれた。
自分が書いたものを彼らが真剣に、情感をこめて、読んでくれる。こんな経験は初めてで、感動のため、背中がゾクゾクするほどであった。
そのあとで朗読のコツのようなことを講師の小山さんや松村・川島さんたちから教えてもらった。
一つは、句読点は文章上のこと、読む際は無視していいとのこと。
これまで、「。」は句点、「、」は読点といい、読むために便利な区切りというのが常識だと思っていた。でも、よく考えると昔の、つまり《読む>書く》時代の文章には読む点は付いていないから、今日教えてもらったことの方が正しいのかもしれない。
二つは、声に出して読むということと朗読とは違うということだった。朗読は「伝える」ためのものだという。そういう目で、いや耳で、朗読のコツを聞いていると、納得するところがかなりあった。
それは、ここが面白いという山場を決めること。そうすると、ゆっくり読む箇所と情感込めて盛り上げる箇所が見えてくる。またその山場を想像することも大事になってくる。そのとき、登場人物はもちろんのこと、使用されているあらゆる言葉を想像するのだが、想像は人によって千差万別である。
この情感力ということに関しては、自分や皆さんの朗読を聞いているかぎり、女性が男性より優れている。まるで幼な子に読んできかせるように登場人物に成り切った声で見事に朗読される。そんなことを隣の席に座っておられたC(女性)さんに話したら、「女は化粧するからネ」とおっしゃった。うまいことを言う。男の声はいつでも何処でもスッピンだが、女の声は時と場合によって化粧する、というわけだ。勿論これがすべてではないだろうが、シャレた見方だ。
それからもうひとつの想像力についてであるが、これについても面白い体験を得た。民話でも「お蕎麦の稲荷」などはすでにひとつの物語として伝えられており、それを書き留めることは比較的簡単だ。一方では、「ちょっと、こんなことを聞いた」程度の話がある。それが「根津の幽霊」だった。「幽霊が出るらしい」。ただそれだけの伝承である。それを書くとき多少前後に何かそれらしいことを付け加えたが、それでも話としては何かが足りない、と思いながら作業を終えた。
ところがである。今日これを読んでくれたBさんは話の物足りなさを見事に撥除けてくれた。とはいうものの、「どうしてだろうか?」とその謎を解くべく、演出家さんや俳優さん、そしてBさんに尋ねてみた。
その結論は、Bさんが根津に長いこと住まわれていて、根津の風土が身体に染み付き、それが説得力となって表現されたのだろうということになった。これを「地元力」というのであろうか。人間の不思議なところである。
☆地産地消
さて、蕎麦の話である。食べ物の世界にも当然地元力がある。
いままで美味しかった蕎麦はたくさんあるが、その中に忘れられない蕎麦がある。それは千葉で食べた千葉在来種と、深大寺で頂いた深大寺蕎麦である。
昨年末、千葉の野呂地区を訪ね、一帯で採れる千葉在来の蕎麦を食べた。
打ってくれたのは千葉在来普及協議会のMさんだった。香り、風味、食感、いずれも最高だった。
それから今年の1月、東京の深大寺を訪ね、一帯で採れる深大寺蕎麦を食べた。打ってくれたのは深大寺蕎麦の再生に力を尽くしておられるAさんだった。このときもとても美味しかった。
この二種の蕎麦に共通する鍵は「地元」ということだった。採れ立て、挽き立て、打ち立て、茹で立てであることはむろんのこと、Mさんも、Aさんも各々の蕎麦を自ら手塩にかけて栽培されているところから、お二方ともに各々の蕎麦の性質をわが子のように塾知されているのであった。身体の中に取り込まれたその塾知が蕎麦を打つ際の呼吸に現われるのだろう。
これが地元力である。だから、江戸蕎麦は江戸・東京の蕎麦屋で食べる方が美味しいし、日本の蕎麦は日本で食べる方が美味しい。
老舗「かんだやぶ」の堀田康彦さんが、「日本の蕎麦を食べたければ、日本に来なさい」とおっしゃるのも自然である。
となれば、その土地に伝わる民話の朗読会をやろうと企画された小山さんの慧眼が素晴らしい。
参考:小山ゆうな企画「文京区に伝わる昔話で朗読体験しよう」(平成25年2月:文京区汐見地域活動センター)、文京ふるさと歴史館友の会『文京の民話』、ほしひかる作「お七とお嶋、涙の拭裟」(江戸下町文化研究会『江戸人紀』)、
深大寺蕎麦(第187、167、155、154、132、128、124、48、36、9、7話)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕