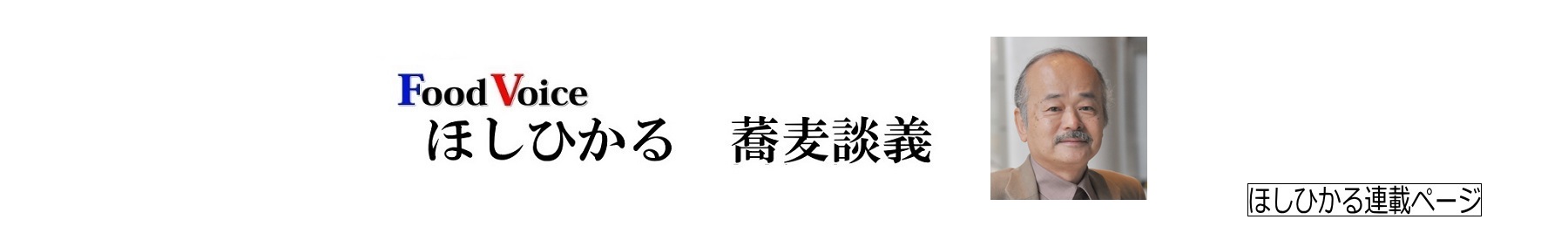第327話 小説「コーヒー・ブルース- XIV」
2025/12/06
~ Lilac Wine ♪~
このところ野中は、通産省と厚生省の外郭団体の人で、アメリカの医療情報システムを研修してきたという岩崎という人物と面談を重ねていた。あるベンチャービジネスの会合で名刺交換してから訪ねるようになり、3度目の今日は後輩の古賀と一緒だった。
「今日は、将来の医療の話をしてみますか。」
「はい。」
「も少ししたら、病院と医院と家庭がコンピューターでつながるんですよ、そのシステムをワークステイションといいます。」
古賀が眼を光らせた。
「そのころになると、ドクターのデスクの上にパーソナルコンピューターが置いてあって、ドクターは診療開始前にスイッチを入れる。そうすると患者さんから電子メイルがきている。コンピューターには患者さんのこれまでの病状や検査データが蓄積されている。ドクターはそのデータを見ながら、患者さんの質問に回答して上げる。」
「データが蓄積されているのは便利ですね。」
「そのファイルを病院⇔クリニック間で送受すれば、データを共有できます。紙だと書き写したり、複写して持参したり、郵送したり、ファックスしたりしなければならないけど、それだと救急医療では間に合わない。その点、コンピューターによるワークステーションを構築していると〔医療情報〕を共有できる。」
「〔情報化医療〕もしくは〔情報医療〕ですか、」
「〔情報医療〕! 面白い♪ そんな言葉を使った人は、誰もいませんよ。野中さんはいつも言葉が的確ですね!」
「最近〔情報社会〕って、やたらというじゃありませんか。だったら〔情報医療〕というのもあるんじゃないですか。」
「本当に情報社会になったら、わざわさそう呼ぶ人はいなくなるでしょうが、到来時期には刺激的な言葉ですよ。ぼくも使わせてもらいますよ。これからは〔情報化医療〕だって。」
「それから、ひとついいですか? さきほどの電子メイルって何ですか?」
「文字通り手紙の電子版、コンピューターを繋げておけば、お互が文章でやりとりすることができます。」
「はあ。しかし、文字だけで医療相談なんて成立するでしょうか? Face to face、あるいは触診が医療の基本中の基本じゃないですか?」
「いい指摘ですね。野中さん、古賀さん。もう夕方ですけど、会社に戻らなければなりませんか?」
「いえ。今日は土曜日ですから、もう直帰しますよ。」
「だったら、飯でも食いに行きませんか? 駅前の蕎麦屋ですが。」
「いいですよ。」
岩崎は二人を四谷駅前の蕎麦屋には連れて行った。
適当につまみとビールを頼むやいなや、岩崎は話し出す。「さきほどの話ですけどね。医療の基本はFace to face、あるいは触診、というのはその通りだと思いますよ。しかし、それに少しでも近づこうとしているのがテクノロジーでしょう。寒さを防ぐには焚火がいいけど、効率が悪いから電気の暖房機が発明される。歩くのが基本だけど、馬車や自動車が発明される。みたいなことと同じじゃないですか?」
「うーん、そう言われると、反論の余地がないですけど、医療は心身が壊れている人間が相手だから、少し考慮しましょうよっていうところがあるような感じですね。」
「分かりますよ。しかしテクノロジーの波は何処にでも押し寄せてきますね。」
「でしょうね、」
「そしてテクノロジーの全てがいいことだとは限らない。弊害というのが必ず伴います。だからこそ、薬剤には、つまり物事には作用と副作用が必ずあるんだと理解している製薬会社の人に、この医療情報、じゃなかった情報医療の世界に関わってもらうのは大事なことだと思っているのですよ。」
「なるほど。」
「実のところ、薬剤の処方同様、情報システムの操作もプロが携わるべきだと思っているんですが、それを言うと不遜だと言われたりします。しかし情報システムが拡大していくにつれ、悪い点も広がることを思えば、そう言いたくなります。そして皮肉なことに悪いことほど早く浸透するのですよね。」
「・・・・・・、」
「一方、テクノロジーというのは汎用でなければなりません。だから、プロだけだなんて言ってると、怪訝な顔をされます。というわけで、せめて、作用と副作用があることは当然だという世界の製薬会社の人に、この情報医療の世界に関わってもらいたいと思うのです。」
「すごい所に話を持ってきますね。」
「ちょっと教えてほしいんだけど、製薬会社の人は、薬剤を信じているの? それとも道具ていどだと思っているの?」
「これまた、すごいことを訊いてきますね。尋問だ。ははは。」
「どうなの?」
「部署によって違うでしょうね。開発した者は信じているでしょう。営業員は、そうですね、どちらかといおえば治療のツールの一つぐらいにしか思ってないでしょうね。」
「うん、そこなんだ。コンピューターもツールていどに考えてほしいと思っているんだけどね。」
「なるほど。そういう話だったんですね。」
話は続いたが、野中は半分も理解しただろうかと自問自答しながら、聞いていた。
そして三人は、最後に蕎麦を食べて別れたが、野中と古賀は近くの喫茶店で、もう一度話を整理してみることにした。
「野中さん。やっぱり、アメリカですかね。」
「ンー。時代を創るのは、いつも大国だよ。」
「でも、話が面白くなってきましたね。やりましょうよ。」
「ああ、まるでSFだよ。」
「きっとそうなっていくんでしょうね。」
「もうひとつの話は、筋がまともすぎて、責任重大だよ。」
「情報社会の副作用ですか? そんなことってあるんでしょうか?」
「あると思うよ。ワードプロセッサーを使っていて、そう思うよ。」
「え?」
「たいていの人がローマ字入力しているだろう。」
「ええ。」
「日本の字の内のメインは漢字、それは【見る字】、一方のローマ字は【読む字】あるいは【話す字】だよ。」
「そう、いいますね。」
「だからローマ字入力のワードプロセッサーばかり使っていると、【読む字】中毒になるんじゃないか? つまり漢字が通じなくなる。」
「えっ? たとえば、」
「【暖簾】や【蕎麦】という字は読むものではなく、見て【のれん】とか【そば】とか、憶えておくものなんだろう。」
「それはそうですけど、」
「さらに、漢字は読むものではなく、見て、憶えていて、判断するものだという字があるだろう。たとえば、【後】は【ウシロ】【ノチ】【ゴ】と覚えていて、文章を読むときに前後を見て判断する。しかし、ローマ字式だと、そのときに読めるようにと【ushiro=後ろ】【nochi=後ち】と書くようになる。」
「そんな、バカな。【後ろ】【後ち】なんて日本語じゃありませんよ。」
「でも、そうなるよ。【気持】もそうだ。【キモツ】と読むのか、【キモチ】と読むのか、分からないから、読めるように【kimochi 気持ち】と書くようになる。ローマ字ばかり使っていると漢字は読むものではなく、見るものだという基本が、忘れられる。」
「だって、学校で習うでしょ。」
「だから、岩崎さんが言ってたように、学校で教える正しいことより、一般の誤解や間違いの方が早く広まる。」
「へえー。」
「戦後、日本がGHQの支配下にあったとき、マッカーサーが日本語を廃止してローマ字にしよう。そういう方法でもって日本人の思想改革をしようとしていたが、それを〝改悪〟とみないで、〝変化〟とみて、受け入れようとした日本人もいた。いまローマ字変換によって、それが亡霊のように蠢いているというわけだよ。ははは。」
「確かに。そういう点では、フリガナだって似たようなものですね。地面=ヂメンが正しいのに、ジメンになっちゃう。片付ける=カタヅケルなのに、カタズケルになっちゃう。」
「小田社長も同じことを言ってたよ。正しいことより、いいかげんな噂の方が速く伝わるってね。」
「僕も、小田社長でものの見方がすごいなって思いますよ。」
「おれも感心するよ。一番納得したのは、東大紛争のとき警視庁の機動隊が入っただろう。新聞・テレビでは『学問の府に警察が介入していいのか?』って一斉に叫んでいたけど、社長は『当たり前だよ。東大は官僚を作る大学。だからやっぱり最後の頼みは官僚なんだよ。』とケロッとしているんだ。これには驚いたよ。」
「なるほどね、そういう目で見るんですね。」
「そして、言われたよ。『それより、これから先は、マスコミが言うように学問の府への警察介入が一般的になるだろう。それこそ、東大と警察の思う壺だ。【大学学長連盟】みたいなものがあるのかどうか知らないけど、もしあるとしたら、そのことを東大へ申入れしておかなければならないのに怠慢だった。こうして、社会はこっちへ動くべきなのに、あっちの方へ動いてゆく。それが歴史だよ』ってね」
「すごいな、背筋がゾクゾクしてきますよ。で、野中さんも、歴史に強いじゃないですか。その眼では情報化医療はどうですか?」
「間違いなく、そうなるさ。時代は絶対高度テクノロジーへと進むものだから。」
「明快ですね。」
「そうさ。だから、古賀君は古賀君で開発を進めておいたら、」
「ええ。何とか検査数値がグラフ化できないかと、試しているんですよ。」
「そりゃいいじゃないか。」
「あと、レセプト(医療報酬明細書)のコンピューター化も避けられないと思いますよ。」
「それはレセプターみたいなものが、他の会社にあるだろう。そこに殴り込みをかけるというのにはウチは実績がなさすぎるよ。」
「そうかもしれませんが、それがないと市場がこっちを向いてくれないでしょう。」
「う~ん、それをやるかやらないかは、大問題だな。技術的にはどうなんだい?」
「難しくないけど、面倒ですね。」
「体力勝負か。」
「そうですね。」
「それから、うちの会社がそういう情報分野へ進出すべき、大義名分みたいなことを見つけ出さなければならないな。」野中の頭を過ったのは、塩分計を作ろうと思い付いたとき、町工場の社長から言われた「作る理由がきちんとしてなければ、ダメだ」という言葉だった。
「そっちの方は野中さん、お願いしますよ。」
「体力づくりは古賀、お化粧はおれかい。」
「小田社長もおっしゃってたじゃないですか。ホンダも、ソニーも名コンビで引っ張ってきたって。」
「あんがいお前は、夢も、意欲もあるんだな。」
「ははは。」
「とにかく、情報医療をやるには何か鍵がいるな。その鍵は何なんだろう?」
古賀と別れてから、野中は自分のアパートに寄った。1階の郵便受で郵便物を取ってから2階へ上がると、ちょうど隣の部屋の男が戸を開けて、出てきた。男は「オース」と声をかけて、何処かに出かけて行った。
部屋に入った健は、畳の部屋で大の字になった。 (このアパートでのおれは、「オース」と挨拶をされるていどだ。しかし、恵子のマンションでは管理人も洋子も丁重な挨拶をする。同じ野中健ではあるが、住んでいる所で違ってくる。) と妙なことに感心しながら、煙草に火を点け、寝っ転がったまま灰皿に手を伸ばして引き寄せた。
「ふ~、」煙が天井に消える。よく見ると、その天井は汚れている。やはり恵子のマンションとはかなり違う。
健にとっては自分の煎餅布団が寝やすいところはあった。(もしかして、恵子と知り合うことがなければ、絵美みたいな女とここで暮らしているかもしれない) と思わないでもなかったが、やはり健は恵子のことを忘れることはできなかった。 (だからといって、おれのような薄給の身で、これからも恵子と付合っていけるだろうか?)
(後輩の古賀にはもっともらしいことを言ったけれど、ああ、ア、おれもザマないな。安いアパートと高級マンションの間をウロウロしている自分は、今の仕事の状況と同じだ。)
健は、もう一本火を点けた。
数日前、恵子の後姿によく似た女性が先を歩いていた。健は (まさか) と思いながら脚を急がせ追い付いて、その女性を見たりしたが、やはり赤の他人だった。(ああ、恵子に会いたい。)「恵子!」思わず健は恵子の名を口にした。
恵子がNYに来て戸惑ったのは、デートの誘いらしきことが多いことだった。店内の人間、取引先の社員、お客、男たちは隙を見せれば、閑さえ見つければ、何やら彼やらと誘ってくる。これには閉口した。
恵子は日本にいるときは指輪をしなかったが、身を守るために填めることにした。しかし、そんな小さな嵐もお腹が目立つころになると治まったが、今度は周りの男性たちがやたらと親切にしてくれた。恵子はこれにも驚いた。道路を歩いているだけで、道を大きく空けてくれるし、ちょっとした段差があると手を差し延べてくれる。
日常を女性第一においているようなアメリカの男性というものが、恵子のような仕事をしていた者から見ると何か可笑しかった。
恵子が手伝うようになったのは、〔Lauren〕系のレディース専門のブティックだった。オーナーのエリザベス・ライアンは、恵子より10歳ぐらい年上だった。彼女は最初から恵子に親切で、時々食事にも誘ってくれた。
今日はミッドタウンにある洒落たイタリアン・レストランに二人はいた。
「ケイコ、お腹がだいぶ大きくなったわね。」
「順調ですって。それにつわりも軽いタイプのようで、よかったわ。」
「GYN病院なら大丈夫よ。医療技術も信頼できるわ。」
「ドクターもこの病院は絶対失敗しませんとハッキリおっしゃったの。」
その点は、(アメリカに来てよかったわ) と恵子はだんだん出産に自信をもつようになっていた。
恵子はNYに来るまで知らなかったが、GYN病院はVIPの患者が多いらしく、その名前を出しただけで、相手の恵子を見る目がちがってくるのが不思議だった。それも医療費の高いアメリカらしく、日本では考えられないことだった。
「ケイコ。赤ちゃんは、一人で育てていくつもり?」
「・・・、」恵子はテーブルの上にあった水を一口飲んで、言った。「わたしは35歳、だからお産に自信がなかったの。けれど、アメリカに来てから自信をもったわ。無事に産むことができるような気がしてきたの。だから産んだら、日本にいる恋人にプロポーズするつもり。でも、彼がオーケーしてくれるかどうかが心配なの、」
「ベイビーの父親ね。」
恵子は肯いた。
「ケイコからプロポーズ? それもいいわね。でも、なぜ心配?」
「赤ちゃんができたことを彼に言ってないの。彼と離れたくないという気持があったから、どうしても言えなかったの。だからそれを知ったら、彼は怒るかもしれない。」思わず恵子は瞼に涙を浮かべた。
エリザベスは立ち上がって、恵子の隣に座って、恵子の肩を抱きしめた。
「ケイコ、大丈夫。あなたが彼を愛していることを彼は分かってくれるわ。きっと、うまくいくわ。」
そのとき次の料理が運ばれてきたので、エリザベスは自分の席に戻って、言った。「少し食べなさい。」
恵子は病院で「赤ちゃんに栄養を回すために、食べなきゃダメ」と言われたのを思い出し、野菜と魚に手を付けた。
「彼の名前は?」
「野中健!」
「ケンは、どういう人?」
「誠実な人よ、」
エリザベスは何度も頷く。その度に美しい金髪が揺れる。そして懐かしそうに言う。「ジローもそうだった。そういえば、ジローには家族は何人いるのか、知ってる?」と尋ねてきた。
「ジロー?」
「タチバナよ」
(あ、そうか。エリザベスを紹介してくれたアパレル・メーカーの部長橘慶二郎さんのことなのね、) と分かったが、ただ恵子は店のお客としての橘しか知らなかった。信頼できそうな人で、アメリカにいたことがあると聞いていたから、紹介を頼んだのだが、家族のことまでは知らなかった。だから、「仕事での知合いだから、家族のことは分からない」と答えた。
エリザベスはウンウンと肯いたが、その目に遠くを懐かしむような眼差しがあった。エリザベスはワイングラスを傾けてから、「日本人は若く見えるわね。ケイコは20代かと思った。ジローも若く見えたわ。昔のことだけど、わたしとジローは愛し合っていたのよ。もう20年も経つわ、」と言った。
恵子は驚きながらも、橘の顔を思い描いてみた。忘れかけていたが、誠実な感じの50代半ばの紳士であった。恵子は理由もなく、健も20年30年経ったら、ああいう感じの紳士になるのかもしれないと想った。
「わたしの親も、ジローの親も、古い家だから、外国人との結婚を許してくれなかったの。アメリカと日本の戦争が終わってから、まだ15年しか経ってなかったからね。わたしたちは別れたけれど、ジローには感謝している。若いころに遠い異国を想うこともできたし、わたしの世界が広がったわ。」
「・・・・・・。」
「それから、今の夫を知って、愛し合うようになり、結婚したの。もちろん夫や子供たちは私のこと愛してくれているし、私も夫や子供たちを愛しているわよ。」
「そうだったの。」
「だから、わたしは日本人が好き、ケイコも好き。ケイコはおとなしそうに見えるけど、わたしより強いわね。一人でNYへやって来て、一人でお産をしようという。きっと貴女はやりとげる人よ。わたしはケイコを応援するわ。だから何でも言って。」
「ありがとう。でしたら、ファッション業界の色んな方をご紹介してほしいわ。話を聞きたいの。」
エリザベスは両手を広げて言った。「オーケーよ。ジローのおかげでケイコとわたしは友達になった。夫がよく言ってるわ。何ができるかではなく、誰を知っているかが大事だって、」
「たしかにね。」恵子も微笑みながら応えた。
恵子はアパートメントに戻った。独りでいると「恵子!」と時々健の呼ぶ声が聞こえてきてハッとすることがあるが、気のせいだと気付いて苦笑する。
アメリカ人は別として、「恵子」と呼び捨てにするのは健が初めてであった。両親も、近所の人も、親類も、子供のころは「恵子ちゃん」と呼んでいた。そして大人になってからは「恵子さん」ばかりであった。それが健は、恋人関係になってから「恵子」と呼んだのに、恵子はまるで抵抗感がなかった。むしろ今の恵子は、無償に「恵子」と呼ばれたい気持に縛られていた。
恵子は服を脱いでバスに入った。そして身を沈めながら、思った。
(さっき、エリザベスは「強い」と言ってくれたけど、そうだろうか? もしそうだとしたら、あの事件以来、耐える力は身に付いたように自分でも思う。でも、健を愛するようになってから、泣き虫になったのも事実だわ。)
恵子はバスから上がって、テレビを点けた。
ヘレン・メリルが歌っている。どこかでのショーの録画のようだった。
恵子はソファに座った。
ヘレンが「Lilac Wine ♪」を歌い始めた。
https://www.youtube.com/watch?v=EejJVj_KXGc
まだ健と恋人どうしではなかったころ、恵子は「ジャズは一人で聞くのが好き」と言ったことがあった。でも今は違う。この「Lilac Wine ♪」みたいな曲は、あの人に抱かれながら聞きたい、そう思った。恵子はお腹を擦りながら立上がり、机の方へ行って、引出から一週間前の健からの手紙を取り出し、またソファに座った。そして読み返してから手紙を胸に抱いた。
野中と古賀は毎日、一日中、社内でも外でも打合せをしていた。その結果、早く「情報医療チーム」を立ち上げよう! と話し合った。
二人が目指す情報医療とは、パーソナルコンピューターを医療用として利用するということであった。その医療情報は、①検査データのグラフ化すること、②レセプト(医療報酬明細書)をパーソナルコンピューターで処理すること、だった。
野中は、情報医療というシステムを診療現場に導入した場合、どのような事態になるかを知るために、営業時代のお得意先を訪ねてみた。
田中整形外科、中村病院、齋藤医長クリニック、大村病院など・・・・・・。お得意先の皆さんは、野中のことを懐かしがってくれた。大村病院の院長と陣内副院長は「おい、また旨いものでも食いに行こう。今度はおごってやるぞ」と相変わらずだった。
ただ、女性の方は変化があった。中村病院の高橋薬局長は結婚して、小森と姓が変わっていたが、応対が前とちがって律儀そうな態度になっていた。また齋藤医長クリニックの京子先生は、噂通り婿養子を迎え、ご主人は副院長、京子先生は薬局長の席はそのままだったが、一週間に一度ぐらい顔を出すだけで、薬局の仕事は若い薬剤師さんに任していた。
野中が「前に担当していた者」だと言うと、電話をしてくれて「奥様がお会いになるそうです」と言う。野中はクリニックの隣の自宅を訪ねた。久しぶりに会ってみると、京子先生は明るさとゆとりのある奥様然となっていた。紅茶とケーキを頂きながら一時間ほど取留もない話をしてから、「また遊びに来て頂戴」という言葉に送られて辞したが、野中は (以前の京子先生とは別人のようだ) と驚きながらも可笑しかった。
ところで、肝心の情報医療システムであるが、全ての医師が「忙しいのに、パーソナルコンピューターを操作している時間はない。無理だ。」「検査データをいちいち入力するなんて、バカげている。紙に印刷してある数値を見ながら、説明すればいい。」と反応が芳しくなかった。言葉を替えると、皆さんは共に、face to face を大事にされていた。
野中は、(大病院なら、どうだろう?) と思い、東京キリスト大学病院と東京国際総合病院も訪ねた。
すると、山田教授も、河村部長も「〝インフォームド・コンセント〟か」と呟いた。
「えっ! 〝インフォームド・コンセント〟って何ですか?」
「日本の医療には概念がないから、訳せないが、敢えて言えば、〝説明と同意〟かな? アメリカあたりでは、そういうが、契約社会だから成立つ。日本では定着しないだろう。」
野中は、山田医師の話すことの意味がよく理解できなかったが、(さすが、大病院の医師は新しい動きも知っているんだな) とだけ思った。
「それよりか、恵子ママは辞めて、徳子が店をやっているけど、野中君は行ってるかい」と山田医師が言った。
野中は慌てた。「いえいえ、今の部署はそういう所とは全く縁がありませんから。」
野中は玄関を出た。車のドアを開けてキーを回した。そしてハンドルを握りながら、恵子のことを想った。(今ごろ、どうしてるんだろう?) 車を動かしていると、いつのまにか晴海に着いていた。
野中は車を停めた。自動販売機があった。野中は下りて、お金を入れて〔ポカリ〕を手にした。野中は缶を開けて、飲んだ。缶の縁に恵子の口紅が付いているような錯覚がした。
野中は煙草を取り出した。思えば、恵子を初めて見染めたのは、店でサックスの「アルフィー♪」が流れているときだった。恵子を見て、(何と、きれいな女性だ) と思った。
その次は〔バッハ〕でペギー・リーが「ブラック・コーヒー♪」を歌っているときだった。恵子は「ジャズは一人で聞くのが好き」と粋なことを言った。野中はだんだん恵子に魅かれてゆく自分が分かった。そしてとうとうここで泣き崩れる恵子を抱きしめた。そのときは「愛しい女」だと思った。それから恵子との夢のような日々が始まった。恵子は優しい女だった。おれは幸せ者だと思った。しかし、こうして離れていると、いま直ぐにでも会いたくて仕方がない。
健はカーラジオのスイッチを押した。ヘレン・メリルの「Beautiful Love♪」が流れてきた。
https://www.youtube.com/watch?v=EM2YKTmGHBQ
「恵子に会いたい。」健はラジオを聞きながら、独り言を吐いた。
NYダウンタウンのチャイニーズ・レストランだった。料理は美味しいと評判の店だったが、惜しいことにすこし乱雑だと皆が言っていたが、その通りだった。
恵子とエリザベスは「ファッションのバイブル」といわれる雑誌『NY』のエディター、ダイアナ・コールを迎えて、ディナーを楽しんでいた。エリザベスは恵子からファッシン界のいろんな人の話を聞きたいと頼まれていたので、「時々、食事をしながら話を聞く会をやろう」と言ってくれた。
ダイアナは絹のような銀髪が美しい50歳の独身女性、サングラスが良く似合っていた。20代のころダイアナは、ファッション・モデルをやっていたが、30歳になって出版社に入り、今は『NY』の編集長の、「片腕の一人」と呼ばれるまでになった。
ダイアナは言った。「わたしはファション界が好きだし、いつも『最高の一冊 = 最高の作品』を作ろうと思って編集している。その情熱は人一倍もっているつもりだし、わたしの人生そのものがファッションだと思っている。でも、編集長にはなれない。わたしのボスである編集長にはわたしにないものがある。」
ダイアナは恵子を指さして言う。「ケイコ、分かる?」
エリザベスは答を知っているから、黙って頷いている。
「彼は、常に社会の一歩前を歩く、ファション界のリーダーよ。いやそれ以上に美の教会の司祭なの。それがわたしにはない。」
「・・・・・・。」
「フフフ。ケイコ、一度わたしのオフィスに来なさい。『女の夢の園』を見せてあげるわ。オートクチュール、プレタポルテ、アンダーウエア、メイク、シューズ、バッグ、帽子、宝石、香水・・・、イザ出撃というときのために何でも揃っているし、一流のデサイナー、コーディネーター、プランナー、ディレクター、カメラマンが行き交っている。それでもボスは満足しない。いつも一歩先を見ているからよ。」
ダイアナは誰が見ても颯爽としてカッコイイ。それでも自分の足りないところをちゃんと知っている。恵子は感心した。
食事が済んでから、「サンキュー」と三人は握手して別れた。
恵子は、昔の恋人を紹介してくれた橘に心から感謝した。普通だったら、そこまではしないだろう。そういう彼の誠意がエリザベスにも伝わったからこそ、彼女もまた誠意をもって私の面倒を見てくれる。そう思うと、嬉しくなってきた。
それにダイアナの真剣な話も面白かった。これまでのような酒の席は所詮遊びだから仕方がないとはいえ、お店では自慢話、悪口、冗談だけが渦巻いていた。だから、恵子にとって今日のような席はとても新鮮だった。
恵子は自分のアパートメントに戻った。
(今日みたいな話、彼と一緒に聞いていたら、きっとあの人は何かサゼッションをくれただろう。) そんなことを考えなから、郵便箱を見ると、健からと桃子姐さんからの手紙が入っていた。
健の手紙はベッドに入ってゆっくり読むつもりで、先に桃子の手紙の封をペーパーナイフで切った。開けると、「一人の生活は寂しいだろうから、近々陣中見舞いにNYへ行ってあげる」と書いてあった。
(XVへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕