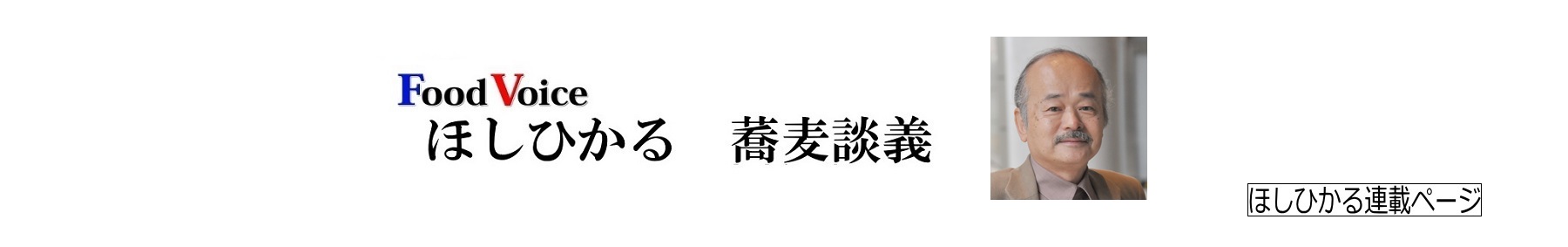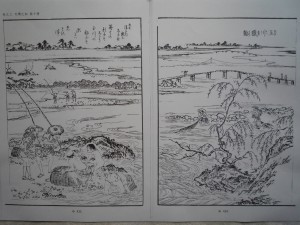第180話 一月二十日 鈴木家 日待の料理
《 蕎麦膳 》九
武蔵国多摩郡柴崎村は現在の立川市の一部、江戸ソバリエ・ルシック講師のT先生が勤務されている地区であるが、話は徳川12代将軍家慶の御世にさかのぼる。
天保11年(1840年)1月5日のことだった。風が多少あったが、見上げる空は晴れていた。この日、柴崎村の年番名主鈴木平九郎重国(1807年生)ら18名はお伊勢参りへ旅立つため、駕に乗った。講の仲間は前々年から旅費を積んでいたが、農閑期になって籤引きで代表者を決めて出立するのであった。残った村人たちは一行の出立を見送ろうと集まってきた。中でも家族の者や親しい者は、後についていった。多摩川の渡まで来ると、さらに見物人が増えて賑わった。平九郎たちは満起銭(撒銭)をして、日野の渡りを渡った。これも儀式のひとつであった。彼らは八王子に着いて昼食をとり、相州橋本まで来ると、そこで見送りの人たちと別れて最初の宿場厚木へと向かっていった。
多摩郡の柴崎という村は甲州道中日野宿の助郷(宿の夫役を応援する近隣の村)であった。また八王子千人同心の扶持米を負担し、一方では江戸城への御用鮎を献上するという栄にも浴していた。村は昔、組頭の中から交替で名主を選出するという年番制をとっていたが、1787年以降は鈴木家と中嶋家が交替で名主を勤めるようになっていた。
中嶋家の10代目次郎兵衛(屋号「大北」)は日野寄場組合44ケ村の惣代であり、多摩一帯の実力者であったが、そこの次男平九郎が鈴木家の養子に入っていた。
鈴木平九郎は1834年に平村(日野市)の名主平魯輔の娘嘉代(1815年生)を嫁にもらい、寅吉(1821年生)、健次郎(1839年生)の二人の息子をもうけていた。
夫平九郎(33歳)が伊勢参りに出かけている間、鈴木家の留守は妻の嘉代(25歳)と、二人の息子と、下男清次郎、下女サヨらが守った。
だから、夫は4月まで留守である。この間の、年賀の客、留守見舞客の応対は妻がこなした。嘉代は娘時代、越後村上藩の永田馬場南行当(千代田区永田町)の上屋敷で、19代藩主内藤紀伊守信親の奥方に奉公していた。それゆえに、嘉代は高い教養と、江戸との人脈をも持つ、賢妻であった。
年始客の中島家の母には魴鮄の塩焼と酒、井桁屋御内室には吸物と酒、白鳥家御内室には生売茶飯と酒で接待した。
また留守見舞客の椱戸、八兵衛、巴屋は赤飯、要吉は豆腐二丁、菊隠居は草餅二重、実家の中島からは鮃一枚が届いた。皆、村の豪農であった。
こうした日常の記録は、平九郎が記していた「公私日記」に残っているが、夫の留守中「日記」は嘉代が代筆した。
伊勢までは片道15日、1月20日が夫平九郎の宮詣のころと思われた。そこで妻の嘉代は、たとえ身は武蔵国に居ようとも、気持のうえでは共に詣でるのが妻の務めと考え、自宅に客を呼んで日待を催した。「日待」というのは「日祭」が訛った言葉であり、かつ「待つ」という受け身上の幸字を当てたものと筆者は推定している。
《呼客》は次の9名であった。
中島家の母、井桁屋、綿屋、伊右衛門、甚右衛門、民五郎、留吉、忠兵衛、斧治郎。
《料理》
吸物ー鱈 コンブ 二ノ吸物ー白味噌 豆腐 蛤 酒肴ーのりすし 鰤味噌漬
本膳蕎麦 鐺焼ー麩 たこ はす クワイ 長いも
料理を見てみると、先ずは昆布出汁のお吸物、続いて白味噌の汁とお酒、それに海苔寿司と鰤の味噌漬、そして蕎麦切、鐺焼が供されている。
鐺焼というのは鍋焼と理解していいだろう。そうだとしたとき、焼く料理かと思いきや、わが国では近年まで焼く料理と煮る料理の概念は明確ではなかった。たとえば「鍋焼うどん」といっても煮たうどんである。となると、鐺焼とは麩、たこ、はす、クワイ、長いもを煮た物であろう。
見渡せば、江戸の町の庶民の間では、すでに蕎麦切、鰻、天麩羅、握り鮨といった単品料理が発達していたが、鈴木家では正式な〔肴+酒〕料理を食し、そうした伝統的な膳で蕎麦切を楽しんだようである。これが多摩郡の豪農の風習なのか、あるいは江戸武家屋敷に奉公していた嘉代の教養からくるのかは判らない。
考えてみれば、江戸の単品料理というのは世界でも珍しい。日本では江戸時代以前、あるいは近畿および西日本、そして世界でも中国料理などは〔肴+酒〕料理、今でいうコース料理が正餐である。もともと「献立」という言葉は肴を整えることを指すぐらいであるが、江戸の町のみ特異的に単品料理が発展していった。これを世間では、よく「江戸のファストフード」と言う人がいるが、それは短慮な人が言うことだと思う。そもそもファストフードというのは何処でも同じ味という歪な食べ物を指すが、そんなものと歴史ある江戸の料理を同じ卓にならべるのは、蕎麦切、鰻、天麩羅、握り鮨に対して失礼というものだろう。そうではなくて、江戸の単品料理は、わが国の料理史上、金をもらわない家庭料理から初めて金がもらえる店料理へと脱皮、近代化したものと考えるべきであろう。
余談であるが、『南総里見八犬伝』の作者滝沢馬琴は最初に原稿料で生計を立てた作家であるとされている。同様に、単品料理ではあったが蕎麦切、鰻、天麩羅、握り鮨を商品として世に出した人たちが江戸の料理職人だったのである。
それからもうひとつ。日待の膳も、留守見舞客への接待も、酒が出ているが、それは【食中酒】であって、明治以降の【酒主肴従】ではないことがうかがえる。明治維新というのは食文化からいっても激変をもたらしたことはよくいわれるが、酒の流儀も然りであった。都市の食文化を知らない片田舎の下級武士出身の獅子たちが、酒だけを呑むという田舎流を新都で蔓延させ、やがてその流儀が軍隊へ引き継がれて以来、約140年間の日本は「男の酒」的な【酒主肴従】になったのであるが、それまでの長い時代は【食中酒】という食文化の中にあったのである。
話を史料に戻すと、村のどの家かの留守を見舞ったり、その留守宅では主人の代わりに家内がしっかり留守を守っているのを見ると、一族で家を守り、地域ぐるみで地域を護っていたこの時代の人々の日常が見えてくるかのようだ。そうしたときのハレの食というのは、その潤活剤であったのかもしれない。
のち、鈴木平九郎は多摩川上ケ鮎御用世話役、日野宿助郷37ケ村日〆惣代、日野宿組合44ケ村惣代を勤めたという。
加えれば、この項とは関係ないかもしれないが、同じ多摩郡の石田村(日野市)で生まれた土方歳三は5歳になっていた。それが後に新選組の鬼の副長として活躍しようとは、平九郎はむろんのこと当時の村人は誰も想像していなかった!
参考:「公私日記」(ただし、稲沢先生から頂いた「日待」の箇所のコピー資料)、『江戸名所図会』(ちくま文庫)、瀬川清子『食生活の歴史』(講談社学術文庫)、
《 蕎麦膳 》シリーズ(第180、176、171、170、166、157、154、153、150話、)
〔江戸ソバリエ認定委員長、伝統江戸蕎麦料理編集委員 ☆ ほしひかる〕