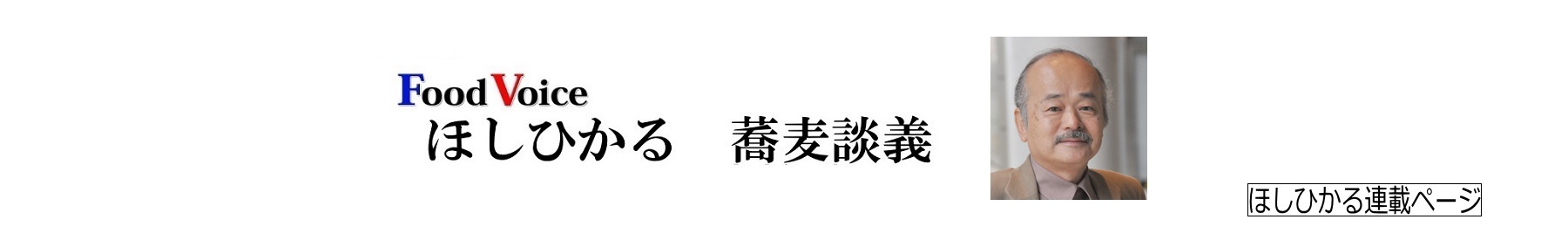第185話 無国籍な蕎麦
2025/12/06
最近「つけ蕎麦」という文字や看板を目にするので、モノは試しと入ってみた。一言でいえば、ラーメンの汁の中に蕎麦を入れたようなものである。たぶん大勝軒が始めた「つけ麺」の「麺」が転じて「蕎麦」になったのだろう。
確かに「つけ蕎麦」という言葉は新しいが、蕎麦を汁につけるという食行為は伝統的なもので、われわれ日本人は昔から、麺(《ざる蕎麦》も)を汁につけて食べていた。だから、その蕎麦汁を「つけ汁」という。一方の《かけ蕎麦》などの汁は「かけ汁」と呼んでいる。
先ほど、「ラーメンの汁」と言ってしまったが、店によっては、中華風、イタリア風、和風の汁とあるようだ。それに、いずれの汁も香辛料と肉の存在が大きく、総じてコッテリ系である。その点がこれまでの「お蕎麦」とは世界観を別にしている。
わが国では食の思想家といわれる道元が「六味 ― 苦い・酢い・辛い・塩からい・甘い・淡い」ということを述べて以来、和食はあっさり、きれいが基本となった。
そのため、和食では香辛料(山葵、唐辛子、辛子、山椒) は単数、小量しか使わない。だが、中華系は複数を組み合わせ、多量に使用する。その中華の流れを現在のつけ蕎麦屋は汲んでいる。肉にしても江戸時代の1824年ごろから鴨南蛮が顔を出しているが、つけ蕎麦屋のそれはちょっと重めの豚、猪、牛である。
ま、こうした香辛料と肉汁に蕎麦をつけて食べるから「つけ蕎麦」というのだろう。
香辛料といえば余談になるが、以前に『タッチ・オブ・スパイス』という素晴らしいギリシャ映画があった。その映画がいいたかったことは、「人生は料理と同じ。深みを出すのは一摘みのスパイス」といったところだろう。しかし、物語の中で一番印象的だったのは、父親が流す一筋の涙だった。キプロス問題(民族・宗教・領土問題)で揺れるギリシャとトルコ。その渦中で人生を翻弄された一市民の一筋の涙 ― これが本当のスパイスだったのである。
こうした映画を観ていると、日本、中国、欧米とでは香辛料文化がまったく異なることを思い知らされる。日本では香辛料より、重視するのは「出汁=旨味」である。出汁が効いているか、いないかで、和食の成否が決まる。
わが国の蕎麦切は室町時代に登場したが、最初は膳料理の最後に出る献立の一つだった。それを「後段」というが、江戸初期にわが国でも食堂が営業されるようになると後段から独立した蕎麦が蕎麦屋として営まれるようになった。その蕎麦が進歩・発展し、江戸の中期以降のころには「旨味があって、キレのあるつゆ(出汁+かえし)」と「コシがあって、喉越しのいい蕎麦(もちろん手打ち)」が、粋な江戸蕎麦として迎えられた。
その後1800年代から、かけ蕎麦、田舎蕎麦、鴨南蛮なるものが顔を出し、さらに明治末から大正時代にかけて機械打麺が登場し、蕎麦の裾野は広がっていった。それでもこれらは汁の旨味は守っていた。
ところが現代では、第三の蕎麦が台頭しつつあるというわけだが、それらは汁の旨味より、香辛料や肉の味覚に比重がおかれている。だから私は「無国籍な蕎麦」と呼ぶのである。
しかし、それもいいだろう。若い人が望むなら、第一の江戸蕎麦、第二の蕎麦に続く、第三の無国籍蕎麦も、おおいに結構ではないか!
ピラミッド構造は大きいほどいい。日本の蕎麦文化、いやアジア麺文化のために。
参考:『週刊プレイボーイ』No.9, 2013 (集英社)、タンス・ブルメティス監督『タッチ・オブ・スパイス』(2003年)、
〔江戸ソバリエ認定委員長、エッセイスト ☆ ほしひかる〕