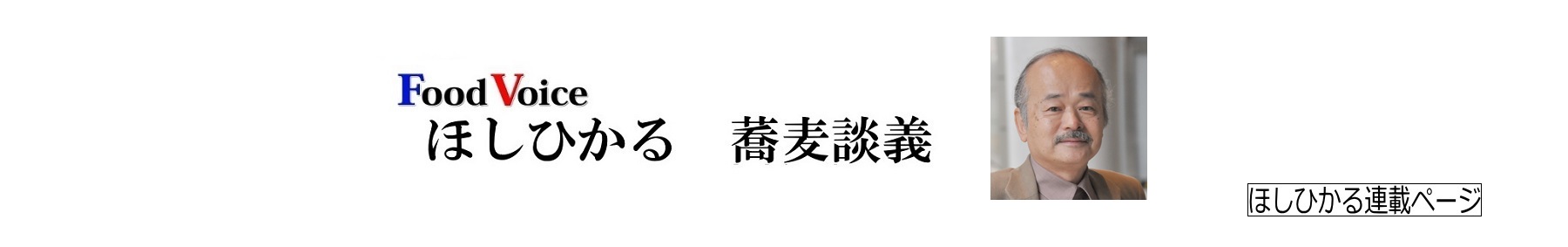第639話 草上の昼食のマネ
2025/12/06
ソバリエの伊嶋實さんは「墨線画家」と名乗っておられた。線を主して絵を描かれるからだ。もともと日本は線画が多い。マンガ・アニメもそこから発展した。
絵が下手な私は、線画だと幼稚になるから、モノを物体として捉え、線は描かない。何ども色を塗り重ねる手法をとっている。その割にはソバリエの加藤正和さんのように上手に影を描けないから、影なしの物体になる。とすると非現実的な変な絵になるが、それが私の絵である。
ところで、エドゥワール・マネ(1832-83)の「草上の昼食」(1863年)という面白い絵がある。
ここのところ時間に余裕があるので、倣って私も描いてみた。ただし、それをモチーフとした抽象画である。これだと下手なところがごまかせるからだ。しかし抽象というのは楽しい。私の場合、抽象というのは「要約」と理解しているからである。
たとえば、蕎麦の種の撒き方、刈り方、蕎麦の打ち方、蕎麦の食べ方にも重要な基本原則と、人それぞれからくる端々の事がある。それを選別して要約する作業が抽象化に似ている。だから、抽象化を考えることは楽しい。
さて、絵に描かれているのは男女4名。そしてこれを描いたマネの5名で草上の昼食をとったのだろう。草の上には籠が倒れて果物が散乱し、飲み干した大きな酒瓶が転がっている。
ただ他の者たちは衣服を着ているというのに、一人の女性だけ裸である。だからどうしてもそちらへ視線がいくが、それが分っていたのか、彼女は絵を観る者をじっと見返してくる。
人間が描かれている絵を観るとき、マンガの吹き出しのようにセリフを入れるつもりで見るといい。たとえばこの女性は何と言っているか、男たちは何を語っているのだろうかを想像すると絵の観賞が楽しく深くなってくると思う。
この絵の場合「なぜ私が裸なのか知りたいの?」とか何とか言ってるのだろうか。
じゃ、その解答を考えてみよう。
裸の女はヴィクトリーヌ・ルイーズ・ムーラン(1844-1885)という21歳のパリジェンヌ。ヴィクトリーヌとマネが初めて出会ったのはパリの大法院前の路上だという。このときヴィクトリーヌはまだ18歳だった。彼女の不思議な風貌と意思の強い雰囲気に心を打たれマネは、すぐモデルになってほしいと頼み込み、昨年は「ヴィクトリーヌ・ムーラン」を描き、今年はこの「草上の昼食」と「オランピア」を描いた。男性のうちの真ン中の若者はオランダ人の彫刻家フェルディナン・レーンホフ、マネの妻シュザンヌ・レーンホフの兄である。そして横向きの人物はエドゥワール・マネの弟ウジェーヌ・マネである。向こうで水浴をしている女は誰だろう? マネの妻だろうか! それとも弟の妻の女流画家ベルト・モリゾだろうか!
マネは、ヴィクトリーヌや、妻や、弟の妻の三人の女性をモデルにして度々絵を描いている。それらから兄弟夫婦、かなり仲のいい家族だったことがうかがえる。
ところが、この絵を観た現代の女性が「ピクニックの昼食時に裸になる必要などまったくない。どうして男どもは裸の女性を描きたがるのか」と怒るという。実は、その反応ぶりは19世紀の人々もそうであった。だからマネの「草上の昼食」は酷評されて展覧会に落選した。それというのも、19世紀までの画壇は神は裸だが、一般の人間は衣服を着ているもので、裸は身分の卑しい者しかならないというのが決め事であった。だからマネはそういう「世間の決め事」に挑戦した。ではどこで女神と一般女性の区別がつくかというと、神は最初から裸体であるが、衣服を脱ぎ捨てているのは人間の証拠だという。だからこの絵のポイントは草の上に脱ぎ捨てられた衣服と、それを際立たせる男性の正装と、モネの気持を込めたムーランの挑むような視線である。
これが答えである。
それから以後、マネの進取性に感銘した画家たちはたくさんの「草上の昼食」を描いた。たとえば、ウジェーヌ・ブータンは、それを描くために、マネの「草上の昼食」でモデルになったエドゥワール・マネの弟ウジェーヌ・マネに来てもらい、わざわざ同じポーズを取ってもらって描いた。またマネの大ファンであったジェームス・ティソも、ポール・セザンヌ も、マネと対立していたステュアートさえも、そして弟ウジェーヌ・マネの妻ベルト・モリゾも描いた。さらにピカソにいたっては何枚何枚も「草上の昼食」を描いた。
かくて現在、ヌード画は一般的となったのである。
私の拙い絵は、「草上」だから緑色で、「昼食」も忘れずに、裸の女だけ白で、そして脱ぎ捨てた衣服・・・これが人間である証拠なんだが、それをピンクで四角に描くことにした。
〔文・絵 ☆ エッセイスト ほしひかる〕