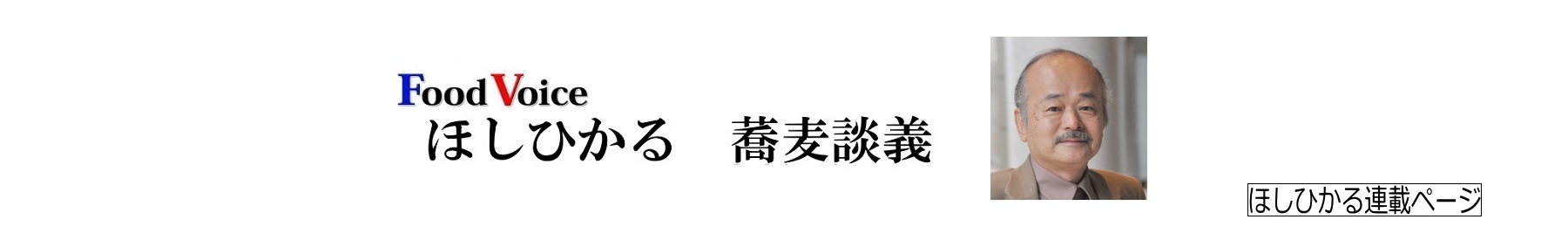第683話 最後の晩餐のブリニ
2025/12/06
『世界蕎麦文学全集』物語25
☆マリー・アントワネットの最後の食事
ヨーロッパ編は一旦終わるので、それにふさわしく今回は『最後の晩餐』とした。
しかしこの題名には、あのダ・ヴィンチが絵画にして遺しているためか、人間の荘厳な思いが込められているような気がする。だから物を書く人は一度は挑んでみたいテーマであるのかもしれないが、ただ残念ながらダ・ヴィンチを越える作品を私は知らない。
それでも、人間には当然最後の晩餐がある。その一つであるマリー・アントワネットの最後の食事は哀れである。
フランス王国の宴の型はヴァロア王家のカテリーナ・メディシスによって始まったことは第681話で述べた。
それに続くブルボン王家も前王家の宴の形式を引継いだ。そのことによって正当なフランス王であることを主張したかったのである。ブルボン王家は太陽王ルイ14世、グルメ王15世と続き、そして最後の王朝ルイ16世とマリー・アントワネット妃の代に市民革命が起きた。1793年、王と王妃は処刑された。その日のマリー・アントワネットの最後の食事は《ブイヨン》だけだったという。
この革命時、ブルボン朝の支流であるシャンティ城コンデ公ルイ5世ジョセフは国外へ逃亡。やむなく厨房長であったロペールは城を出て、パリのリシュリュー街でレストランを開業した。これがフランスのレストランの第1号である。
このことを申上げるためにマリー・アントワネットの《ブイヨン》を引合いに出したわけである。つまり
Ⅰ.カテリーナメディシス王妃 ⇒
Ⅱ.ブルボン王家 ⇒
Ⅲ.レストラン「ロペール」の開店後、料理人たちは市民たちに新しい料理を供するためにソースを大きく発展させ、
その結果としてフランス料理が〝世界の料理〟となったことをわれわれはヨーロッパの料理史としておさえておく必要があると思う。
☆『最後の晩餐の作り方』
さて、手元に『最後の晩餐の作り方』という小説がある。ジョン・ランチェスターというイギリスのフードライターが書いた料理小説であるが、イギリスの料理の話ではない。
よく、イギリスの料理はおいくないという。昔はおいしかったが、19世紀の産業革命後からまずくなっという。その理由を白井聡は、産業革命によって農村共同体が崩壊し、「村」や「祭」の文化を失ったところに、新富裕層は外国人のシェフを雇って外国料理を堪能し、イギリス独自の料理文化を育てなかったからだと指摘している。
しかし笑ってはいけない。日本も明治・大正・昭和も同じことをやってきた。和食を蔑視し、洋食を高級食として崇めてきた。
そんなわけだが、作者がイギリス料理を取り上げらけなかったのもそのせいかもしれない。だから書かれた内容はヨーロッパ全体の食である。ヨーロッパ編のまとめとしてここで取り上げた。
ところが、この小説の原題は『The Debt to Pleasure』というらしい。それを訳者が『最後の晩餐の作り方』という題名にした。訳者はこれがふさわしいと考えたのだろう。私も、その「最後の晩餐・・・」という言葉に魅かれて手に取った次第である。
頁を開くと、いきなりこうだ。
~ この世に数多く実在する小麦粉、卵、牛乳もしくは水の混合物すなわちパンケーキ、ワッフルの類 ー クレープ、ガレット、スウェーデンのクルムカークル、ソッケシュトゥルーヴル、ブレッタル、フィンランドのタッタリブリーニット、北欧諸国で広く食べられているエッグヴォッフラ、イタリアのブリジディーニ、ベルギーのゴーフレット、ポーランドのナレシニク、ヨークシャー・プディング ー のなかで私自身がいちばん好きなのは《ブリニ》であります。
幸せなパンケーキ一家の一員である《ブリニ》の特徴は(薄焼きではなく)厚みがあり、形は(二つ折や三つ折にせず)丸いままで、膨らませるのに(ベーキングパウダーではなく)イーストを使い、ロシア生まれで、しかもブルターニュ地方のパンケーキのように(ふつうの小麦粉ではなく)蕎麦粉でできている点とあり、《ブリニ》の作り方が書いてある。
私は先ず、蕎麦粉の《ブリニ》に目を奪われ、そして、パンケーキ、ワッフルの類 ー クレープ、ガレットに目が移ったが、他の物はさっぱりわからない。
少し話はそれるが、来日してまもない中国人から「〝ごはん〟と〝メシ〟が同じだということを最近やっと分かった」と言われたことがある。当国の人にとって当たり前のことでも、外国人から見れば、こんがらかってなかなか整理できないことがある。
しかし、こうやってズラリと羅列されると、673話や674話で混乱していたパンケーキ、クレープ、ガレットが何となく整理できて、やっとヨーロッパの菓子の世界が見えてきたような気がしてきた。
つまりは和菓子に生菓子と干菓子があるように、洋菓子にも生菓子と干菓子があって、その生菓子のうちの【焼菓子】が、それらなんだ。そしてその材料が、小麦粉や蕎麦粉やトウモロコシの粉だったりするのだ、と。
それにしても、この小説は読みにくい。それは日本の小説の省く文体とはちがって、英語の饒舌な文体そのものだからである。いわば説明が多くて、知識満杯・・・。
たとえば、この小説を書いた理由はこうだ。
~ ひとつのメニューがたとえば文化人類学的に文化を語ることもあれば、心理学的に個に迫るときもあるし、それ自体、伝記にも文化史にも、特殊な語彙を集めた用語集にもなりうる。考えだしてた人間、味わう人間の社会学的、心理学的、生物学的背景はいうに及ばず地理的状況の証ともなりうるメニュー。メニューは知識への扉であり、途であり、インスピレーションであり、道であり、秩序だてであり、形作るみとであり・・・・・・・ ~ と1ページぐらい述べてある。
私だったら、「ひとつのメニューがたとえば文化人類学的に文化を語る」ぐらいまでしか書けないだろう。
ところで、日本の場合、コース料理のようなときは【お献立表】といい、一品一品の価格を書いてあるものを【お品書き】というが、ジョン・ランチェスターがいう【メニュー】は日本の【献立表】に当たるのだろう。
『世界蕎麦文学全集』
50.ジョン・ランチェスター『最後の晩餐の作り方』
* レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』
* 白井聡『武器としての「資本論」』
文:江戸ソバリエ認定委員長 ほし☆ひかる
「最後の晩餐」(レブリカ):ほし所蔵