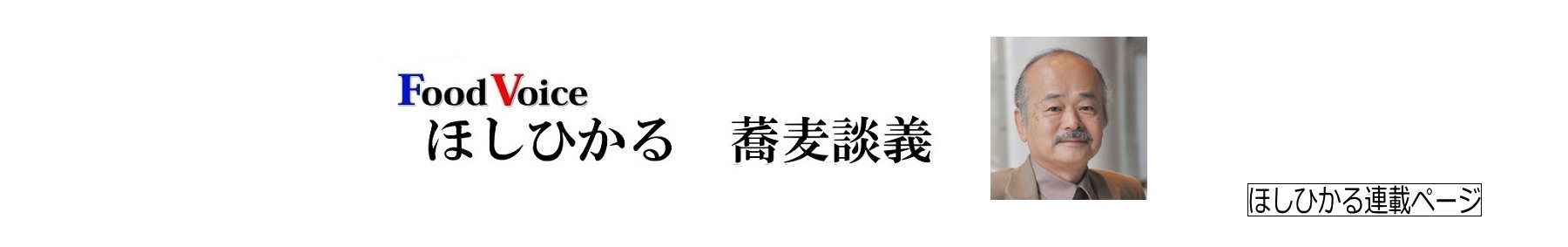第727話「ねじれ花」
2025/12/06
~ 松本清張と深大寺 ~
社会派推理小説という分野を開発した作家松本清張(1909~92)の話です。
清張は膨大な数の作品を残し、いまでも『黒革の手帳』などが何度もテレビドラマ化されていますから、皆様もご存知だと思います。
清張小説の特色の一つとして〝悪い女〟が登場します。しかも美貌ときていますから、映像向きかもしれません。これからご紹介する『波の塔』もそうです。ただ、この『波の塔』は清張物としては珍しく「ラブ・ミステリー」ともいうべき分野です。それも若い女性向けの『女性自身』に連載された小説だからでしょうか。
そんな小説をなぜ採り上げたかと言いますと、深大寺の蕎麦店「門前」さんが登場しているからです。
女子大を卒業した若い輪香子は一人旅を思いつきます。輪香子の父は高級官僚です。その父に娘は小旅行の許しを願い出ますが渋られ、母親からもお父様がダメと言ったらダメですよと宣告されます。ですが何とか「三泊四日以内、かつ旅館は父親が決めた所にするなら、許可する」ということになりました。この小説が書かれたのは昭和35年、そのころの一般家庭はこういうものでした。
輪香子は木曽福島を歩いてみたかったので、名古屋 → 木曽福島 → 諏訪を巡ります。そして諏訪に行ったとき、たまたま復元された竪穴住居があると聞いたので立ち寄りました。そのとき輪香子は変な青年と出会います。彼は古代史が好きらしく、茅野の尖石竪穴住居へ行ったり、明日は富山へ行って洞窟を見ると言っていました。茅野の尖石史跡公園といえば、蕎麦博士といわれた氏原暉男先生の研究室へ行く途中にありますから寄ったことがあります。そのため、若い二人が出会った場もあんなだったろうかとその景色が浮かんできます。輪香子は青年に好感をもちましたが、その日はそれだけで別れました。普通の袖振り合うていどのご縁ならそんなものでしょう。 帰宅してから娘は母親に旅の報告を求められます。
娘:「お父さまの指定の旅館には、わたし、ちゃんと泊まりましたわ。でも、駅までのお迎えや、旅館にまできて、差し入れたり、お節介していただく約束はしませんでしたわ。」
父が絶対だと思っている母は、話を父に報告するつもりです。そこが若い娘にはちょっぴり不満なのです。
母:「差し入れなんて、きたない言葉はよして頂戴。」なんて会話が続きます。
私は、「ン・・・! そうだったのか」と思って、念のために手元の辞書で確認しますと、「差し入れ:留置または拘置されている者に、外部から品物を入れること」とありました。言葉というのは低俗語が一般化するところがありますが、昭和35年当時、「差し入れ」はいけない言葉だったようです。が、実はこれが物語の結末を予告しているのです。
数日して、輪香子は女子大時代の同級生に誘われて深大寺へ遊びに行きます。そして蕎麦屋の「門前」で《虹鱒料理》を楽しみます。虹鱒は、東京では水質が中性で温度も適している深大寺でしか育たないそうです。二人は俎の上の虹鱒を見つめています。よく「俎の鯉」といいますが、虹鱒も俎の上では動かないようです。親父さんは「俎の上に乗せたら立派なもんです」と言いました。この親父さんこそが現在の店主浅田修平さんのお父上なんですね。
このとき輪香子は、灌木の枝が遠くで鳴る音がしましたので、何気なくその方を見ました。すると、あの諏訪の遺跡にいた古代史の青年の姿があるのです。偶然でした。輪香子は驚きました。しかし青年には連れの女性がいます。背がすらりとして、陰影の深い顔でした。自分より五つぐらい年上でしょうか、おだやかな知性の匂いを感じますが、それが輪香子には圧迫でした。一応、挨拶だけはしました。こうしてこの物語は始まりますが、昔の小説では素晴らしい女性を褒めるとき「知性的」という言葉がよく使われました。でも最近では使われないなと思いながら、読み進めますと、実はこの物語の主人公は連れの女性の方でした。こっそり明かせば、この知性的な美しい女性、頼子こそが悪い女なのです。そんなわけですから、『波の塔』の物語は深大寺から始まると言っても過言ではありません。
ところで、前話では三島由紀夫は「門前」の隣の「むさし野 深大寺窯」で鳩笛を買いました。しかし歴史通の清張は深大寺土産の藁馬を採り上げました。
頼子は青年に「どうして、藁の馬をここで売っているか、ご存じ?」と青年に尋ねます。古代史青年の本業は検事でした。ここが清張らしいところです。輪香子と出会ったときは趣味の旅だったのです。
頼子はきれいな声で言います。
阿加胡麻乎 夜麻努尓波賀志 刀里加尓弖 多麻能余許夜麻 加志由加也良牟
(赤駒を 山野に放し 捕りかにて 多摩の横山 徒歩ゆか遺らむ)
755年(天平勝宝7年)宇遅部黒女の歌
「万葉集にあるのが由来よ。わたしも受け売りですわ。」
受け売りではここまで完璧に歌えません。これも頼子の謎の部分です。だいたい頼子は青年には自分のことは一切話していません。連絡は頼子の方からするという関係でした。
話を戻して、万葉歌の作者宇遅部黒女は、豊嶋郡(現在の東京都豊島区を含む都内の一地域)の椋椅部荒虫の妻です。多摩の横山というのは、現在の多摩丘陵を指します。
中央政府から防人として勤務するよう赤紙が来ましたが、急なことなので放し飼いしていた馬を呼び寄せず、夫は徒歩ででかけたという焦燥の歌です。
頼子も人妻、この若き青年と不倫の仲ですが、夫を歩かせてしまったとは、どういう気持で口ずさんだのでしょうか、意味深です。
頼子の夫は、政界の情報屋という影の仕事をしていますが、かなり羽振りがよく、頼子も女中付きで十分贅沢をしていました。しかし夫は自宅より妾宅で生活することが多い毎日です。夫婦としては異常な関係でした。知性豊かで美貌の妻は夫の仕事の「影」のせいで閉じ込められているようなものです。当然、妻の頼子は心の中で叫びを上げます。その聞こえない声が偶然青年検事に当たったのを機に、頼子の方から青年を誘います。こうして頼子は夫の不在を縫って青年との小旅行を繰り返していました。
しかし秘密事はだいたい漏れます。夫は仲間から聞いた「奥さんを見かけたよ」のたった一言から妻に疑いを持ち始めます。その日の頼子の行動はだいたい聞いていたのに、その男の言い方で裏をキャッチしました。これが伏魔殿のような政界を徘徊している者の狼のような嗅覚なのです。
この後、夫は汚職事件で逮捕されました。闇の仕事が白日の下に晒されます。事件のことを新聞で読んだ頼子は、衝撃で身体がガクガク震えました。夫の汚職のことではありません。夫が仕掛けた罠を初めて知ったのです。事件の担当検事は頼子の愛人の青年でした。妻と検事の不倫を知っていた夫は、復讐のためにそれを暴露して、青年を失脚させたのです。
頼子は夫が勾留されている拘置所へ行きました。拘置所の前には差し入れのための品物屋が並んでいました。夫婦は短い会話を交わしました。空虚感のなかで頼子は、長い間の夫婦の闘争が終わったことを知りました。
帰り際、頼子は遠くから輪香子の姿を見かけました。輪香子の父親も、連座して逮捕されていたのです。その父へ面会か差し入れに訪れたのです。しかし彼女には深大寺であったときの溌剌さはありませんでした。
あのとき頼子は青年にこう言いました。
「あんなお嬢さんと、結婚なさるとよろしいわ。きれいなかたじゃないの?」
これは頼子の女としての自分自身の願望でした。
そんな、まともな家庭をもちたいという妻の叫びが夫には聞こえませんでしたし、夫は聞こうともしなかったのです。政界の闇に生きたきた男は、家庭に陽を当てる術を知らなかったのです。妻は復讐に走りましたが、夫をさらなる復讐を仕掛けてきました。言葉を換えれば傲慢な男の破滅という無理心中でした。この捩れた憎悪愛を何といっていいのか、言葉が見つかりません。なので、ここではカタカナで「ラブ・ミステリー」としました。
頼子の夫への復讐として青年との第二の人生の道があったかもしれませんが、清張は頼子にその道を与えませんでした。汚れ役が社会になぜ存在するのか。これが社会派清張のテーマなのです。昨今の「もり・かけ」事件、広島の夫婦議員による選挙違反事件、東京15区のIR汚職事件等々政界の悪は後を絶ちません。社会派の清張は、社会の悪を許したくなかったのです。
頼子もまた影に汚染された自分の身では、普通の家庭は望むべくもないことが見えていました。青年とのことは終わりにしなければならない。
頼子は湖畔のホテルで最期のコーヒーを飲みました。静かな西湖に波が立ちました。それから用意していた白い粒を口にしてから、青木ケ原の樹海へ独りで向かって行ったのです。
この本を読んでいた春は、庭に「ねじれ花」が咲いていました。漢字では捩れている花「捩花」と書きますが、植物図鑑には螺子=ネジのようだということで「ネジバナ」と表記してあります。しかし日本人には風情のある「捩花」、または「ねじれ花」の方が好みでしょう。ただ今日ばかりは「頼子の花」という名がふさわしいようにも思えます。 「ねじれ花」は来春にまた小さな花を咲かせます。でも「頼子の花」はもう咲くことはありません。
参考
松本清張『波の塔』
『ものがたり深大寺蕎麦』シリーズ
・727話 ねじれ
・721話 謎の武蔵国司の乱?
・720話 深大寺白鳳仏はどこから?
・718話 白鳳仏 千年の目覚め
・717話 青春の白鳳仏
・716話 二重の異邦人
・715話 日本の中の朝鮮文化
〔文・絵 深大寺そば学院學監 ほし☆ひかる〕