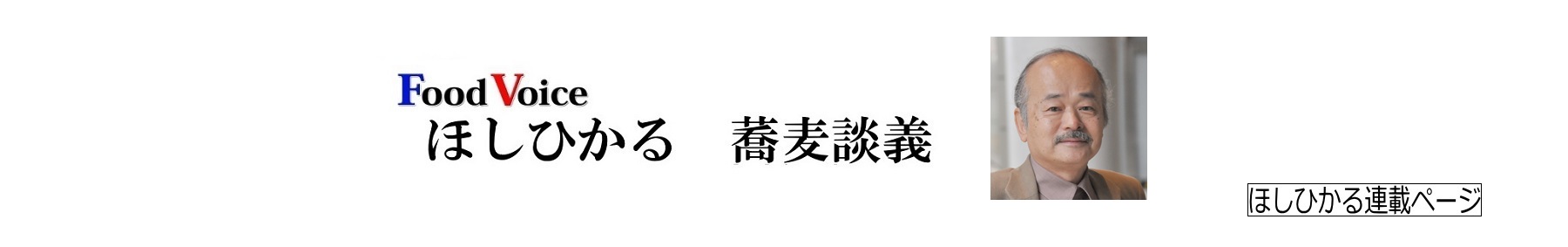第240話 謎の絵師蘭崖
2025/12/06
神田明神の祭神は、一の宮《大己貴命=大黒様》、二の宮《少彦名命=恵比寿様》、三の宮《平将門命》である。
そのうちの将門公の御真影が、神田神社の記念館にある。「七人の影武者」の伝説を題材にして描いた掛軸であるが、この伝説は将門の子孫千葉氏が守護神としていた北辰(北極星)からきているという。すなわち、【北辰・北斗七星】の関係から、【将門・七人の影武者】となったというのである。
この「将門公御真影」を描いたのは蘭崖三宅高英という絵師だ。落款が捺してあるから間違いない。ところが、彼の生年月日や素性、および絵の由来も「まったく分からない」と神社側は言っている。
分からない場合は、それだけ想像の余地があるから楽しくなるというものだ。それにしても、もう少し謎解きのヒントはないものかと国会図書館で調べてみると、彼が『蘭崖画譜』という画帳を出していることが分かった。『画譜』といっても挿絵集だが、上梓したのは明治14年9月10日だ。画集を上梓できるのは、一般的に油がのった年頃だろう。だとすれば、彼の活躍期は明治だったという仮説も考えられる。
奥付には、「三宅高英 = 士族、北豊島郡金杉村86番地」とある。三宅という姓氏は古くからあって、士族にも多い。金杉村は今の台東区根岸であるが、そこに住んでいた元武士の絵師というわけである。
出版社は、芝区中門前町1丁15番地の玉林堂、主人を杉立辰二郎という。中門前町1丁は今の芝大門、いわずと知れた増上寺の門前である。
わが国の出版社のルーツは京都などの寺院の経本印刷から始まった。それが江戸時代になると日本橋をと中心とした版元が黄表紙や浮世絵を作るようになった。増上寺門前にあった玉林堂は、寺社関係の書や絵画の本などを扱っていたのだろうか。さらに調べていると、辰二郎は明治13年に『漢画石譜』というのを出版している。作者は大岡雲峯(1765~1848)、雲峯は江戸画壇の大物であった。そういう絵師の画集を出せる玉林堂もそれなりの出版社であったことが、うかがえる。
話は変わるが、神田の社の古くからの祭神は《大己貴命》と《平将門命》であった。
しかし平将門は、武士の頭領である源頼朝や徳川家康から敬われたが、明治政府は「将門は皇家に矢をひいた者」として見ていた。
だというのに、明治天皇が神田明神に行ってみたいと言い出した。困ったのは宮内省、「《大己貴命》はいい、しかし・・・」と考えた末に、鹿島の大洗磯崎神社の《少彦名命》を分霊勧請することにし、《平将門命》を格下げした。これが明治7年8月のこと。そして翌月に陸軍演習の途次に天皇御親拝となった。
そんなことが一時的にあったとはいえ、維新後は徳川色の強いモノ、あるいは江戸文化そのもの、ひいては日本文化というものが軽んじられていった。というよりか、新権力者となった地方の下層武士出身者たちは江戸文化に対して何の理解も関心ももちあわせていなかった。彼らは足元より、遠い異国の文化を羨望していた。だから、「文明開化」を成し遂げたのである
そうした流れから、日本は君主大権を残すドイツのビスマルク憲法をモデルとする方へと大きく舵を取ろうとしていた。「明治14年の政変」もそうであった。
この動きは食においても然りであった。明治5年に天皇は初めて肉を口にされ、これを機会に皇室の正式料理はフランス料理となった。さらに明治16年から鹿鳴館時代に入った。もはや江戸は遠くになりにけりである。
そんな潮流の中、元士族である、日本画の絵師三宅高英は、武士の間で敬われていた平将門を描いた。
掛け軸の前に立ってそれを見ていると、将門と蘭崖の二人の声が聞こえてくるようだ。「われわれは〝反骨〟という一本の線でつながっている」と。
その声を感じ取っていると、なぜ「影武者なのか」が分かったように気がした。あの日に亡くなったのは影武者であって本当の将門は生きているというのが、この影武者伝説の意味である。
同様に、「日本の武士魂は生きている、不滅だ」と、文明開化の時代の反骨者は言いたかったのではないだろうか。
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕