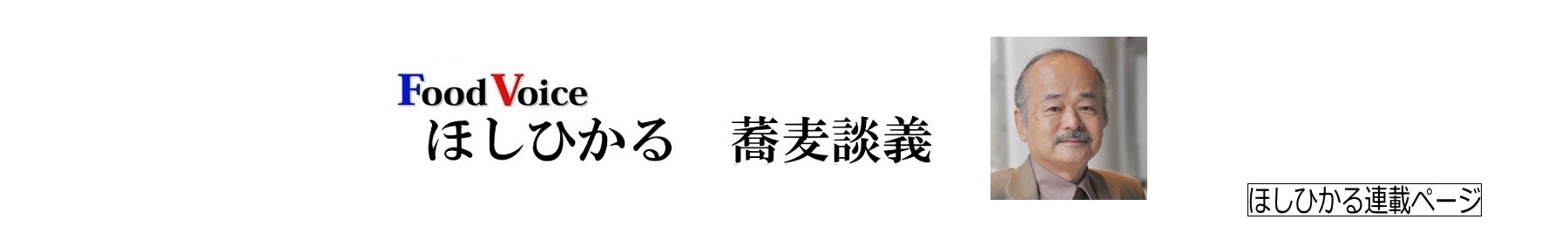第942話 私たちには、これが蕎麦
2025/12/06
~《へぎ蕎麦》文化と小嶋屋 ~
新潟名物の《へぎ蕎麦》でよく知られている小嶋屋は小林三家で営んでいます。小林三家というのは、小林重太郎が大正11年に創業した「小嶋屋総本店}、重太郎の三男小林辰雄が昭和30年に店舗を構えた「越後十日町小嶋屋」、そして重太郎の五男小林信雄が昭和45年に立ち上げた「越後長岡小嶋屋」です。
この小林三家のうちで一番活躍している越後十日町小嶋屋(小林均社長)とそばネットジャパン(阿部成男代表)が共催した研究会「へぎそば文化と小嶋屋」(北川育子氏プロデュース)に参加するために、新潟十日町市の小嶋屋さんにやってまいりました(令和7年5月)。
初日は、1)越後十日町小嶋屋の小林均社長のお話を伺い、2)それを受けて筆者(江戸ソバリエ協会理事長)が、郷土蕎麦について少しだけコメントさせてもらい、それから蕎麦に欠かせないつゆ部門の話として、3)ヤマサ醤油㈱、4)福島鰹㈱の方たちから醤油と出汁についての講義をいただきました。5)さらに《へぎ蕎麦》は食べやすいように丸く束ねてあるのが特徴で、それを「手振り」といいますが、その実体験もありました。
2日目は、6)越後十日町小嶋屋の工場見学、7)新嵜照幸氏と廣木和美氏によるへぎ蕎麦デモンストレーション、8)へぎ蕎麦打ち体験が行われました。
越後《へぎ蕎麦》小嶋屋の創業者小林重太郎は、それまでハレの日など(冠婚葬祭)で、民間の人によって食されていたと言われています手打ちの《布海苔蕎麦》を、機械打ちにして、販売する「小嶋屋」を新潟県川西町(千手村木嶋)に設立しました。言ってみますと、小嶋屋は「家庭 郷土食」を企業化して「新しい郷土蕎麦」として売り出したのです。
「ハレの日には蕎麦」という形は、昔の村でよく耳にすることでしたが、一方では蕎麦はむしろ寒村の貧しい食べ物だったとの話もあります。なのに、そういう公的な席に蕎麦がなぜご馳走になるのか、腑に落ちないところがあります。それはこういうことです。江戸時代、江戸などの都市では〝貨幣〟中心の商売が活発でしたが、地方の農村では〝年貢米〟で日常が動いていたのです。分かりやすくいいますとお米がお金でした。ですから、年貢(税金)を藩に納めたあとは、各家庭では僅かに残ったクズ米に大根や大根菜などを混ぜて炊いたメシが、日常食だったという時代には、蕎麦がご馳走だったというわけです。その「ハレの日」の慣習は明治・大正になっても傾向としては続いていたようです。
小嶋屋の《へぎ蕎麦》の特徴的なことは、《布海苔蕎麦》ということと、板の容器と、それに《へぎ蕎麦》というネーミングです。
布海苔につきましては、当時、この地方でも近隣地区同様に、繋ぎには山牛蒡・小麦粉・卵などが使われていたのでしょうが、小千谷と妻有地区だけは越後縮の生産過程で使われる布海苔も繋ぎに使用されていたのでした。これに重太郎は目を付けたと思われます。容器は小嶋屋では和菓子販売用の盆をヒントにして近くの大工さんに作ってもらったといいます。そして名前は削った板を「へぎ板」と言ったりしますが、その「へぎ」をとって《へぎ蕎麦》としました。
ただ、初代の重太郎が企業化した「蕎麦専門店」は機械で製造し、「へぎ」に盛って販売しましたが、蕎麦屋という店舗ではありませんでした。それを店舗化したのが「越後十日町小嶋屋」の辰雄(小林均現社長の父)です。そして三代目の均社長はそれまで、大きな「へぎ」に盛られた蕎麦を店舗内で囲んで食べるという形式だったものを現在当たり前に見られるようなお一人様用の食器にしたのですが、この個人化が、店舗のあるべき姿だったのです。もちろん一人用であっても多人数用であっても「へぎ」に盛られる蕎麦の「手振り」は変わりありません。この手振りがいつから見られたのかは不明ですが、おそらく最初は素麺などの細い麺の盛り方は全国このようであったかと思います。といいますのは、筆者の故郷九州北部では素麺は食べ易い量に束ねてありました。また筆者が直接耳にした話でも日本橋や川崎などの古老によりますと、「昔、素麺は束ねて盛っていた」ということでした。それに室町時代以前の史料にも麺を数える単位として「束」という言葉が出てきますから、この方法は伝統的な盛り方であったのでしょう。それがこの十日町一帯では「手振り」、戸隠辺りでは「ぼっち盛り」と名づけられて、今も続いているのだと思います。

それから、デモンストレーションでは、新嵜氏は一般的な《へぎ蕎麦》の打ち方の手法で、廣木氏は繋ぎとしての布海苔の可能性を追究するという思いで更科の水捏ねで臨まれました。とうぜん会場では、加水の量はとか、一般的には蕎麦粉1㎏に糊状の布海苔400gというが、その点はどうかとか、蕎麦麺の長い方が束ねやすいとか、細い方がよりつるつる感が増すなどとかが話題になっていました。それを踏まえて、名人クラスのお二人が丁寧に打たれた《へぎ蕎麦》はたいへん美味しいものでした。
また小林均社長の話では資料における《へぎ蕎麦》の登場は蕎麦研究家の植原路郎あたりではないかということでしたが、筆者もほぼ同時代の新島繁+薩摩卯一共編『蕎麦の世界』(昭和60年)で、芋・山牛蒡の葉・蓬・さるごまなど繋ぎの紹介の一つとして布海苔を掲げているのを拝見していますが、たとえば健康の面からも布海苔繋ぎの追究は課題となってくるのではと思っています。
ところで、当日は衆議院議員(新潟県)の梅谷守ご夫妻も蕎麦打ち体験までご参加されていましたが、夫人によれば「私たちにとっては、これ(《へぎ蕎麦》)が蕎麦ですネ」とおっしゃったのが印象的で、かつて木曽で《すんき蕎麦》を食べたときや、帯広で《札幌ラーメン》を食べたときに「郷土蕎麦(郷土食)は、この空の下で食べるもの」と言われたことを思い出しました。
そして《郷土食》というのは、そうした郷土愛と伝統食を守り続ける人たちがいなければなりません。守り続けるということでは、たとえば小嶋屋のように、1)初代の企業化、2)二代目の店舗化、3)そして三代目による個人化と工場の近代化という〝攻めの改革〟によって、郷土蕎麦がいつでも誰でも食べられるようになったわけです。
筆者も伝統食の世界を少ながらず見てきましたが、やはり地元企業の力は絶対不可欠な要素の一つだと思います。
そういう目で、目に付いた新潟県の食品会社を思いつくままにあげてみますと、伝統食分野ではありませんが、新潟には亀田製菓、ブルボン、サトウ食品、越後製菓、三幸製菓など優れた企業がたくさん在ることに驚かされます。「サトウのごはん」はご飯革命を起こしました。「柿の種」はビールの国民的つまみとなりました。越後には独特の起業家魂が見受けられるような気がします。
私たちは、そういう魂のある地元企業を応援できればと思っているところです。
《こぼれ話》
今回の研究会参加者は約25名でした。そのうちのソバリエの一ノ瀬さんと、同じくソバリエの石川夫人と小生の3名が同じ誕生日ということが判明し、みなさんに驚かれて拍手をもらいました。
よって、この拙い文を誕生日の5月21日の善き日に掲載させていただきました。

写真提供:河邊美季さん、
(小林社長、へぎ蕎麦4人分、へぎ蕎麦1人分、5/21生まれの3人)
江戸ソバリエ協会
ほし☆ひかる