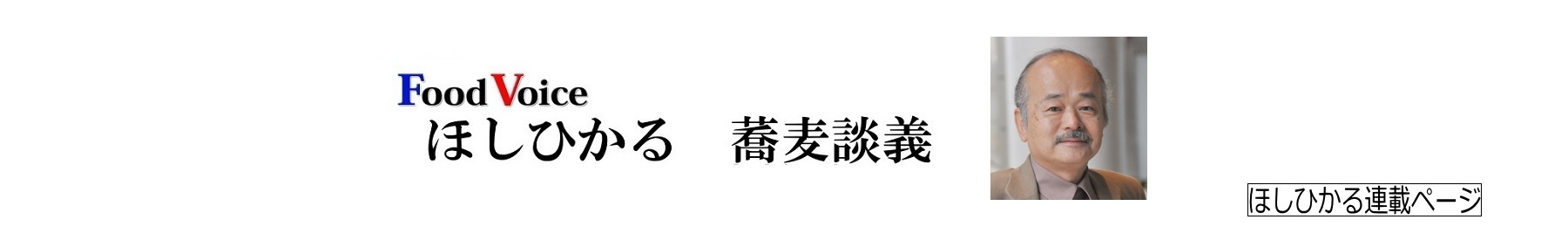第959話 ブルー・トレインと氷見のうどん
2025/12/06
~ 日本列島の熟成力 ~
☆富山地鉄 市内電車
10月、出張で富山県を訪れることになりました。
夕方の18時半から数名が集う食事会に誘われていましたので、その前までにホテルへ入ればよかったのですが、この一週間忙しくて、時間に合わせたキッブの予約を怠ってしまいました。そのため、早めのお昼過ぎに東京駅へ行って、そのまま北陸新幹線「はくたか565号」に乗りました。
富山駅に着いたのは16時です。今から約2時間、どうやって時間を潰そうかと考えたとき、ふと思い出したのが、市内に「ブルー・トレイン」という喫茶店があるらしいということでした。さっそくスマホで検索してみますと、駅前から「富山地方鉄道 市内電車」で5つ目の安野屋駅で下車とあります。新幹線と市電に乗って、喫茶「ブルー・トレイン」へ。それもいいじゃないかというわけで、停車場へ。するとずいぶんレトロな、というよりか古びた型の車両がやって来ました。なかなか乗り甲斐があります。運賃は240円でした。
下車してから、歩いていた高校生に店を尋ねると、すぐ近くだと教えてくれました。
ドアを開けて入ると、世界の列車のミニ模型がずらりと並んでいます。数えきれないほどです。有名な「オリエント急行」もちゃんといます。学生時代の私が乗っていた「さくら」「みずほ」「あさかぜ」の懐かしいプレートが壁に飾ってあります。コーヒーを頂いていると瞬、半世紀前の夜行寝台列車の走る音が耳もとを通過していきました。出会いには、そんな思い出を引っ張り出すところに意義があると思います。そうでなければ、ここはただ一休みするだけの喫茶店でしかないのです。
でも、日本にはどうしてこういう〝鉄道文化〟があるのでしょうか。
韓国の観光社会学者アン・ウンビョル(東京大学大学院助教)さんも不思議がっています。「日本人にとって鉄道というのは移動手段だけではなく、鉄道に乗ること自体が目的みたいな、特有の文化だ」と言っています。
島国日本は、一度伝来したら、海外へ出ていかないで、列島内で熟成して、独自の鉄道文化となるのでしょう。
コーヒーを飲み終わってから、私は店を出ました。
安野屋駅からホテルのある桜橋駅まで乗りました。
夕食が楽しみです。


追記:須賀敦子の「オリエント・エクスプレス」は素敵なエッセイです。ああいう感性の高い文章を書きたいのですが、なかなか及びません。
☆氷見のうどん
富山市での仕事が終わりました。
Kさんが、「富山駅まで送ってくれる人がいるけど、一緒に行きませんか」と誘ってくれました。帰りの乗車券の予約もしていませんから、少しで早く駅へ行きたいところですので同乗させてもらいました。車中で話してみるとKさんも予約はしていないとのこと。駅についてから、二人で18:30分発の「はくたか574号」を買いました。出発まで1時間ちかくありましたから、ゆっくり土産でも買おうということになりました。
ぶらぶと見回っていますと、うどんがありました。ホテルの朝食にもうどんがありましたが、富山は麺王国といえるところがあります。蕎麦も盛んですが、《氷見のうどん》(氷見市)や《大門のそうめん》(砺波市)の歴史は江戸中期ごろから続いていると聞いています。
もともと日本の麺類というのは、南宋へ留学した僧たちが彼の国で打ち方を覚え、その知識や道具を日本へ持ち帰って、京の大寺院で点心料理として食しました。それが室町後期ごろには地方へ伝わりました。そのひとつが曹洞宗総持寺祖院(輪島市)に伝えられたのですが、そのため総持寺の僧侶は今でも修行僧は四九日(四と九の付く日は座禅を休む)にはうどんを食べる習慣があるそうです。
やがて、この総持寺の麺類製法は民間に広まり、輪島の《白髪素麺》として加賀藩御用達にまでなっていたのですが、輪島の素麺は今は絶え、富山へ伝わった《氷見のうどん》と《大門のそうめん》が今も同じ製法で続けられているわけです。その状況証拠とでもいうのでしょうか、輪島地方には「能登麦屋節」、富山県白端地区には「越中麦屋節」という粉挽き唄が残っています。
南宋 → 京の大寺院 → 地方の寺院 → 地元民 → 他の地方へ
その製法を農水省HPで見ますと、小麦粉に塩水を加えて、手でしっかりと捏ねて、熟成させ、さらに生地を足で踏み、力を込めて生地を練り上げます。生地を平たい円形に整えたら、外側から中心に向けて渦巻き状に生地を切って1本の長いロープのようにし、手作業でよりをかけながら伸ばしていきます。その際に油は使いません。2本の棒に八の字に掛けて熟成させた後に、さらに伸ばします。この作業を繰り返し、細く伸ばして竿にかけ、干して仕上げます。
熊本県南関町のそうめん作りの動画を見たことがありますが、氷見も、そして砺波、五島列島、稲庭などもほぼ同じ作り方です(ただ油の使用がまちまちです)。
それはおそらく、古に南宋の国から伝来してきた作り方とそう変わっていないと思います。
島国日本は、一度伝来したら、海外へ出ていかないで、熟成して、独自の麺文化となっているからです。
そんなわけで《氷見のうどん》を買うことにしました。
帰宅してから、涼性の《つけ》と温性の《かけ》で頂きました。
《うどん》(小麦麺)は、品格のある滑らかさが魅力だと思います。
その点、この種の古式の麺は、しっかりと捏ねて足で踏む手打ちの要素と、手を使って縒りをかけて伸ばしていく手延べの要素を併せもっています。
だからでしょう。《氷見のうどん》は、いい滑らかさと、おくゆかしい腰を醸す美味しい《うどん》でした。
江戸ソバリエ
ほし☆ひかる