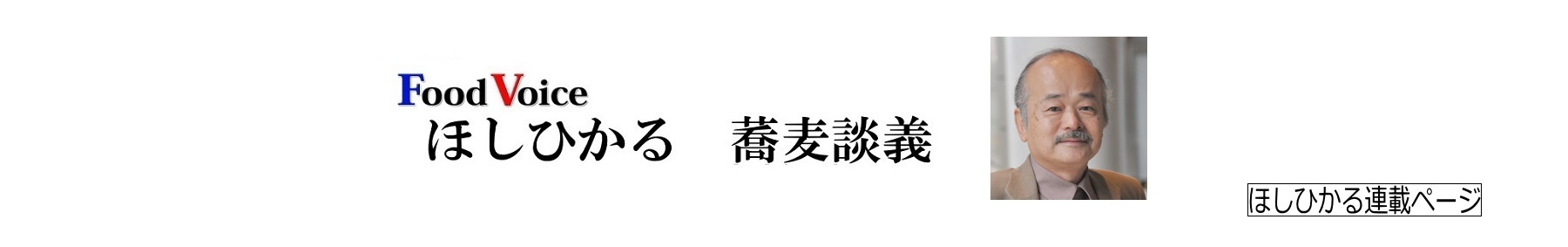第310話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅶ」
2025/12/06
~ Lovin’you♪ ~
「今度、いつ会ってくれる?」
「日曜日はどう?」
「ほんと? 嘘ついちゃいやよ。」
働き盛りの二人、客商売どうしの二人が会うのはあんがい難しかった。
やっと会えたのは、あの日から10日経っていた。
野中は、井の頭公園へ桜を観に行こうと誘った。
二人は腕を組み井の頭公園をゆっくり歩いた。桜の花弁が祝福するように二人に降りかかる。
野中健も美薗恵子も、ただ歩くだけでこんなに幸せになれるのかと思った。
暫く歩いて行くと坂道の途中に〔もか〕があった。〔キャラバン〕の親父が、敬愛しつつもライバル視している珈琲店である。
「あそこに入ろうか?」
「うん。」
珈琲の香りがドアの外にまで漏れてくる。
二人はカウンターに並んで座って、珈琲を飲んだ。格調高く上品な味だった。
〔キャラバン〕の親父さんから、ここの店主は海外へ出かけて行っては、世界の珈琲を味わい、研究した人だと聞いている。
親父さんは、彼の行動力と資金力が羨ましく、敬愛しつつも、「俺は日本の風土に合った珈琲を探す」と頑固になっているのである。
野中は、〔キャラバン〕の親父と〔生粉打ち亭〕の店主のことを思うと、珈琲と蕎麦は似ているように思った。二人の姿は珈琲道、蕎麦道を歩いているようなところがある。〔もか〕の店主だってそうかもしれない。
「ね。私たちって、珈琲に縁があるわね。」恵子は珈琲を深く味わうようにして飲んでいる。
「そうだね、縁結びの神様だよ」と野中は応えた。
「ほんとに縁結びって思ってくれる?」
「うん。」野中は (キミみたいな、美人とデートできるなんて) とは言わなかった。本気で好きになりそうなときに、お世辞とか、ゴマスリみたいな台詞を使う気にはなれなかった。
二人はまた外に出て歩き始めた。
暫く行くと、その先に瀟洒な和風旅館が見えてきた。門の所まで来たとき、野中が恵子の顔を見て、そっと身体を押した。入ろうというのである。
恵子は身体をかたくした。恵子が描いていた野中と結ばれる所のイメージがちょっとちがっていたのである。
野中はそれ以上、無理押しせず、また歩き始めた。
恵子はちらりと野中を見た。
野中は黙ってしまった。
(どうしよう。怒ったのかしら。もしそうだったら、この人の気持を取り戻さなければ。恵子だって、貴方と同じ気持。でも、ゆっくりとした時間の中で貴方と・・・、できれば自分のマンションに来てもらいたいくらい。あ・あ~、何と言って誘えばいいの。)
桜の花弁が落ちてくる。
恵子は、ただ野中への対応を考えることに夢中になっていた。(「送ってくれない?」ではお別れみたい。「うちに来る?」では試しているみたい。でも、やはり・・・、)「ね、恵子のうちに、来てくださらない。」
野中が恵子の目を見つめ、肯いてくれた。
(よかった。) 恵子はほっとして、野中に笑みを送った。
桜吹雪がさっと舞った。恵子は野中の腕を強くつかまえた。
二人は車まで戻ってきた。陽は落ちてきている。野中の車は築地へ向かった。
途中、野中が言った。「千鳥が淵の桜もきれいだよ。ちょっと寄ってみようか。」
野中は九段に着くと、靖国通りの片側に車を停めた。
桜の花をたっぷりまとった枝が堀の水を欲しているかのように何本も垂れ下がっている。
「うわ、きれい!」恵子が感嘆の声を漏らした。恵子は車のドアを開けて、外に出た。
これまでの恵子は女子大生のころから、明子ママの言うがままに〝大人の女〟ばかりを演じてきた。それが野中といるときだけは〝少女〟のようになれる。その感覚が何ともいえず心地よかった。
花弁が恵子の周りで踊り始めた。恵子は両手を高く伸ばして思切り背伸びをした。
「きれいだ・・・、」野中が呟いた。
恵子が野中を手で招いた。
野中もドアを開けて出て行って、恵子と向き合った。
桜がまた舞い落ちてきた。
恵子はベッドの中で目を覚ました。束の間だったが、眠っていたようだった。恵子は隣で眠っている健の頬に軽く唇を寄せると、そっとベッドから抜け出し、バスルームに入った。
恵子は夢の中で両親と会っていた。高校生のときに病死した父を思い出すのは久し振りのことであった。
これまでの恵子の男性観には父の影響が少ながらずあったような気がする。画家だった父は、アーティストとしての千利休の生き方に心酔していた。それは侘びの世界を創出しながらも、他方では真逆の煌めく金の茶室を演出するという、幅の広さだった。その賛美をよく目を輝かせて恵子に語って聞かせていた。
それから恵子は、人間としてのスケールの大きい男、それを脳裏に描くようになっていた。しかし、それに叶ったのは恩師三木茂吉だけだったのかもしれなかった。「闇将軍」と畏れられた三木であったが、実は女性に対しては高潔であった。生涯独身を通し、一人明子ママだけを愛した。
その三木によって、恵子の信用取引や株取引における能力は引出された。あるとき三木は「お前のジイ様はあの佐々木竜三だったのか。どうりで博才があると思っていた」と言った。
恵子は母から母方の祖父竜三は材木商だったとだけ聞いていた。
しかし三木が話すところによると、かなり荒っぽいウリカイをやる男として有名だったという。「お前の勘と決断力はジイ様譲りだな」と満足そうに笑っていたが、釘を挿すことも忘れなかった。「それでもナ、所詮お前は女、これを商売にするな。せいぜいカブていどにしておけ。それよりもその才を他で活かすことを考えろ。」
三木は亡くなるとき、ある程度贅沢できるくらいの財産を明子に遺し、残る巨額の富は生まれ故郷に寄付して逝った。三木茂吉はそんな男であった。
それに比べて、これまで恵子に近づいてきた男は表の世界では名がありながら、実際には情けなかった。それでも恵子はそれが父の言う〝幅〟だと思っていた。
しかし野中と初めて会ったとき、彼が違う〝色〟をもっている男だと直観した。その色が何なのかは、まだわからない。
恵子は、肌を合わせたまま隣で眠る野中の温もりに〝家族〟を感じていた。だから両親の夢を見たのだろうかと思った。
恵子はバスの湯の中に身体を沈めた。思わず鼻歌が出た。
「La la la la la.♪ Doot-n-doot-n do doo ♪」
それは恵子が好きな【Lovin’you】だった。
初めてラジオでミニー・リパートンのこの歌を聞いたとき、可愛い歌だと思った。すぐに銀座のレコード店に問い合わせてみたが、「まだ日本では発売になっていない」という。恵子はアメリカから取り寄せてもらった。
恵子はバスから上がって寝室へ戻った、バスタオルを巻いたまま窓辺に行って外を見た。銀色の大きな月が浮かんでいた。
「さっき歌ってた?」健がベッドから声をかけた。
「あら、起こしゃった? ごめんなさい。ネ、さっきの歌知ってる?」
「La la la la la.・・・♪のメロディは聞いたことあるけど、曲名までは知らないな。」
「【Lovin’you】っていう曲よ。歌って差し上げましょうか? 愛しい健さまのために!ふふふ」微笑みながら言うと、恵子はいきなり健の身体に飛びかかって覆い被さり、健の耳元で歌い始めた。
「La la la la la.♪ Doot-n-doot-n do doo ♪
Lovin' you is easy cause you're beautiful
Makin' love with you is all I wanna do
Lovin' you is more than just a dream come true
And everything that I do is out of lovin' you
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo Ah...・・・」
ここまで歌うと、恵子「くくく・・・・、」と枕に顔を埋めて、笑いを堪えた。
「何だい?」
「ううん、何でもない。」
「言え。」今度は健が恵子に馬乗りになって、恵子の鼻を摘まんだ。
「白状しますから、お許しださいッ」恵子が鼻を摘ままれたまま、笑って言う。
健が手を離すと、恵子は身体をクルリと回転させ、また上になって健の耳元で囁いた。
「子供ころね、お母さんが恵子の耳元で童謡とかをよく歌ってくれてたことを思い出したの。」
「おれは子供か。」
「ううん、ちがいます。お母さんは恵子のことを愛しいてたから、優しく子守唄を歌ってくれたの。恵子は、あなたのことを愛しているから、優しく愛の歌を歌って上げるのよ。」
たまらなくなって健は、恵子を抱きしめた。
抱かれたまま恵子は言う。「日本語ではこうよ。」
「Lovin’you の?」
「そう。」
あなたを愛することはとても簡単なこと、だってあなたは素敵だから、
恵子の望みはあなたと愛を交わすことだけなの、
夢がかなうことより、もっと素晴らしいものはあなたへの愛、
恵子がすることは すべてあなたを愛すればこそ
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo Ah...・・・♪
「この歌は今日から恵子の歌よ!もうミニー・リパートンの歌じゃないの、」
恵子は続きを口ずさむ。
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in the springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you
Lovin' you I see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo
Ah...
健は、女の優しさをあふれるほどに享受できる幸せに酔っていた。
(Ⅷ.〔愛してる〕へ 続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕