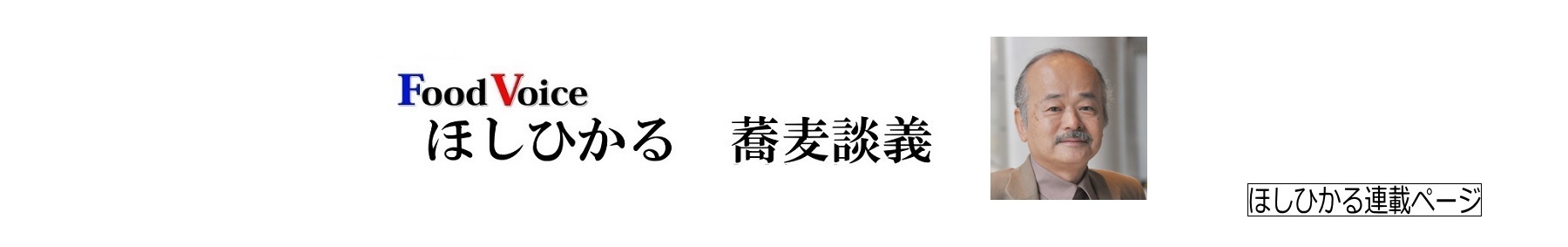第314話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅹ」
2025/12/06
~ I’ve Lost You〔去りし君へのバラード〕♪ ~
ニューヨークから東京へ帰って来た美薗恵子と野中健の二人は、仕事に戻った。
帰りの機中も楽しかった。二人は、店の女の子たちとカナダ旅行したことや、仕事で学会に行ったことが、記憶の外にあることに気付いて笑い合った。
ニューヨークでは、酔ったせいもあって恵子はベッドの上でかなりわがままに振る舞って健を困らせた。そして恵子はそれを見て喜んでいた。いま思い出すと恥ずかしいくらいだ。
恵子は滞在中のホテルや街を歩いているときに「ハネムーンみたいだ」と何度も健に言いかけては言葉を飲んだ。一番言いたいことが、気軽に言えない何かが恵子の胸の中で疼いていた。その大きな理由は、34歳の自分がサラリーマンの健との、いえば人並みの結婚が許されるのだろかという悩みだった。思い切って「結婚してほしい」と恵子が言ってしまえば、あの人は「うん」と言ってくれるだろう。しかし、生活環境の違う私と一緒になることが、この人にとって幸せなことだろうか? 「二人で過ごしたニューヨーク」ということで満足しなければならないだろうか? でも、健とは別れたくない。
仕事ではたいていのことも切り抜けてきた銀座〔クラブ恵子〕のママも、真剣な愛の始末には迷うばかりであった。
会社に戻った野中に秘書室から電話があった。小田社長が呼んでいるという。内容は、アメリカへ行った他の連中が「社長の取り調べを受けている」と言っていたから、分かっていた。
創業者社長の小田は、事業の芽、政治・経済・社会の変化、何でも強烈な関心を示した。だから、アメリカに行った連中から、何か参考になる〝土産話〟を聞き出そうというのであったが、その関心度は並大抵のレベルではない。細部にわたって執拗に訊くし、返答に詰まると「そんなことも調べないで、何のために行ったのか」と叱られる。そのために報告者はヘトヘトだ。だから、社員たちは〝取り調べ〟と称しているのである。
野中は秘書の山中に「お客さまとの約束があるから」という理由で遅めのアポを押さえてもらった。その間に何を報告しようかとまとめる必要があったからだ。社長の性格としては何事も早め早めに対応しないと機嫌が悪くなるのであったが、同時に叩上げの商売人気質の社長は、お客様との約束を破ることを一番嫌う人であったから、秘書の山中の報告によると「遅いアポを渋々承知していた」らしい。
数日して、野中は自分の家の珈琲豆がなくなったので、〔キャラバン〕に顔を出した。しかし、行ってみると、シャッターが下りて、貼り紙がしてある。
読むと、何と! 親父さんが亡くなって、明日お通夜、明後日告別式だと記してあるではないか。(マサカ!) 野中は腰を抜かさんばかりに驚いた。咄嗟に (半年ぐらい前から痴呆がひどくなって入院している奥さんは、どうしてるんだろうか) と心配になった。
店の裏にある自宅へ行って覗いてみるが人影が感じられない。(やはり奥さんは入院したままか。) そう思って、再び店の前に戻って、佇んでいると近所の人が通りかかった。その人は野中の顔を見て、「あんた〔キャラバン〕に豆を買いに来る人だね」と声をかけてくれた。
「はい。」
「一昨日だったよ。病院を予約していたらしいけど、来なかったから、婦長さんが見にきてくれたんだって。婦長さんは、すぐそこの人だからね。」
「・・・。」
「そしたら、布団の中で冷たくなってたんだって。」
野中は頷いた。親父さんは前から心臓が悪く薬を服用していたことは知っていた。「奥さんは、入院中でしょうか。」
「そうそう。婦長さんが奥さんに会って、言ったらしいけど、ぜんぜん分からないんだって。」
「かわいそうに、」
「でもね、マスターは偉いんだよ。店と家を担保にして銀行からお金を借りて、奥さんの入院費用を作って遺してくれていたんだって、オトコだねえ。うちの亭主はそんなことしてくれないよ。」
「そんなことはないでしょう。」
「で、ほら二軒先のあそこが区会議員の荒井先生のお宅だからね。荒井先生を中心に近所の人たちが一緒になって、お葬式をやって上げてやろうということになったんだよ。マスターにはお子さんがなかったからね。」
荒井議員は店で会ったことがあるから、野中も知っていた。「分かりました。ありがとうございました。」
野中は、シャッターの下りた店に合掌してから、その場を去り、奥さんが入院している病院へ行ってみた。
奥さんはベッドの上に座っていた。ずいぶん白髪が増え、小さくなったような感じだった。奥さんは野中を見ると、「あ、野中さん、珈琲ですか?」と声をかけた。
「お願いします。〔キャラバン〕の珈琲が一番だからね。」思わず、奥さんにそう答えた。
「主人もね、一生懸命研究しているからね。」そう言うとあらぬ方向に視線を移し、そのまま野中の方を見なくなった。
看護婦さんがやって来て「おたくの名前はちゃんと呼んでましたか?」
「はい。」
「一瞬だけ正常になるんですけど、あとがタメなんですよ。」
「・・・・・・。」野中は溜息を吐いた。見ていると辛くなってくるので帰ることにしたが、「また来ますから、元気でね」と言っても反応はなかった。
夜中になって、健は恵子に電話した。「珈琲が恵子との縁を結んでくれたって、言ったっけ。」健は気落していた。
それを感じて、恵子は神妙に応えた。「はい。聞きましたわ。」
「おれに珈琲を教えてくれたのは〔キャラバン〕という珈琲店の親父さんだったけどね、その人が亡くなったんだ。だから一緒に葬式に行ってほしいんだ。いいかな。珈琲が縁で恵子を知ったって、せめてご霊前で言いたいんだよ。」野中の声はくぐもっていた。
思わず恵子も涙ぐんだが、それは健の気持が嬉しかったせいもあった。(あの人は恵子のことを真から大事に思ってくれている。) そう思いながら、返事をした。「はい。恵子がお役に立てるなら、ご一緒させてください。」
「ありがとう。」健は続けた。「それから、今日はそっちに行っていい?」
「うん。待ってる。気をつけてね。」そう言って受話器を置いて、瞼を押さええながら、念のためにと手帳を見てみると、生憎、葬式と言われた日はお客さんとお昼の食事を約束していた。明子ママからは「約束は絶対破るな」と教えられたけど、(あの人の方が大切。お客さまの方は告別式が入ったと言ってお断りしよう)と決め、健を迎えるためにバスに入った。
翌々日の告別式は午後1時からだった。健は午前中も夕方も仕事が入っているから、恵子のマンションへ12時に行くので着替えさせてほしいと言っていた。
その前の11時には取引銀行の新任の支店長が挨拶に来た。美薗恵子は銀行にとって大事なお客様のベスト幾つかに入っていた。だから、盆、暮とか、支店長が代わったときには必ず挨拶に来た。
しかし、恵子はよほどのことがないかぎり、人を自宅に入れないことにしていたので、マンションのミーティング室で新任支店長の挨拶を受けた。
恵子は、支店長が帰った後、喪服に着替えて待っていた。
健は12時少し前にやって来た。健は恵子の姿を一目見るなり「おお、きれいだ。惚れぼれするよ」と言いながら恵子の寝室で、今まで来ていたスーツを脱ぎ始めた。
恵子は健の下着姿を見て困惑した。昼間の下着姿は夜の愛の時間とはまた違う、何か生活感のようなものを感じさせた。恵子は戸惑いを隠すようにして健が持ってきた黒い靴下を取って、足に履かせて上げた。こういう世話も初めてのことであった。
「ありがとう。行こうか。」
式は下谷の自宅で行われた。喪主不在の葬式だった。弔問客は珈琲豆メーカーなど取引会社の社員二、三名と近所の人だけの寂しいものであった。読経が終わると、親父さんの亡骸は町屋の火葬場へ向かった。議員の荒井先生が一緒に付いて行ってくれた。
恵子は終始、健の背後に控えていた。その姿に皆からは新妻のように思われたようだった。区会議員の奥さんが、残った人に対して「お店の方で〝お別れの珈琲〟を淹れてますから、ぜひ飲んでやって下さい。野中さんも、奥様も、さ、どうぞ。」と誘導した。
健と恵子はテーブルに座った。珈琲豆メーカーの社員らしき人が珈琲を持って来てくれた。
恵子は〔キャラバン〕の豆を初めて飲んだ。おとなしい味だけどスッキリして美味しいと思った。珈琲碗を持っている健を見ると、目がいつもより少し濡れていた。心の中で相当悲しんでいることが恵子にも分かった。健のためにどうしてやればいいのだろうと思ったとき、議員さんの奥さんという人が「野中さん、いつのまにかこんなにきれいな奥様をもらってたの、」と声をかけた。
野中はそれを否定しなかった。「奥様」と呼ばれて、恵子は心臓をドキドキさせながら立ち上がって、奥さんに一礼した。その後になって、 (どうしよう。余計なことをしてしまったかしら、) と不安に思い、健の顔を見たが、変わりなかった。恵子は (よかった) と安心した。
珈琲を飲み終わってから、健が「失礼しようか」と恵子に言った。
「はい。」恵子も返事をした。
奥さんが送るため、近寄って来て言った。「今日は、ほんとうにどうもありがとうございました。奥様、またいらっしてくださいね。」
二人は車に乗った。
恵子は今日、「奥様」と呼ばれたことが、心地よくもあり、きつくもあった。
以前、よく同級生たちに会ったりすることがあると、20歳のころは「彼よ」とか、25歳ぐらいになると「主人なの」とか言って紹介されたものだったが、そのころまではまだ抵抗は少なかった。だが、その後の30歳ごろになると「長男なの」とか「長女なの」とか言われ、自分と彼女たちの距離感を感じたものだった。今日の心地よさは、その距離感を取り戻したような錯覚をもたらしてくれるのだが、この喜びを健には言えなかった。口にすれば、彼にプレッシャーを与えるような気がした。それがきつかった。
恵子は言った。「親父さんとかいう人が亡くなって、寂しくなった?」
「うん。もちろんそうだけど、人間はいつかは、・・・だから仕方がないよ。でもね、あの親父さんが焙煎した豆は素直で、飽きない味だったんだ。その技術がもったいないと思ってさ。誰も引き継ぐ者がいなかったのだよ。もちろんおれには荷が重いけど、あの職人技を何とかできないのかなって悔しいね。」
「・・・・・・。」恵子はカーラジオのボタンを押した。
プレスリーが泣くような声で歌っている。
「着替に来るんでしょう?」
「うん。そうさせて。」
「今夜は泊まりに来る?」
「いや、明日はゴルフだから、」
「あらら、大変ね。起きられる?」
「大丈夫だよ。」
「何だ、せっかく電話して起こして上げようと思ったのに、」
「ありがたいけど、おれの女神にそんなことさせられないよ。」
「いや。そんな風に言わないで、」恵子はなぜか強く言ってしまった。
「怒った?」
「うん。少し怒った。私は普通の女です、」恵子がそう言ったとき、ブレスリーの歌が終わった。
デスクジョッキーの話手が、今の曲は「I’ve Lost You〔去りし君へのバラード〕」だったと紹介した。
恵子はカーラジオを消すために指でボタンを押しながら言った。「じゃ、いつものように土曜日は泊まりに来てね。」
「うん。そのつもり、」
車がマンションに着いた。
着替えた健が仕事に出かけた後、煙草とライターを忘れていることに気付いた。恵子は健の煙草を一本抜いて火を点け、(ああ、ほんとうに困ったなあ)と苦笑と一緒に煙を吹かした。
恵子は、先ほど「奥様」と呼ばれたことが、尾を引いていた。 (ニューヨークのあの激しかった夜に、どうして私は『結婚して』と言わなかったのだろう。どうしてあなたは冗談でもいいから、『結婚しようか』って言ってくれなかったの・・・)。恵子は一人で目頭を押さえた。
あの事件以来、もう泣かないと決めたはずなのに、健を愛するようになってから、しょっちゅう涙を流しているような気がする。
恵子は健と一緒に住んでもいいとも思っていたが、月曜日の朝7時半には出かける健を見ると、自分との生活時間の差を感じた。たかが生活時間の差、されど生活時間の差だと思い知らされた。また一緒に住んだとしても、(私は炊事も掃除、洗濯すらも洋子さん任せている。) こんな現実的な悩みもあった。
(それでも、今の涙は甘い涙だから、幸せだと思わなければならないのかな。明子ママは「人間を大きくする恋なら大いにやんなさい」と言ってたけれど、これもけっこう辛いわ、明子ママ!)
恵子は時計を見た。(洋子さんが来る時間だ。支度をしなくっちゃ。)
土曜日になった。午後、先日挨拶に来た新任支店長の藤岡が部下を連れてまたやって来た。用件は、恵子の財力を当てにして、「小さいけど、面白い化粧品会社がある。その会社を買わないか」という相談だった。以前にも銀行や証券会社が、そんな話を持ち込んできたことがあったが、当時はクラブ経営にまっしぐらのころだったから、興味はまったくなかった。その後は例の事件が起きて、銀行も証券会社も挨拶には来るものの、深入りを避けるようにしてそんな話を持ってこなくなっていた。ここにきて金融会社の信用は戻ったのだろうかと恵子は可笑しかった。
支店長は「お店にも一度顔を出させていただきます」と言って帰ったが、それにしても、 (会社を買ってどうするんだろう?) と、恵子は見当がつかなかった。ただ、この話に何か光明のようなものを感じたから、「考えさせてほしい」とだけ返事をした。その一方では、たぶんその会社を買うことはないだろうとも思った。恵子は自分で自分が分かっていた。その気があれば、その場で「買いましょう」と返事をしている。
かつての師匠三木茂吉は恵子の勘を「女彪の勘」と呼んだ。恵子は普段の99%は動かないが、1%だけ瞬敏に動き、その動きが勝ちに繋がる。信用取引で多くの財を手中にしたのもこれだった。
健との現在も、そういうつもりではなかったが、その勘が発揮された結果であることを恵子は分かっていた。あの日、吸い寄せられるように〔ぶるまん〕へ行き、瞬時のうちに健を〔鮨 小竹〕に誘った。後になって、三木が言う女彪が獲物に飛びかかる姿と似ていたかもしれないと思って自分でも恥ずかしくなったが、その後はおとなしく健に従ってきた。三木の言う「1%」は母方の祖父の血かもしれないが、「99%」を黙って従っているところは母に似ていると恵子は思っていた。
思い出せば、初めて大金を手中にしたとき、そのお金を一人で暮らしている母に上げようとした。それは秋田では家一軒を建てられるぐらいのお金だったが、母は「恵子ちゃん、あなたが持ってなさい。」と言って受けとらなかった。母は父が遺してくれたわずかな貯金で十分だと言った。
母は若いころは、洋裁学校に通っていたという。そこでデザイナーになりたくて勉強しているうちに、売れない画家の父と知り合い、結婚した。恵子から見れば、自分を捨てて、父と共に生きる道を選んだともいえる。だから、父の遺したほんとうにわずかな貯金で構わないと言う。母は100%父と共に生きたのである。恵子は健を知ってから、自分の「1%」が疎ましく思うこともあった。母のように生きられたら、自分も健の胸に飛び込むことができるだろうに。
その夜のうちに、支店長は本店の担当者を連れて、店にやって来た。挨拶だと言っていたが、たぶん店の様子を見に来たのだろう。
本店の担当者は驚きの目で恵子の顔を見入っていた。こういう視線に恵子は慣れていた。(こんな美人が、なぜあんな大金を持っているのか? もしかしたら黒い金じゃないのか?) そんな目付である。しかしこの視線のお蔭で恵子は決心した。(今回は止めておこう、) と。
恵子ママが小さい声で支店長に言った。「お店ではあの話は困りますよ。でもせっかくお見えになったのですから、どうか楽しんでいってください。」
「承知致しております。ご挨拶だけでございますから、すぐ帰らせて頂きます。」と支店長が答えた。
このとき、恵子には閃くものがあった。それは銀行側が薦める化粧品会社購入ではなく、(こんなことから、私は夜の世界から足を洗うことができるかもしれない。) ということだった。
言葉通り、支店長らは短時間で引き上げた。
恵子が見送りしようとすると、「いえいえ、こちらで結構でございます。」と低頭して言う。
恵子は言った。「そうはいきませんわ。今は貴方がたがお客様ですから。」
これも明子ママから教わったことだ。「お店に来た人は、すべてお客様。」「出迎え三歩、見送り七歩 ― また来たいと思って頂くよう必ず丁寧なお見送りをしなさい。」
外に出ると、銀行の車が待っていた。
「あの、藤岡さん。」
「はい。」
「悪いけれど、今回の話はまだ乗り気がしないの。でも、結局は大株主になったらという話よね、興味はあるの、だから話はまた持って来て頂戴。」
「はい。承知致しました。」支店長と担当者と運転手は恵子ママに頭を90度ぐらい下げて、帰って行った。
藤岡支店長が帰ってから、他の客の席に座ったとき、徳子や他の女の子たちが一人の紳士に恋の相談みたいな話をしていた。
恵子は「何か楽しそうなお話ね」と挨拶代わりに口にした。
紳士は「男の30歳はまだ子供だよ、と言っていたところだよ」と言った。
「あらあら。」他愛のない話のようだったが、恵子は健のことを思い浮かべ、ドキッとした。
夜の世界は、男と女の他愛もない話が多い。それを「あらあら」と離れた所からゆとりをもって見ていられるのも、(あの人がいてくれるお蔭) と恵子はつくづく思う。女の子たちと一緒になってオトコ談義をしていたら、ママとして示しがつかない。
その紳士が帰るとき、見送りながら恵子は (そうなのよね。男の30歳はまだ子供だと思えば、気が楽になりそう。若くったって、あの人は恵子の守護神。それはまちがいない。ほんとに、いいことをおっしゃっていただきました。) という気持で丁寧に頭を下げて見送った。そして恵子は一人で微笑んだ。(人様の言葉に敏感に反応するようになったところは、恵子もあの人に似てきたのかしら。)
その夜、恵子は1時丁度に帰宅した。健は5分遅れて来てくれた。ずっと以前に合鍵を渡しているのだが、健はまだ使うまでにいたっていない。
「今日、小田社長にニューヨークのことをいろいろ聞かれてさ、」健はソファに座って、話し出した。
今夜の健は、なかなかバスに入ろうとしない。(それならそれでもいいわ。)
と恵子も着替えないまま、ウィスキーの水割を用意した。
「日本が強くなるには、文化を世界レベルにまで引き上げなければならない、っていう話になってね。」
「ズゴイ話ね」と言いながら、恵子も健の隣にピッタリくっついて座った。
「これからの日本は、野球、サッカーを強くしなければならない。ゴルフやテニスは一流プレイヤーが誕生しなければならない。音楽や映画は世界的な賞を獲得しなければならない。ファションや食では世界をリードしなければならないっていう話になってさ。」
「あなたの社長さんは製薬会社でしょう。どうしてそんな話になるの?」
「うん。企業の力だけだとさ、〔エコノミック・アニマル〕と言われるだけで、文化産業も興隆しなければ真の大国にはなれない。経済と文化の両輪が動いて、日本は強くなるって、社長が言うんだよ。」
「それと私たちのニューヨークと、どう関係がるの?」恵子は頭を健の肩に預け、グラスを振って氷の音を楽しんだ。
「私たちのニューヨークか、いいね」
「だって、そうだもん。4泊5日、昼も夜も、私たちずうっとくっついてたわよね、楽しかったわ。」
恵子は、健と社長との話の内容がよく理解できなかった。ただ恵子は何かに夢中になっている健を見て、一つだけ分かったことがあった。(この人は、ソウルに一緒に行ったドクターといい、会社の社長さんといい、第一級の人間と会うと敏感に反応するみたい。) そのことを理解できたことが、恵子には嬉しかった。恵子は一人で健に向かって、グラスを上げて乾杯の仕草をした。
「今日はご機嫌だね。」
「そうよ。」
「この前はちょっと辛そうだったけど、ごめんな。」
「ううん、全然。『奥様』なんて言われちゃって、ちょっと気分よかったわ。」「奥様」と自分から言ってしまったが、恵子はせいせいした。(クヨクヨしたって始まらない。) 恵子は割り切ることにした。(仕事もしたい。この人も離したくない。だったら今のままの関係で、年上の女ならも年上の女らしく健の役立つようなことをして上げればいい。) そう思いながら、恵子は健に寄りかかったまま目を瞑った。
健は恵子を見ながら「その文化の発信は都会がリードしてやるべきだとさ。パリやニューヨークのように東京が、銀座が、」と言ったが、恵子が眠ってしまったようなので抱きかかえ、ベッドまで運んだ。
恵子は、ベッドの上に横にされたとたん、ニッコリ笑って両腕を健の首に巻き付けてきた。
野中の上司の牧田常務は、渋い顔をして、各支店長、各部長が提出した名簿を見つめていた。
小田社長が「新しい事業部を作るから、その部員になる候補者リストを提出せよ」と各支店長、各部長に命じていたのであった。
牧田が見るかぎり、社長の真意を汲み取って優秀な人材を候補としたのは、全体の四分の一、残りの四分の三はだいたい左遷扱い的な候補ばかりであった。
社長の意図は、会社が大きくなった現在、社員がサラリーマン化してきていることを憂慮して、将来の優秀な事業家を養おうというものであった。いわば、「小田社長経営塾」みたいなものだった。子飼いの牧田には社長の気持が痛いほど理解できた。だが気持は分かるが、策は反対だった。人事部が「新規事業部」なんていう社長の思いが伝わらないありきたりの部署名を付けたことや、四分の三の部長たちが左遷的人事を頭に描いたこと事態が当社の現実であり、創業者時代に戻りたいという気持は理解できても戻ることできないと考えていた。
病院部の名簿を見てみると、野中の名前があった。牧田は (アイツ) と舌打ちした。「アイツ」とは病院部長のことである。「病院部を二つに分けようか」と部長に相談したとき、アイツはニコニコしていたから賛成だとばかり思っていたが、自分の甘さに腹が立った。(これで当社の病院政策は遅れるな。) 牧田は野中に期待しているところがあった。そんな牧田であったが、結局は提出された候補者を全員認めた。それが牧田のやり方であった。
現在の営業体制は牧田が営業本部長のピラミッドの頂点に立っているが、それまでは西日本、中日本、東日本の3営業部のトロイカ方式が敷かれていた。
それを10年前、小田社長は3部長の中から牧田を営業本部長に選んだ。創業者の小田社長は「競争の原理」の信奉者であった。それによって会社を大きくしてきた。当社の、毎月の営業会議の席は成績順に座ることになっていた。「ドンジリが嫌なら成績を出せばいい。数字を出すためにはどうすればいいか、考えろ。」小田社長の考えは明快であった。
成績は、偶に席に変化があることもあったが、部単位では、だいたい西日本、中日本、東日本の順だった。だから本部長制にすると社長が発表したとき、誰もが西日本部長が本部長席に座るだろうと思った。だが、小田社長が指名したのは中日本の牧田だった。牧田は「絶対に人と争わない」主義だった。競争主義の創業者社長が競争しない主義の牧田を本部長に選んだのである。
一番驚いたのは牧田自身だった。以来、牧田は社長の大番頭となって、社長の補佐一筋に生きてきた。この「争わない主義+社長補佐一筋」が盤石の「牧田体制」を作り上げた。といったらきれいすぎるが、実際には「争わない主義+社長補佐一筋+大酒」だった。牧田は酒が強かった。毎晩のように部下と酒を飲み、人とは争わない、社長補佐一筋を貫いてきた。言いかえれば、争わない代わりに、酒の力で屈服させたのかもしれなかった。
しかし、ここにきて社長は、トロイカ時代を本部長時代へと脱したように、さらにはまた新たな体制を目指そうとしている。
牧田常務の視線も小田社長と同じであった。しかし、会社の舵取りにおいて、小田社長は小田社長らしく事業家精神の育成を目指そうとしているが、牧田は会社がサラリーマン化したのなら、それを徹底して組織にすればいいと考えていた。そのために中枢としての戦略室を作るべきだと考えていた。それには野中のような戦略性もった男が必要だと考えていた。
だが、牧田は部下に先手を打たれた。そうであっても牧田は病院部長の打った手を飲んだ。それが牧田の主義だった。人とは決して争わない、しかし最後には勝つ。
(XI. I’ve Lost You へ 続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる ☆ 作〕