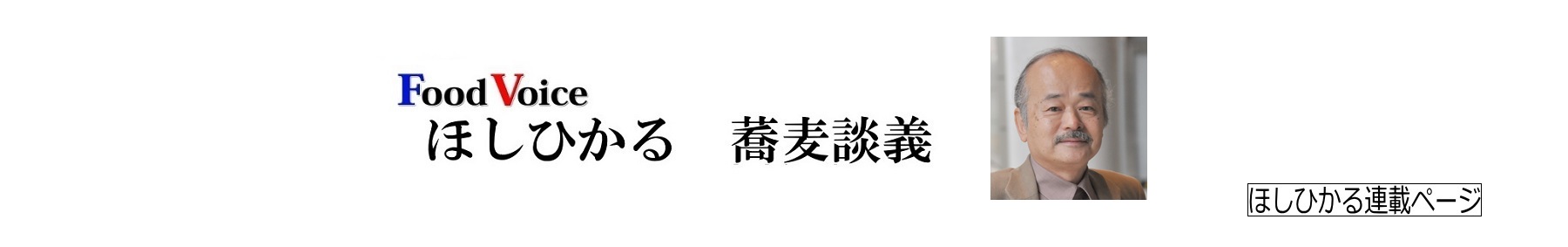第245話 「You 'd be so nice to come home to」
2025/12/06
蕎麦屋の「菊谷」でジャズコンを実施した後、ご参加されたSさんからこんなメールをいただいた。
― お話してもただご迷惑だと思っておりますが、昨年6月に29年間公私共に過ごしたパートナーが他界し、「私が本当に帰れる場所はもうない」と思って過ごしています。
曲名の本来の意味を知ってもともと好きだった曲でしたが、あの日からさらに「You 'd be so nice to come home to」は私の人生ソングとなりました。―
この曲は、当日演奏されたものの一つだった。コール・ポーターという作曲家が1942年に発表した曲で、ヘレン・メリルやジュリー・ロンドンなど多くの歌手が歌い、またインストゥルメンタルとしてもカヴァーされ、ジャズのスタンダードとなった。
曲名は「あなたが待っている家に帰って来られたらすばらしいだろう」という意味であろうが、日本では「You 'd be so nice to come home to」という題名で普及していた。それはニューヨークのため息といわれたヘレン・メリルや、バラ色のビロードのようなハスキーな声のジュリー・ロンドンが歌い出す、最初の「You 'd be so nice to come home to」の歌詞があまりにもインパクがあったせいだろう。
Sさんのメール文はご覧の通りわずか数行だというのに、大人の、珠玉ジャズ小説を読んでいるかのように、インパクトがあった。しかも、 私よりも若い方だけに感慨も一入である。
話は少し逸れるが、このメールに刺激され、若いころ読んだ河野典生の小説のことなどを思い出した。河野は大藪春彦と共に日本のハードボイルド小説の草分けといわれた作家だったが、彼の小説にはジャズのフィーリングがあった。ただし、こちらの方はイキがった若者が主人公であった。
元々ハードボイルドというのは、アメリカのレイモンド・チャンドラーやダシール・ハメットあたりが拓いた探偵小説の分野だが、約半世紀して河野や大藪によって日本にももたらされた。
その主人公は、たいていが男の匂いがしていた。どこが男の匂いかというと、たとえば喧嘩なども多少は心得ているというようなところだったのかもしれなかった。
そういえば、けっさくな思い出が今フト蘇ってきた。それは高校時代の授業中のことだった。激しい描写に赤線が引っ張られた本が回ってきた。大藪春彦の『野獣死すべし』だった。皆は、先生に見つからないようにと、ドキドキしながら回し読みしたものだった。それらの主人公は、たいていはたとえていえば裕次郎が太陽を見詰めながら眩しそうな顔をしてタバコを吸って、それをポーンと川に投げ捨てて、後も振り返らないで、立ち去って行くといような、どうってことはないけれど、カッコつけて、イキがっているような、とはいっても、それでも彼の行動には、オトコのモラルとか、オトコとしての筋は通す、美学みたいなものが見られたものだった。
ト、こんな風に描けば、ハードボイルドは、やはりドラムスとか、サックスとか、トランペットとかのジャズがお似合いであることを理解してもらえるだろう。そして田舎の高校生の耳には外国人女性歌手のハスキー・ボイスもたまらなく刺激的な楽器だった。そうしたジャズ・シンガーの一人にヘレン・メリルもいたのであるが、こうしたジャズやハードボイルドは、時代といえばそうだが、若さの叫びみたいなものだったろう。
今でも深夜ラジオで聞いていた、トランペットやドラムスのビートが耳に残っているし、女性シンガーの声は子守唄のように心地よい。
しかし、人間も、社会も、時代も、二度とあの日に帰ることはできない。
だからこそ、「あなたが待っている家に帰って来られたらすばらしいだろう」なのである。
どうやら、いい曲というのは、どこかセンチメンタルなものがあるようだ。
それは、ふと訪れた懐かしい親友との出会いに似ているのかもしれない。
数日後、「こんなメールを頂いたよ」と店主に話すつもりで、「菊谷」に行ったが、昼時でとても忙しそうだった。だから、遠慮してそのことは口に出さず、お蕎麦だけ頂いて、そのまま帰らせてもらった。
頭の中で「You 'd be so nice to come home to」の歌詞を繰り返しながら・・・。
参考:レイモンド・チャンドラー『大いなる眠り』『かわいい女』『ザ・ロング・グッドバイ』、ダシール・ハメット『マルタの鷹』『血の収穫』、黒沢明監督『用心棒』、河野典生『殺意という名の家畜』『明日こそ鳥は羽ばたく』『いつか、ギラギラする日々』、大藪春彦『野獣死すべし』
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕