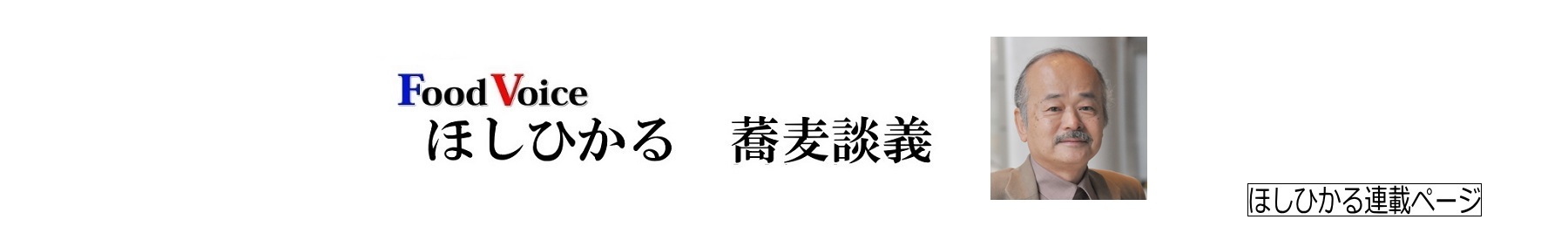第246話 「Black Coffee」
2025/12/06
久しぶりに銀座の「ランブル」に行った。林先生(江戸ソバリエ・ルシック講師)と打合せをするためだったが、美味しいコーヒーは、やはり美味しかった。
そんなことで、気をよくしたせいなのか、本屋に寄ったとき、アガサ・クリスティの『ブラックコーヒー』が目に入ったので、その夜に読んだ。
本当は、蕎麦などの食べ物に関わっている者にとっては、飲食物で殺人事件を起こしてもらいたくないのだが、昔の小説だから目を瞑るとして、たしかにお茶、紅茶、コーヒーのなかでは、コーヒーの方が事件を呼びそうだなと思いながら頁を捲った。そして、それについて述べてみたい衝動にかられるのだが、これはミステリーだから、よした方がいいだろう。
ところで、最近は美味しいコーヒーを供してくれる店が減少し、企業が経営するチェーン店か、コンビニのコーヒーが増えてきて、どれも同じ味のファストフードの代表になってしまった。少し前までの、専門家が淹れるコーヒーはそれだけ奥の深いミステリアスな飲み物であった。だからこそコーヒーが推理小説の材料となったのであるが、現代では小説のネタにならないかもしれない。
「ブラック・コーヒー」といえば、ジャズに有名な曲がある。ポール・フランシス・ウェブスター作詞、ソニー・バーク作曲、1948年の作品だ。
こちらの方は、「家で貴方を待つしかできない私」というワケアリの女性が、涙を浮かべながら苦いコーヒーを飲んでいるといった歌だ。初めはサラ・ボーンが歌っていたが、後にペギー・リー、ジュリー・ロンドンが人気となった。
声量のあるサラより、ハスキーな声でけだるそうに歌うペギーやジュリーの方がミステリアスなブラック・コーヒーにはぴったりだったからだろう。
私は中・高生時代に、女性ボーカルのジャズをよく聞いていた。ブラック・コーヒーの三人の歌姫はもちろん、ビリー・ホリデイ、エラ・フィツジェラルド、アニタ・オディ、カーメン・マクレエ、ジューン・クリスティ、クリス・コナー、ヘレン・メリルの声も好きだった。映画『真夏の夜のジャズ』でアニタ・オディを聞いたときは、異国の熱い音楽に痺れたものだった。
彼女たちはいずれも1910年代.20年代に生まれた歌手である。だから、いま聞いても、女性ジャズシンガー界の老舗のような本物感と懐かしさがたっぷり味わえる。
とにかく彼女らは私の子供時代の夢の歌手だったが、それはそれで原点として憧れをいだきながら、たまに若い歌手にも耳を傾けることもある。
サリナ・ジョンーズ、シェリル・ベンティーン、ダイアナ・クラール、ジャッキー・ライアン、ローリー・ホィラー、ニッキ・パロット、ソフィー・ミルマンなどがお気に入りである。
なかでも最高にフィットしているのはサリナ。私と同じ歳だからだろうか、黒人特有の良質の生ハムがまとわりつくような声が素晴らしい。
それからダイアナ(1964年生)とソフィー(1983年生)もいい声だ。とくにダイアナ・クラールの「When the curtain comes down」には泣けてくる。
昨年ニューヨークの「ブルーノート」に行ったとき、店の冊子を見ていたら、ダイアナ・クラーク出演の案内が目に止まり、「あゝ、日程が合っていたら、生が聞けたのか~」と歯ぎしりしたものだった。
話をブラック・コーヒーに戻すと、ニッキ・パロット(1968年か69年生)もこれを歌っている。なかなか上手いし、雰囲気もある。だがそれは「ランブル」のようにたいへん美味しいコーヒーであるが、ペギーやジュリーのようなミステリアスさはない。時代がコーヒーの味も雰囲気も変えるのである。
そのことを一番よく知っているのはニッキ・パロット自身なんだろう。だから、2010年に収録したき、「ジュリー・ロンドン&ペギー・リーへ捧げる」とサブタイトルを付けている。
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕