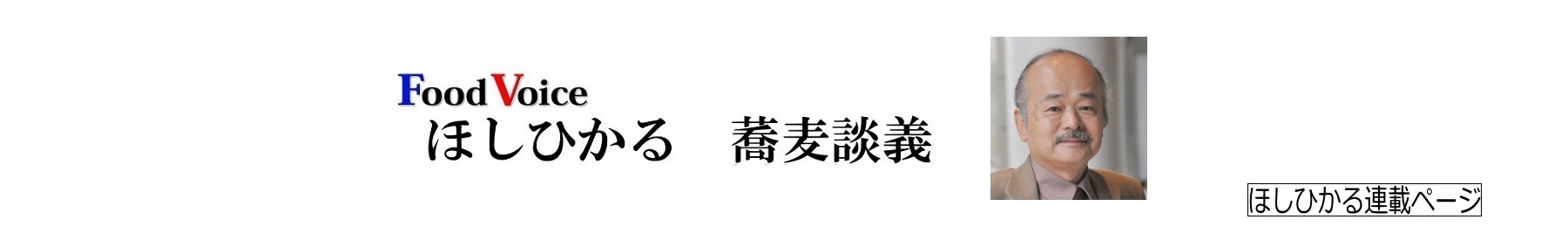第941話 五月の薔薇
2025/12/06
☆詩人・大岡信の《桜海老ちらし鮨》
池袋➡元町・中華街行は、特急電車一本で約50分。
元町・中華街駅で下車すると、アメリカ山公園の満開の薔薇が出迎えてくれた。
そこからイングリッシュ ローズ ガーデン、イギリス館、111番館を左に見ながら、神奈川近代文学館の方へと雨の舗道を歩いて行く。この辺に来るときはいつも文学館にある「鮨喫茶 すすす」で昼食をとることにしている。すぐ先に霧笛橋が見えた。あそこが文学館、私は入口を入った。
すると、エッ! 「大岡信 言葉を生きる 言葉を生かす」展が開催されているようである。知らなかった。
私は今日、ここで昼食を済ましてから、ある茶会に参加するつもりだった。これでも時間にゆとりがあるはずだったが、展示を観るとなるとちょっと慌ただしい。でもせっかくだから、すべてをこなそうと、先ず「すすす」へ。
この鮨喫茶は《鮨×文学》をテーマにしたランチをいつも提供している。『小説から読み解く和食文化』を上梓し、また『蕎麦文学紀行』を連載中の私も《蕎麦×文学》がテーマなので、同志感からお気に入りというわけだ。
今日は、詩人の大岡信が三島市出身ということから駿河湾産の桜海老を使った《桜海老ちらし鮨》ということだった。そうなんだ。以前に、駿河出身の蕎麦屋さんがいたが、駿河で《桜切り》といったら《桜海老切り》ですよ、と言われたことがあった。さっそく《ちらし鮨》を頼むと、今日はこれで最後だという。やはりこちらを先にして正解だった。私は小雨けむる東京湾を眺めながら駿河湾の《桜海老》を味わった。もしかしたら、大岡家の食卓にものぼっていたかもしれないなんて妄想しなが頂いたけれど、この妄想がわいただけでも食べ甲斐があった。

さて、展示を拝観しなくてはと思ったが、そうだその前に冬木先生にメールしてみよう。「神奈川近代文学館に来ましたら、大岡信展でした。驚きました」。
冬木れい先生は料理研究家、ご主人は大岡信のご長男で作家の大岡玲氏。ご夫婦と、巣鴨の「栃の木や」や麻布の「更科堀井」でご一緒したことがある。
文学館では、大岡信が遺した創作ノート、原稿、書、書簡などを「大岡信文庫」として保存しているということで、それが展示してあった。
時計を見ると、急がなければならない。玄関を出たところでメールを見ると、冬木先生から返信がきていた。「4/26 夫・玲が講演した『父を語る』も盛況でした。また、義父が義母に出したラブレターも展示してありますよ」とのことだった。
玄関の本の売場には大岡信の著書以外に、先日冬木先生から頂いた『大岡博 評伝 拈華微笑』が置いてあった。歌人の大岡博は歌人・詩人の大岡信の父に当たる人である。
頂戴した本にはきれいな字で歌が書いてあった。字の薄墨の色にも気品があった。父と子の絆の書だった。
浪の穂に 裾洗わせて 大き月 ゆらりゆらりと 遊ぶがごとし
大岡博 作 大岡信 書
『大岡博 評伝 拈華微笑』のサインよ
☆nokkoさんの茶会
霧笛橋を渡ると大佛次郎記念館がある。入口の右側の垣根に赤い薔薇が咲き誇っていた。
部屋の入口で、nokkoさんが笑顔で迎えてくれた。ソバリエのともこさんにご紹介され、nokkoさんがパーソナリティをやっているインターネットラジオの『花咲くだんす』に数回出演させてもらった。また彼女は他に喜泉蘭昇の名で日舞、そして今日のように有結流花咲テーブル茶道教室をもっておられ、今日はその茶会である。
初めに横須賀の和菓子司「いづみや」の柿色の薔薇の和菓子を頂いた。nokkoさんの説明によると、薔薇は花の色によって花言葉が違うが、オレンジ色の薔薇の花言葉の一つは「絆」だとのこと。薔薇は五月の花、絆はnokkoさんのラジオ、踊り、お茶とのご縁のある人たちとの絆の意味だろうか。続いてお薄を頂く。和菓子のあとの抹茶は美味しい。
最近、美味しさを追究するようになってから、単品だけの美味しさではなく、相性のいい料理というものを意識するようになった。最初は、蕎麦とつゆだった。それから国外で食味する機会があってから、とくにソース、つゆ、スープ、お茶など汁物との組み合わせへの関心が高くなった。だから抹茶と和菓子はよく合うとしみじみと実感する。
それにしても抹茶茶碗に猫ちゃんの絵が描かれているのには驚いた。理由は大佛次郎が「猫は生涯の伴侶」と言って可愛がっていたからだという。作る人もよく作陶したものだが、それを見つけてきたnokkoさんも面白い人だと思う。猫と薔薇、大佛次郎記念館での五月の茶会のコンセプトは十分に伝わった。
テーブル茶会は、昔のイギリス宮廷でアンナ・マリアが始めた午後の紅茶会と似ているところがあると思う。詳しく知らないが、インド産のアッサムやタージリン、中国産のラプサン・スーチョン(立山小種)やキーマン(祁門)などに合うケーキを楽しみながらの団欒だったらしい。
日本の茶会では昔から、「一期一会」という言葉がある。何かむずかしそうだけど、映画にもなった『日日是好日ー「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』の森下典子さんは「会いたいと思ったら、会わなければいけない。花が咲いたら、祝おう。嬉しかったら、分かち合おう。恋をしたら・・・。それがたぶん、人間のできる、あらんかぎりのことなのだ。だから、だいじな人に会えたら、共に食べ、共に生き、だんらんをかみしめる。一期一会とは、そういうことなんだ」と言っている。
好日の茶会は終わった。私はnokkoさんにご挨拶して、大佛次郎館の外に出た。
このときメールの着信音がした。出発前にある方へお会いしたい旨のメールをお出ししていたが、その方から了解のご返事だった。そういえばこの方のメールアドレスも猫の名前だった。
横浜の海からの心地よい風が右頬を撫でた。反対側のイギリス館のイングリッシュ ローズ ガーデンは見事な薔薇の海。ここを抜けて駅へ向かうが、小雨に揺れている薔薇は小波のよう。
今日もいろんな出会いがあった。これも一期一会というのだろうか。しかし生きものには必ず別離にぶつかる。薔薇はそれを知っているからこそ、今が盛りと咲き誇るのだろう。
エッセイスト
ほし☆ひかる