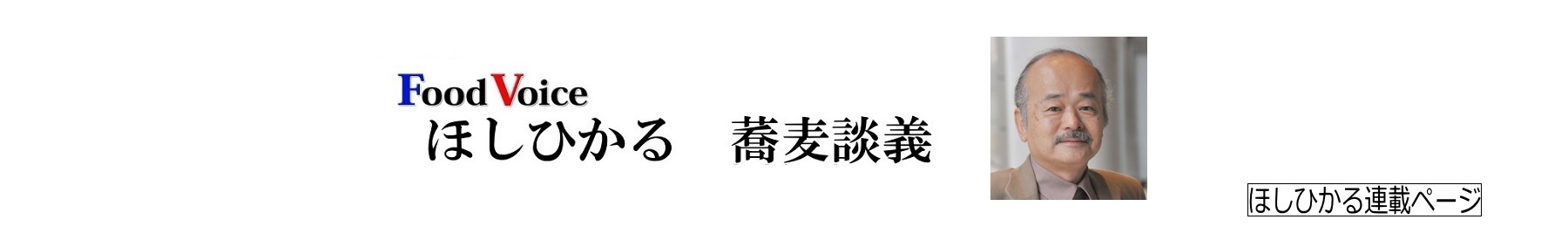第703話 羽を付けた唐辛子
2025/12/06
『世界蕎麦文学全集』物語 45
内藤とうがらしプロジェクトが、農水省-日本農業賞の食の架け橋の部において優秀賞(2021年1月29日)、経産省-全国地域ブランド総選挙において優秀発展賞(2021年2月6日)のダブル受賞した。
今日、そのお祝を兼ねて「内藤とうがらし®10thAnniversary~感謝&新宿エールの日~」がJA東京アグリパークで開催された。
プロジェクト代表の成田重行さんとは長いお付合いのうえ、これまで大変お世話になっているので、お祝に駆付けた。
☆内藤とうがらし物語
せっかくだから、内藤とうがらしと、プロジェクト代表の成田重行さんについてご紹介しよう。
そもそも、栽培唐辛子の始原地というのはメキシコやペルーである。
それが日本に伝来したのは15世紀半ば、ポルトガルの宣教師が種子島経由で豊後国へやって来て領主の大友家に献上したと伝えられている。
そのときは胡椒の代理品のような形で上陸したため、「胡椒」とか「南蛮胡椒」とかよばれていたが、そのうちに略して「蕃椒」、そして「唐辛子」というようになったらしい。ただし九州、とくに肥前では「唐辛子」は「唐枯らし」に通じているため、土地柄から伝来当初の「胡椒」の方が多く使われていた。
ただ伝来したとはいえ、現代からみればまだ九州や近畿の一部にかぎられていた。そのころ来日したルイス・フロイスは《酢漬け唐辛子》などに利用していたと記述しているから、そんな使い方だったのだろう。そういえばソバリエさんからイタリアのお土産に、《オリーブ油漬け唐辛子》というのをいただいたことがあるから、そんな感覚だろうか。
とにかくその間、唐辛子は日本から朝鮮半島に伝わって行き、かの国ではキムチが革命的に変化した。その唐辛子が秀吉の朝鮮出兵時(1592~98)に日本へ逆輸入されて入って来たため、いまでも唐辛子は朝鮮半島から伝わったと言う人がいるくらい、当初はわずかだったのである。
それが、徳川政権が江戸開府(1603年)すると、唐辛子は新都江戸にも入ってきた。
それからまもなくして(1625年)、両国薬研堀の中島徳右衛門が《七色唐辛子》を開発した。当時の薬研堀には医者や薬屋が多く住んでいたので、そこから徳右衛門は漢方薬様の「七味」を考案したのである。いわば、中島徳右衛門は江戸唐辛子の歴史からみて、最初の重要人物となったわけである。
その30年後には、京・清水寺門前の七味屋本舗も伏見唐辛子を使った七味を売り出し、また徳右衛門から110年後に信州・善光寺門前が続き、これが現在の「三大七味」として知られている。
目を江戸に戻せば、芭蕉が深川の芭蕉庵に栽培していた唐辛子を1692年ごろにこう詠じている。
青くても あるべきものを 唐辛子 芭蕉 (『俳諧深川』)
また江戸住の芭蕉の弟子野坡(1662~1740)も唐辛子を詠じているところからすれば、江戸では栽培唐辛子がよく見られたのであろう。
石臺を 終にねこぎや 唐がらし 野坡 (1694年刊『炭俵』)
さて、本題の《内藤とうがらし》であるが、新宿で唐辛子が栽培されるようになったのは8代将軍(1716~45)吉宗のころのようだ。今の新宿はもともと信州高遠藩内藤家の領地であったが、江戸時代の大名屋敷や寺院は広大な土地だったから、当然敷地内には畑があり、野菜栽培が行われていた。内藤家下屋敷では、雇われていた小作人が八房唐辛子や南瓜などを栽培していたという。
ところが江戸中期になると人口が増え、外食屋としての蕎麦屋が林立するようになった。当然江戸蕎麦が盛んとなると共に七味唐辛子が薬味として使われるようになり、お蔭で内藤新宿の畑は季節になると真っ赤に染まるほどだったという。
江戸唐辛子の歴史からすると、内藤家下屋敷の無名の小作人の寄与は大きかったのである。
そしていつのころからか、薬研堀の七色唐辛子売りの口上が生まれたりした。
♪そもそも薬研堀の七色唐辛子とは、由緒いわれ故事来歴がございます。
今を去ること三百有余年前・・・、かの徳川の御名君と謳われた、三代将軍家光侯の御時代は寛永二年長月、菊の御宴のみきりに、将軍家に献上奉りますれば、ことのほかの御感に入り、徳川の徳の字を賜って、山徳の商標を付ける事と相成りました。
薬研堀の七色唐辛子とは、何が入っているかと申しますと、
まず最初に取り合わせまするは、武州川越の名産で黒胡麻、
次は紀州有田名産で蜜柑の粉、
江戸内藤新宿は八ツ房の焼き唐辛子、
四国へ参りまして高松の国は唐辛子の粉、
東海道を上りまして静岡は浅倉の粉山椒、
大和の芥子の実、
野州日光の名産で麻の実、
七色が七色ともに香り、大辛・中辛・小辛に辛ぬき、何しおう、お江戸の薬研堀、家伝で合わす七色は、世の皆様のお好みに叶う元祖の匙加減、お江戸の薬研堀の出張販売でございます。♪
この口上から七味の材料が明らかであるが、成田さんの解説によると、唐辛子が二種入っているところが工夫らしい。つまり高松産は辛味、内藤新宿産の八房は風味を活かしてのことだという。現に学習院大学の品川教室がアミノ酸含有量を調べたところ、新宿産の八房には抜群のアミノ酸量が含んでいることが判明した。そのことを江戸時代の徳右衛門は知っていたというわけである。
なお、文中では「七味」「七色」の両方を使って分かりずらいかもしれないが、昔の西日本は「七味」、江戸では「七色」とよんでいたが、今は統一されて「七味」といっているから、ご了解願いたい。
話を戻すと、新宿が宿場町として発展すると段々畑が少なくなってきて、内藤唐辛子の栽培も低下傾向となってきた。
そして明治維新後は東京全域が近代化され、新宿はその中心の一つとなったため、田畑は消滅し、「内藤唐辛子」の名前すらも人々の記憶から無くなってしまうことになった。
そこへ登場するのが、現在の内藤とうがらしプロジェクトを率いる成田重行氏である。
彼は、先ず日本スローフード協会として、江戸時代の食の研究・再現、種の多様性の情報収集・絶滅種再現をテーマに活動していた。
そのころ同じ方向で活動していた江戸東京伝統野菜研究会の大竹道茂氏と出会って江戸野菜の復活に関心をもった。この出会いは偶然ではない。成田氏の目的が明確であったからこそ必然的に出会ったのである。
そして成田氏は事務所を置いていた新宿に絞り、新宿の歴史調査を始めた。その結果、江戸時代には新宿で内藤唐辛子や内藤南瓜が栽培されていたことを知り、ぜひそれを復活させたいと思うようになった。歴史を知ることは物事の遺伝子を把握することである。これも成功の鍵の一つであった。
成田氏は、その過程で内藤唐辛子は八房類であることを突き止めた。
現在の日本における主な唐辛子は次のようなものだが、八房類というのは鷹爪とともに世界で人気の唐辛子である。
《辛い唐辛子》
・鷹爪(本鷹・三鷹・熊鷹など、有名なのは香川本鷹・栃木三鷹)
・八房
・伏見
・榎実
《甘い唐辛子》
・獅子唐辛子
・スコッシュ類のピーマン
・伏見類のパプリカ
そこで成田氏は、八房の最古の種を筑波の独立法人農産物資源研究所から数粒分けてもらい、それを山梨の畑で3年間隔離して育てて固定種を完成させ、あらたな《新宿内藤とうがらし》(2013年)が蘇った。
それからだった。成田氏が持ち前の情熱とプロデュース力をさらに発揮するのは・・・。成田氏は豊富な人脈から、生産者、産業、料理人、地域、学校を巻き込み、イベント、情報発信につとめ、今やオール新宿で《内藤とうがらし》を名物にしてしまった。かつてのように新宿が真っ赤に染まったのである。
かくて成田重行氏は、江戸唐辛子の歴史において記録に残る人物となった。
ところで、嘘か実か知らないが、唐辛子にはこんな逸話がある。
芭蕉の弟子の其角が、唐辛子の句を詠じた・・・、
赤とんぼ 羽をとったら 唐辛子 其角
すると師の芭蕉翁はこう訂正してあげたという。
唐辛子 羽をつけたら 赤とんぼ 芭蕉
翁の句は優しく、夢がある。
《内藤とうがらし》もまた羽をつけて東京の空を飛んでいるのである♪
『世界蕎麦文学全集』
85.『俳諧深川』
86.『炭俵』
文:江戸ソバリエ認定委員長 ほし✫ひかる
《内藤とうがらし》と芭蕉の句:ほし絵