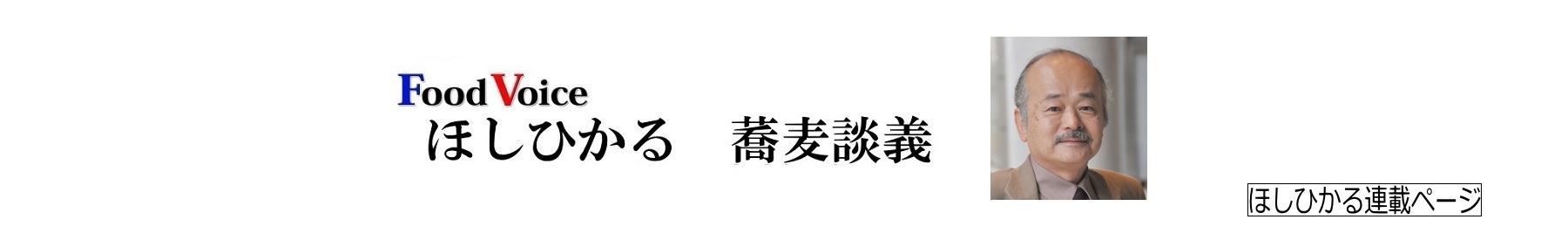第951話 したたかな〝雅〟
2025/12/06
龍谷大学主催の「したたかな京料理」というシンポジウムが開かれました。
開場は11時、開会は11時半とのこと、昼食を迷いましたけど、終わってからでいいかなと思いながら会場のドームホテルに入りました。
ところがシンポジウムでは、下記のように、京料理の代表のような《飛龍頭》、《白和え》、《鱠》、《松風焼き》を京都の名店が作ったものを試食するという会でした。
*《飛龍頭》:たん熊北店、美濃吉本店竹茂楼、たん熊北店、木乃婦
*《白和え》:菊乃井、瓢亭、菊乃井、直心房さいき
*《鱠》:清和荘、萬亀楼、清和荘、竹林
*《松風焼き》:なかむら、レフェルヴェソンス、なかむら、大和学園京都調理師専門学校
(なかには同店で2名の料理人が提供された料理もあります。)




小さな一品とはいえ、16碗、だから11時半開始に、納得しました。
もちろん、16品すべてが甲乙つけがたい滋味というか、和の味が舌にも心にも染みる逸品でした。
とくに《松風》には、在原業平と松風の須磨の浦での悲恋の別れという伝説をもとにした料理ですから、頂くだけではなく須磨の浦を訪れてみたいという気になります。こんな物語性をもった逸品が和食の奥深さを醸し出しているのかと思います。
ところが、このように京料理の代表のような雅な逸品なのに、驚くことに外国由来というのもあります。
油脂分のある《飛龍頭》がボルトガル由来というのは何となく分かりますが、正月料理に欠かせない紅白の《鱠》が、もともとは中国で肉を細く切った《膾》だったというのには驚かされます。それが日本に伝わって、魚や野菜を細く切った物に変わったため、字も《鱠》になったそうですが、複雑さもわいてきます。たぶん韓国の《ユッケ》も、日本の《刺身》もこの線から生まれたのでしょう。なにせ日本史(『日本書紀』)のなかで、最初に出てくる料理が《鱠》ですから、古代とはいえ食文化の国際的な拡がりを感じます。
生の料理、切る料理が和食の基本であることに誰も異論はないと思いますが、《膾》《鱠》の話を聞きますと、和食とは何か、または日本人とは何かということをしっかり考えなければならないと思います。
そういわれれば、「嵯峨野」というもっとも雅で大和らしい地名も唐由来だと聞いています。本名神野親王(後の嵯峨天皇)は唐に憧れて、長安(陝西省西安)の北にある嵯峨山(サツガツサン)にちなんで嵯峨野と名づけられたといいますから、「雅」こそが「したたかさ」だろうか、和食も、日本人もしたたかなんだろうかと考えてしまいます。
江戸ソバリエ協会
ほし☆ひかる