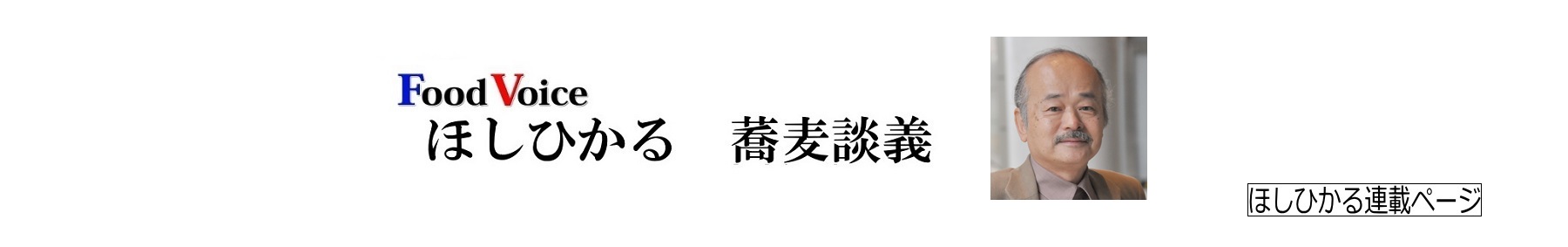第956話 蕎麦はお江戸日本橋
2025/12/06
~ 江戸四大食を世界の食文化遺産に ~
月刊『日本橋』の堺社長様のご紹介で「日本橋東ロータリークラブ」(会場:ロイヤルパークホテル)で「江戸の蕎麦」の話をさせていただきました。
日本橋は江戸蕎麦誕生の地といっても過言ではないくらいですから、江戸蕎麦の話のし甲斐があるというものです。ですが同時によそ者の小生が、日本橋の伝統を背負っておられる方々の前でお話するのは怖いところもあります。それでもやはり江戸蕎麦のためにと頑張りました。
さっそくですが、先ずは江戸蕎麦の定義としまして、蕎麦屋の蕎麦という点があります。つまり蕎麦屋の最初は江戸初期の、浅草の《正直蕎麦》か、日本橋の《けんどん蕎麦》のどちらかだと思われます。
そして、世界的に見ましても、重要なのは《ざる蕎麦》の誕生です。つまり世界の麺は、1)汁なし麺、2)汁あり麺という形をとっていましたが、江戸蕎麦である《ざる蕎麦》は3)付け麺という形をとった画期的な商品だったのです。
その《ざる蕎麦》の祖はどこかといいますと、1700年代の洲崎の伊勢屋伊兵衛か、日本橋の越後屋かのどちらかだろうとされています。
という具合で、江戸で最初の蕎麦屋は日本橋かも、蕎麦の革新的な逸品《ざる蕎麦》の祖先は日本橋かもというわけです。
その他にも日本橋は、《ぶっかけ》《鴨なん》《しっぽく蕎麦》《天ざる》など多くの逸品が誕生しました。状況的には「蕎麦はお江戸日本橋」と言っても過言ではないでしょう。
そんな蕎麦の日本橋ですが、また《鰻丼》も《天麩羅》も日本橋生まれです。
蒲焼は各地にあったのですが、中村座の金主の一人・大久保今助という人が飯付きの江戸前《鰻丼》を考案したのです。また江戸前《天麩羅》の祖は、味付き衣の《長崎天麩羅》ですが、江戸では誰かが、天つゆで食べるようにしたのです。これらに両国橋で始まった《握鮨》を加えたのが「江戸四大食」とよばれるものですが、よく見ますと四大食は隅田川一帯から拡がり、やがて江戸はこれらの専門店が軒を並べるようになったということになります。
さらに世界に目を移しますと、外食店が世界の標準的な形です。消費者は外食店に入って席に着いてから、蕎麦を食べるのか、鰻丼を食べるか決めるわけです。
しかし専門店化しました江戸では、消費者は蕎麦を食べたかったら蕎麦屋へ、鰻丼を食べたかったら鰻屋へ行くという行動をとるのです。こうした食文化のちがいは、面白いものです。
ですから、隅田川一帯から始まった江戸四大食を世界の食文化遺産にとも願っているところです。
江戸ソバリエ
和食文化継承リーダー
ほし☆ひかる