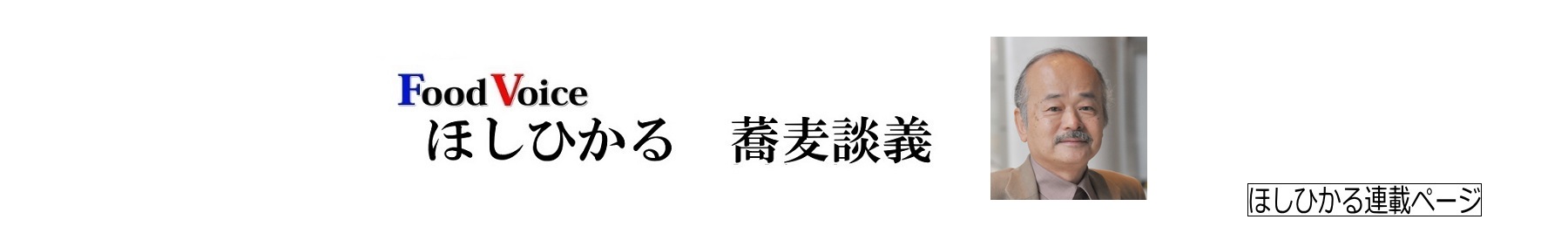第298話 武奈伎
2025/12/06
万葉歌人の大伴家持が「武奈伎(鰻)は夏痩にいい」と歌ったからなのか、夏になると鰻の絵や「う」の字がやたらと目に付く。
だからというわけではないが、「かんだやぶ」のご主人と知人の季刊『うなぎ』編集長をお誘いし、江戸ソバリエの仲間と日本橋「大江戸」に鰻を食べに行った。
打水がしてある玄関から三階に通されると、そこは広いお座敷だった。床の間のお軸や置物が年代物のようだ。とくに左手の大きな屏風は金箔の漆絵だろうか、豪華だ。
小説『火事息子』は赤坂の名店「重箱」のほぼ実話だという。初代は厚木の田舎の次男坊だったが、文化・文政のころに江戸へ流れて来て、縁あって鰻屋になるというところから始まるが、この「大江戸」さんにも似たような物語があるのだろうな、と思いながら座った。
卓の上には手拭地の膝掛が備えてある。広げてみると大きな鰻の絵が踊っている。昔、「うなぎ」という映画があったが、あれにも立派な鰻が出演していた。それから子供のころ、雨が上がるとおじさんたちが濠で鰻取りをしていたナ、なんてことを思い出したりしていると、和服の仲居さんが手をついて「膝掛はお帰りの折にお持ち帰りください」と挨拶された。
さっそくその膝掛を広げ、先ずお酒を頼む。
江戸の後期、美味しいお酒を頂けるのは高級蕎麦屋と高級鰻屋だったという。両方ともに二階のお座敷、だから逢引の隠家として利用されることが多かったと聞く。とくに鰻屋は客の顔を見てから割き始めるから、部屋に入ってから小一時間は待たされる。だからお酒をちびりちびりと飲るわけだが、飲みすぎると鰻が不味くなるから、お新香を肴にお銚子一本を舐めるようにゆっくりと・・・、それでも片手が余っているうえに、誰も来ない。ついつい手が連れの女の膝の上を這うというような場面を映画か何かで見たことがある。
しかし、現代は客を待たせるようなことはしない。前菜が出る、お新香も、お吸物も出る。今日の前菜は蓴菜に鱧だ。お新香には飴色をした奈良漬が必ず入っている。この飴色の奈良漬はけっこう高い。
私は九州佐賀の出身だが、佐賀は酒造りが盛んなためか、奈良漬も名物だ。夏のお歳暮は各家庭で奈良漬を贈ったり、贈られたりしているから、どの家庭にも奈良漬がある。ただ最近の浅漬け傾向から、奈良漬も浅漬物が増えてきた。これは粕のまま少し太めに切って食べると結構美味しい。
それから出てくるのが、鰻の《白焼》だ。それを収めた漆器も品がいい。輪島で特注した物だ、とご挨拶に見えたご主人がおっしゃった。
この《白焼》は山葵醤油で食べるのが旨い。《白焼》を食べる度に醤油がなかった万葉時代には、鰻をどう料理したのだろうか?どうやって食べたのだろうか?との疑問がわくが、誰も答えられない。
次が定番の《肝焼》、噛むと僅かな苦味が舌に沁みる。これが肝の魅力だ。老舗ならではの年期を経たと想わせる垂れに浸けた肝を激しい火で焙っているところが見えてくる。
それから本番の《蒲焼》だ。驚くほどの大きめの丼は佐賀有田の特注だという。蓋を取ると、あゝ!堪らない匂いだ。鰻が身体にいいというイメージは、このたらりと垂れ落ちる「垂れ」の誘惑されるような匂いのせいでもあろう。
編集長さんのお話によると、鰻は大井川の「共水」だという。「幻の鰻」ともいわれているらしく、上品な味だ。垂れはやや甘さを抑えてあるから、上品な「幻」とよく合う。
鰻は「美味しさは素材で決まる」と言う人もいれば、「タネの出所より、焼き加減」と言う人もいる。「焼き加減」と言う人は「鰻はやっぱり江戸だ。強い火で一気に焼き上げる」と付け加える。それに山椒をチョッピリ。
鰻もそうだが、魚などは、「頭から食べるべきか、尾からか」なんていう話題になることがある。魚ばかりか、大根や山葵もまたそうである。「頭から擦るべきかす、尻尾からか」と。しかし、そこまで微妙な味の違いが判ったらたいしたものだ。
それにしても、刺身、ざる蕎麦には山葵、熱いかけ蕎麦やうどんには唐辛子、ラーメンには胡椒、鰻には山椒が合うことを知ったのはいつからだろう。
最後の《デザート》はマンゴーとさくらんぼだ。フルーツは甘くて美味しすぎるぐらい、美味しい。日本の農業のソフトウェアはフルーツもお菓子のように甘く美味しく作り変えた。もう菓子類が不要なくらいだ。
もし、大伴家持がこの席にいたのなら、おそらく「鰻も、フルーツもみな旨い!」と絶句し、万葉歌を作るどころではなかったろう。
お蔭で夏の一日、見事な器に盛られた美味しい鰻を立派なお部屋で頂く幸せを満喫できたが、主役はきっちり《鰻》であったところが、さすがであった。
参考:久保田万太郎著『火事息子』(中公文庫)、今村昌平監督「うなぎ」、「重箱」跡(東浅草2-17-17)、
江戸食シリーズ=第298話「武奈伎」、第242話「鮨屋の板前にて」、
〔江戸ソバリエ認定委員長、江戸食文化研究会会員 ☆ ほしひかる〕